DIPROニュース
ものづくりの知的資産であるソフトウェア・パッケージ製品について
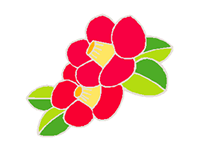
明けましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になりまして、心よりお礼申し上げます。
新年に当たり、少し視線を上げた論点:ソフトウェア製品(以下PKG)を開発・所有していくことの重要性を、ここで取り上げさせていただきます。まず、CAD/CAE/PDMなどPLM分野のPKGを代表例として、その価値を述べたいと思います。
①PLM PKGは、ものづくりの知識をデジタル化したもので、過去30年間発展を重ねてきており、今後10~20年の蓄積で、その知的資産は膨大なものとなっていくものと思われます。例えば、製品のモデリングツールレベルから製品の性能・機能のベースを決めるナレッジ化へ技術の深度を増しつつあり、また、販売業務から保守業務までを含む全製品情報のインフラの役割へと大きな広がりを持ちつつあります。
②PLM PKGは、技術者が毎日使用して製品開発を進めており、開発における必須の道具となっています。ITであるPKGが技術者を差し置いて製品開発の主役になることはあり得ないが、単なる道具にしか過ぎないと割切るのも判断を誤ることになります。その製品開発プロセス全般への幅広い寄与を正しく認識すべきであります。
このPLM PKGは例外的なケースを除いて殆ど欧米で開発され、その知識蓄積の所有権も日本には殆ど無いのが現状です。PKGの利用者にはブラックボックス化されており、使用権での利用に留まっています。この欧米製が独占しつつある状況は、機械系PLM分野に限らず、電子系でも、また会計、生産管理、人事などのビジネス系のPKGでも、更にはミドルウェアやベーシックソフトでも、つまりソフトウェア製品全般にわたって同じ現象が起きつつあります。
いま日本製ソフト製品がほとんど育っていない状況でも不都合があまり見られない、と軽視することは危険です。マクロには産業構造は時代と共に必ず変わっていくものであります。欧米が知的資産の集約であるソフト製品に明日の重要産業をみており、「より高度化へと発展し続ける知的資産」という命綱を決して手放してはならない、とも云われています。欧米と比べてソフト製品を開発できていない、所有していない状態が本当によいのか、少し大きく日本の産業構造の近未来が成立するのかという論点を舞台に乗せることがあっても良いのかもしれない。勿論この状況は既に指摘がなされて久しいが、産業界、行政組織、研究機関、メデイアで広くこの問題意識が共感、共有されて初めて新たな価値観が形成されていくものと思われ、新年にあたり、このDIPRO NEWSでも訴えさせていただきました。
最後になりましたが、本年も弊社の全力をあげて皆様のご支援をさせていただく所存でございますので何卒よろしくお願い申し上げます。
(常務取締役 金谷 善治)
PICK UP












