DIPROニュース
自動車産業の「3D-CAD活用」は、他製造業にとってのベストプラクティスか?
- デジタルコンテンツサービス部 -
自動車産業のデジタル化による業務改革
日産自動車殿が実現した「V-3Pプロセス」など、自動車業界では、商品開発力強化を支える「製品開発業務の効率化、期間短縮」に力を入れ、デジタル化により、着実に実務定着を進めてきました。日産自動車殿の例では、これまで20ヶ月の新車開発期間を半減しました。自動車の「製品開発業務の効率化、期間短縮」に貢献した方策が、徹底した「エンジニアリングのデジタル化」です。
「エンジニアリングのデジタル化」は、過去30年の「3D-CAD使いこなし」の蓄積の結果とも言えます。1980年代の「CAD/CAM一元化」により、「モデルレスによるプレス型製作プロセス」を確立しました。1990年代後半の「データ衝プロセス」では、「アッセンブリ・レイアウトの確認(Digital Mock-Up)」、「生産技術サイマル(コンカレント)確認」、「図面レス手配」を実現しました。
3Dデータ基準による設計・生技の「データ衝」を更に徹底し、「ナレッジCAD」などの新たな方策を加えて実現したプロセス改革が「超短縮プロセス」=「日産自動車殿のV3P」と言えます。
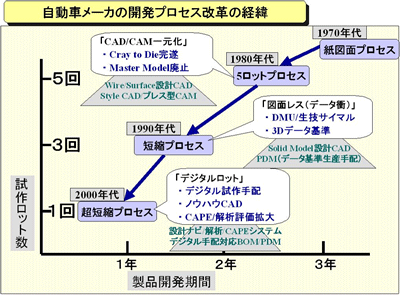
自動車産業と他製造業の違い
「図面レス」に代表される「徹底した3Dデータ基準」の業務をすべての製造業がお手本とできるのか?膨大な設計業務の「標準化」、「ナレッジ・テンプレート化」は、自動車以外の製品設計でも使うのが得か?
自動車産業の「一製品」、「大量生産」、「定期的モデルチェンジ」は、他製造業に比べての特異性と言える。他製造業の代表として、三菱重工殿を自動車会社と比較してみると、単独社員数では日産自動車殿などと同様の規模でですが、三菱重工殿11事業部で主要製品を700も持っておられます。多くの自動車メーカーは、少数の他事業事業部門を持つもののほとんど、「1事業部1製品」と言って良いと思います。単純に、この数字から想像すると、三菱重工殿には、飛行機、造船など、自動車以上に複雑な製品も多くあるものの、1製品当たりの開発投資規模は自動車に比し、2ケタか3ケタの差があることになるでしょう。
自動車と他製造業のもうひとつの大きな違いは、サプライヤ殿との関係です。製品コストに占める外製品比率に大きな差が無いとしても、必ず「製品別の専用部品」を起こす自動車と、「汎用部品ベースに設計する」他製造業では、「部品サプライヤの設計責任の大きさ」に、明らかな違いがあります。
「製品開発投資の規模」、「部品サプライヤの責任範囲」に大きな違いがあることを前提にした時、他製造業では、自動車産業の「デジタル化による業務改革」をお手本にして良いのか?と疑問になります。
効果の上がる方策の良いとこ取りを
つまり他製造業では、「自動車と同じ3D化は必ずしも懸命な方策ではない」と言えます。では、独自の方策を作り出すのか?答えは、「何といっても先行して実績を上げている自動車の3D化方策」の「良いとこ取り」をすること、と思います。例えば、3D基準で業務を遂行するために、「データの保守、設計変更追随」は徹底的にやるが、「図面レス手配はしない」などの取捨選択です。システム面でも、自動車業界で不可欠な「部品表システム」と緊密な連携の取れた「PDM(CADデータ管理)システム」も、当面は「CADデータの流通・管理」を人系で賄う、などの「適用方策の絞込み」を行うことが重要です。
3D化による「業務の効率化、質の向上」が目的であって、システム化が目的ではありません。個々の事業の規模や特質に最適な「方策の選択」が、良いとこ取りです。
今年も皆様のプロセス改革のお手伝いをさせていただければ幸いです
弊社の「3D化コンサルティング」チームも、自動車での経験に加えて、非自動車製造業のお客様とお仕事をさせて頂く機会が増え、種々の経験・ノウハウを蓄積しつつあります。この経験を、今後の皆様の「3D業務改善」に役立てるチャンスをいただければ、幸いに存じます。
今年も、これまで以上に皆様のお役に立てるよう努力する所存です。皆様のお引き立てをよろしくお願いします。
(取締役 デジタルコンテンツサービス部 部長 加藤 廣)
PICK UP












