DIPROニュース
集約化・企業化で若者が夢を持てる新たな産業に
~歯科と農業を例にして~
はじめに
世の中すべてが複雑になりすぎてしまった。あることに対して自分はこう思うと主張しても、視点を変えると自分でいくらでも反論できてしまう。あちらを立てればこちらが立たず、利害や仕組みがあまりにも複雑に絡みあって、どの糸を手繰ってもどこかでもつれてしまう。人間の欲の結果か、矛盾がここまで溜め込まれると選挙のマニフェストも幸せの分配や甘い蜜の約束をするのではなく、負の面のみについて約束するきまりにし、それをどう負担しあうか、どう分かち合うかを競いあった方が、本当のところ真実が宿っているような気がする。そういった端から、結局うそでも負の面を小さく約束した方が勝つであろうと、やっぱり自ら反論できてしまう。以下も正論として主張しようとしているのではなく、そういう見方もあるかくらいに捉えていただければ幸いです。
歯科の世界の“不思議”について
![図1. 弊社加工機による美しい歯(セラミック)の自動創成[注:エンジェルクラウンはメディア社の登録商標です]](/files/news/2012/03/02-01.jpg)
[注:エンジェルクラウンはメディア社の登録商標です]
永いこと携わってきた自動車用CAD/CAMの世界からすっかり離れ、2年半ほど前から歯冠(クラウンやブリッジなど)の自動創成システムの開発から販売の仕事に係わるようになりました(図1)。
このシステムは15年以上前から弊社デンタル事業室長の藤原が中心となって、自動車向けのCAD/CAM/CAE技術を歯科医療の世界に活用できないかと取り組んできたものです。以前は日本でも数社が歯科用CAD/CAMシステムの開発を行っていましたが、今ではほとんどが撤退し国産で残っているのはDIPROしかないくらい欧米が強い分野です。
これまでの長い取り組みにより高い技術や経験、あるいはノウハウが蓄積されてきました。一方で、医療分野は技術的にもマーケットとしても想像以上にハードルが高く、グローバルな競争で生き残るには歯科医療に関する深い知識とシステム化への独自の発想やチャレンジが要求されます。
直接係わりを持つようになってまだ日は浅いのですが、自分にとってはとても新鮮で、素人ゆえの好奇心を満たしてくれます。特に虫歯などでなくした歯をCAD/CAMで修復するため、患者さんの“神から授かった”天然歯はどんな歯であったかを考え、限りなくそれに近づけるために発生学、解剖学、咀嚼機能などを考慮し理想の形を追求する取り組みに興味は尽きません。しかしここではそれとは別に、この業界(マーケット)を垣間見て“不思議”に感じたことを中心に記してみようと思いました。
歯科の“不思議”を深掘りしてみると、一見唐突ですが農業も似たような状況にあることに気づきました。そこでこの小文では歯科業界を見て感じたことに併せ、後段で(複雑かつ矛盾を溜め込みすぎた)農業 について少し触れてみようと思います。そして最後に歯科医療と農業について明るい未来を探す試みをしてみようと思います。
歯科医の収入減は本当に医師の過剰が原因か
このところ歯科大学(歯学部を含みます)の人気が低落し受験者数が定員に満たない大学が毎年増加しています。同じように歯科技工学校の人気もなくなり、毎年2、3校ずつ廃校になっていると聞きます。歯科大学については歯科医師が増えすぎて、学費や開業に多額の資金が要るにも拘わらず収入が大きく減っていることが不人気の原因とされています。技工については低収入に加え、若者が嫌う3K職場とみなされているからとのことです。さらにこの業界は薬事法や医療保険制度、技工士の資格制度などさまざまな保護と束縛が錯綜し、知れば知るほど適切な競争がしづらいであろうと驚き、そして多くの不合理を感じます。さりとて歯科医師の場合、もっぱらその過剰を低収入化の原因にしたり、技工業界が業務の改善や近代化の努力なしに若者離れを嘆き諦めたりしているとしたらとても残念なことです。
ここで、少しデータで歯科業界を見てみましょう。昨年末に厚労省が発表したデータ(2010年末現在、1,000人以下四捨五入)では、歯科医師数がはじめて10万人を超えたとのことです。歯科医療従事者は9万8千人で、うち病院従事者は1万2千人(12%)、診療所従事者は8万6千人(85%)で診療所の開設者が6万人、勤務者が2万6千人となっています。平均年齢は全体で49歳、病院は37歳で診療所だけでは51歳とかなり高齢になっています。一方、技工士を見ると、技工士数は3万5千人、技工所は1万9千事業所となっています。もちろん高齢化も進んでいます。これらの数字からいろいろなことが見えてきます。なかでも特徴的なことは歯科には病院が少ないことで、全体の85%が個人医院で1診療所当りの医師数は僅か1.4人となります。同様に技工所も零細で、1技工所あたりの技工士は1.8人となります。いずれもほとんどが個人事業といって差し支えない数字です。
また、先に触れたように歯科医師の過剰が低収入化の原因とされていますが、本当に多すぎるのか欧米の先進国と比べてみました。
2006年の世界保健機関(WHC)のデータによれば、歯科医師一人あたりの人口は、日本が1,413人、アメリカ637人、ドイツ1,279人、イギリス1,012人、フランス1,473人とあります。この数字では欧米先進国に比べ同じかむしろ少ないくらいで、歯科医師の過剰を低収入化の原因と騒ぐほどではないように思われます。他には医療保険制度や都市部への歯科医の偏在なども考えられそうです。しかし私はこの世界に係わり、低収入化の何よりも大きな原因は、歯科のほとんどが経営者を兼ねた個人医院という事業形態にある、との思いを強くしました。個人事業は経営効率が悪いだけでなく、組織だった医療技術の研究・開発がやりにくい、業界として纏まりがないなど、さまざまな問題の要因となります。この業界を垣間見て“不思議”あるいは“疑問”に感じたのは、「なぜ歯科医療はそれでも個人事業といった構造のまま留まっているのか?」という点でした。
かつて歯医者さんになろうとして歯科大学を希望した人の多くは、医療を通して人の役に立ちたいということと、収入がよいということではなかったかと思います。そのために個人で開業をすることを当然の目標としていました。しかし歯科大学は経営や産業としてのあり方について学問的・体系的に教える場ではないため、経営者あるいは産業人としては素人といわざるを得ません。これは歯科のみならず日本の医療全般に通じるように思います。このことが非効率な個人事業のまま温存されてきた大きな理由です。そしてもう一つは適切な競争原理が働きにくいことにありそうです。
競争の厳しい業種では個人事業では立ちいかず、企業化・大規模化が進みます。魚屋さん、八百屋さん、雑貨屋さんは、はるか昔に効率やサービス力で勝るスーパーなどの大型店やコンビニの進出で姿を消しました。しかし医療の世界は、患者さんに対し“情報の非対称性”という医師側に有利に働く特殊性や、さまざまな許認可制度に守られ、それに安住してきました。その結果が今の状況をもたらしたと思います。もし積極的に企業化(病院化)を進めれば多くの問題を解決できるのではないか、その意味でまさに宝の山に見えるのです。同じことが、さらに厳しい状況にある歯科技工の世界にも当てはまると思います。
個人診療所を病院化するとどうなるか
ここで個人診療所を病院化すると一体何が違うのかを比較するため、都市に集中する個人診療の歯科医20人が集まり一つの病院にしたらどうなるか考えて見ます。
20箇所の診療所を一つに纏めれば必要な土地や建屋の規模は数分の一に、レントゲンは20台が1、2台に、1台数百万円もする治療用ユニット(椅子)も稼働率を考えれば総数を半分以下にしても余裕がありそうです。このように病院の設備投資は20診療所の総投資額に比べ数分の一で済みそうです。またITの活用や、受付や保険事務など管理の集約化で間接員を大幅に減らせます。その結果必要な経費やコストが格段に下がるだけでなく、サービスレベルもかなり向上するに違いありません。余裕のできた資金は、歯科医師は勿論、歯科衛生士やスタッフの待遇の大幅な改善に回せるだけでなく、新しい医療技術の研究や開発に投入できます。つまり医院経営を兼ねた場合より医療に専念した方が遥かに収入を増やせます。それだけではありません。組織化・企業化によるさまざまなメリットを享受できます。個人医では技術や知識を先輩や仲間から学べませんし、学会・講演会への参加も難しく、極端に言えば卒業後は個人の経験以外に技術習得が難しくなります。もし世代や経験を異にした20人の歯科医師が一緒に働けば、診断のレビュー会やディスカッションを通じて相互研鑽や治療の改善、誤診の防止などが可能になります。特にレビュー会がノウハウの蓄積と個人の成長を加速するであろうことは技術系企業を見れば容易に想像できます。そして外部研修に参加する余裕も生まれるだけでなく、交代勤務で24時間サービスも可能になります。「個人医院→病院」による集約化は“マネジメント”の面でも医師として人間として多くの成長の場を与えます。大きな組織ではプロモーションやローテーションの機会が増え、さまざまなコミュニケーションを通して一層の働き甲斐が得られると思います。このようにして競争力が高まれば日本への医療ツーリズムや医療技術のグローバル展開など、さらに仕事の魅力や事業の可能性が広がります。
歯科を産業の立場から見たときどうでしょうか。自動車メーカーには22万人が働いていてもたった11社しかないため(社長が11人)、業界の意思統一が容易です。一方歯科医の世界では、勤務者が2万6千人で診療所の開設者は6万人です。6万人の利害の異なる社長の集まりでは産業全体としての立場で意思を纏め行政や制度に反映するのは難しくなります。低収入化の主な原因を医師の過剰に求めず、組織化・企業化に向け業界挙げて取り組めば更なる収益力と医療の質の向上につながります。
似たような問題を抱える技工士の世界も全く同じことがいえます。零細な事業形態では歯科と同じような問題を生むだけでなく、限られた資金力では機械化や高度化を進めることができません。結果として手作業や鋳造作業を主体とした昔ながらの技工から抜けられません。個人技工所を集約して規模を大きくすれば先進的な設備を導入しやすくなります。優れたCAD/CAMの導入、IT化などで3Kのイメージが一掃され、職場の雰囲気も明るく変わります。そして若い人にとって魅力的な、従来の技工所とは全く異なる“新しい職種”に転換できるとともに、新しいビジネスの創造が可能になると思います。
ところで農業はどうなっているのでしょう
これまで述べてきた“不思議”は、同じような構造と悩みを持つ農業にも当てはまりそうです。いま農業は国として大きな問題となっています。人の生存にとって必須の営みでありながらなぜ収入が少なく効率の悪い個人事業のまま残っているのか、とても不思議です。とはいえ農業問題は根が深くTPP参加の議論を見ても立場によって賛否が全く異なります。特に農地は律令時代の口分田や秀吉による太閤検地、明治維新の地租改正、そして戦後の農地改革と日本の形を作る歴史的な役割を担ってきました。農地改革は地主・小作制度を廃止し、自作農が280万戸から540万戸とほぼ倍増しました。しかし60年を経た今日、グローバルな競争力を集約化・企業化で高めようとしても、多くの所有者に細分化されていることが大きな障害となっています。その上きれいな水や空気といった自然や美しい景観の保護、その土地の文化や歴史・風土の継承など、重要な役割も担っているため経済合理性だけで動かせるほど単純ではありません。さりとて避けて通れるはずもなく、どんな困難があるにしろ集約化・企業化を早急に進めなければいずれ衰亡するしかないと思われます。
農業は外から見て、「いのちに直結した、本来やりがいがある仕事」「ほとんど個人事業であり、経営や産業全体の在り方には関心が薄い」「保護や規制に守られている」といった点で、先に考えた歯科と似たものを感じます。
ここで歯科の場合と同様に農業についてのデータ(2010年厚労省統計)を見てみます。
農業の国内総生産は4兆6,600億円です。就業人口は260万人で、平均年齢は66歳です。農業経営体は168万体で、うち家族経営が165万戸とほとんどで、専業農家は僅か44万戸となっています。1経営体当たりの従事者はたった1.5人となってしまいます。
これらのデータからいろいろなことが見えてきます。最も特徴的なことは事業形態と年齢です。売り上げは自動車の1/9以下にも拘わらず経営体(企業数)が168万(=社長の数)と膨大です。これはまさに個別の“家業”であり纏まりある“産業”とは到底言えません。
もう一つの、年齢については平均66歳と他国と比較しても圧倒的に高齢です(図2)。66歳は通常のサラリーマンならとっくに定年を過ぎています。本来悠々自適(とはいかない?)で過ごしていただく世代が支えていることになります。私たちは農業をここまで至らしめた(放置した)ことに対し申し訳ないと思わねばなりません。
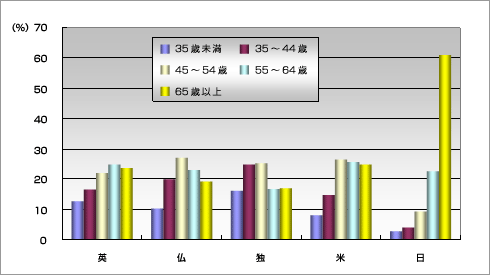
出所:渡邊頼純 著 「TPP参加という決断」より(農林水産省の資料より作成)
どんな産業も同じですが、農業も若い人が働きたくなる産業にしない限りいずれは消滅するでしょう。働き盛りを過ぎた高齢者が家業や副業としてなんとか維持しているわけですからグローバルな競争力がある方が不思議です。もはや戦後の農地改革に匹敵する大改革として、換地を含めた集約化・企業化を進め“全く新しい別の産業”として生まれ変わることでしか生き残れないと思われます。現在1戸当たりの農地面積は米国の100分の1です。せめて米国の1/5位まで集約できたらと思います。もちろん財産権(昔風にいえば全員が地主さん)と分離して集約できるか、山や起伏が多いだけでなく住居地や工場も混ざって細分化された農地を物理的に集結できるのかなど、困難は山ほどあります。それでももしさまざまな困難を乗り越え実現できれば歯科で試算したように所得の大幅な向上が期待できます。そして農家のほとんどを占める高齢の方々には、若者の指導者にまわっていただき(その方々にはきちんとした形で補償します)、平均年齢30歳代の若い産業に変えていきます。若返りと機械化で生産性が上がり、仮に1/10に省人化されてしまっても高齢者260万人に代わって新たに2~30万人の勤労世代の雇用を生むことになります。集約化・企業化は待遇の大幅な改善と、より高度な農業技術や新たなビジネスモデルの研究・開発を行うことを可能にします。そしていつか食料自給はもちろん日本有数の輸出産業に育つであろうと夢と希望が広がります。
明るい未来の日本を目指して
「日本人は行きつくところまで行かなければ動けない」というのが私の一つの日本人観でした。早めにあるいは予見的に動くより、被る損失は遥かに大きいのですが、その分貯められた反発力やエネルギーが大きくなり、動いたあとの変革は大きいものがあります。幕末には黒船という外圧で已やむなく開国し明治維新が起こりました。第二次世界大戦では、敗北が明らかになっても決断できず、徹底的に打ちのめされて初めて終戦に到りました。つまり外圧でしか変わらない、動けなかったということです。「行きつくところまで行きついた」状況をもたらした三つ目の外圧は、グローバル化と3.11の大震災であると位置づけてよいと思います。大震災は同じ外圧でも人間ではなく自然のもたらしたものです。グローバル化と大震災という二つ重なった外圧を、日本が変わる最大にして最後の機会と捉えたいのです。最初に“不思議”に感じた歯科業界も、組織化・病院化を業界全体で進めてほしいと思います。農業は土地の集約化・企業化を実行する最後のチャンスと考えます。私たちは国を挙げて農業を新卒の就職人気No.1クラスの業種に変えることを目標にするのです。企業化された農業はグローバルな競争力をつけることに徹し、夢の持てる全く新しい“別の産業”に創り変えるのです。それができればTPP加入問題も自然に解決するでしょう。
「新しい産業の創出を」といったスローガンは過去20年以上叫ばれてきましたが結局生まれませんでした。ビルゲイツやスティーブジョブスが日本から出ることを待つのをやめ、これまでお話ししたような、昔からある効率の悪い産業を全く別の強い産業に創り変えること、換言すれば若者たちが夢の持てる産業に変えることが日本人に適した“創造”の在り方と考えます。
以前のDIPROニュース2010年8月号、2010年9月号、2010年10月号で、「破綻寸前の地球を守り持続可能な新たな地球システム(もったいないシステム)創造のため日本がリーダーとなり、その実践を通し世界のお手本になる」ことで新しい産業を創出しようと提案しました。それに加えて、歯科や農業を例に述べた“不思議”や“疑問”を、似た環境にある他の産業も含めて解決していくことでさらに多くの“新しい産業と雇用”を創造できるのではないでしょうか。
東日本大震災は、神様が「日本は行きつくところまで行きついたのです、今が変わる最後のチャンスですよ」と告げているように思えてなりません。
あとがき
文頭に、「世の中すべてが複雑になりすぎてしまった。あることに対して自分はこう思うと主張しても、視点を変えると自分でいくらでも反論できてしまう」と書きましたが、書いてみてやっぱり自ら反論できそうです。ここで述べた歯科や農業について、当事者の皆様の異論・反論はきっと多いと思います(ご意見をお聞かせくだされば幸いです)。
「何をしても正解はない、でも佇んでいて解決するわけではない、世の中本当に複雑になりすぎてしまった」
(最高技術顧問 間瀬)
PICK UP












