DIPROニュース
5つの向かい風を超えて (その3)
目指す方向とは・・・
これまで5つの項目について、嘗ての日本の強み、そして現在の弱みとその原因について考えてきました。無謀にもここまで書いてきて、いざ目指す方向は?となった途端にその難しさに途方に暮れる感がします。とはいえ敵を知り己を知れば百戦して危うからずといわれるように、私たちの強みと弱みをきちんと認識し、その真の原因が分かれば自ずと適切な行動がとれるものです。(私事ですが、若いころコンピュータのOSについて知り、その考えに圧倒されるとともに、自分にとってそういう発想がなかったことを弱みとして強く認識しました。このことがその後、さまざまな仕事にシステム思考を取り入れるうえでとても役に立ちました。)
もう一つ重要なのは、トップになりお手本がなくなった後の姿勢です。もうお手本はないはずですが、それでもお手本を探そうとするため、むしろ改悪になってしまいます。こういった姿勢が20年に亘る停滞の大きな原因の一つであったと思います。自らがお手本になる姿勢と、自らの強みを発揮しやすい環境に変えるといった主体性を持つことが重要です。
さて初回の稿で述べた、もう少し具体的な共通の目標は、「破たんしそうな地球を守り、持続可能な新たな地球システムを創るためのリーダーとして世界のお手本になること、そして様々な産業で創り出されたお手本としての地球システムを世界に輸出・提供することで、'新しい豊かさ'を創り出し世界に貢献する」といったことでした。
この目標を実現するために私たちは、全人口の8割を超える発展途上国に、真に循環型といえる社会システム、経済システム、そして生産システムを提供しなければなりません。もしこれができれば単に日本の産業を救うだけでなく、世界を破たんから守ることに繋がります。
フランスの文化人類学者で昨年亡くなったレヴィ=ストロースは、構造主義の先駆者として著名ですが、人類の豊かさや幸福について多くの示唆を与えています。
その著書「野生の思考」によれば社会には2種類があるとのことです。それは「熱い」社会と「冷たい」社会です。西欧社会の原型となる「熱い」社会は熱力学的機械にたとえられ、大量の仕事(秩序を創出すること)をこなせるが、同時に大量のエントロピー(無秩序)も排出します。エネルギーは熱い部分と冷たい部分の差から得られるように、社会階層が存在して機能します。一方未開地に見られる「冷たい」社会は、時計のようにわずかなエネルギーで長い間動き続けます。「摩擦」を最小化し、平衡を維持します。したがって熱力学的な「熱い」社会より平等で、環境にやさしいのです。レヴィ=ストロースは未開社会といわれる人々がやさしく、幸せそうな様子を見て、成長とは何か、発展とは何かについて深い洞察を行います。そして経済的、文明的といわれる発展のみが人間の求めることではないと静かにまた強く語っています。
しかしここでレヴィ=ストロースのいう冷たい社会が持つ豊かさを実現するために、経済的発展を止めよと言いたいわけでは決してありません。その分析を活かし、経済的発展を伴いながら冷たい社会の優れた部分を享受するシステム、すなわち文化の秩序を増大しつつ社会のエントロピーを低くする、'新しい豊かさ'のモデルを、ビジネスとして創り出し提供することが可能ではないかと思うのです。そしてそれができるのは、日本の製造業であり日本の技術ではないかと心から思います。これは極めて困難なチャレンジになりますが、これこそがお手本をなくして以来、停滞する日本が目指すものであると信じています。そしてあらゆる産業とすべての産業人がこの目標にベクトルをあわせ、卓越した成果を実現し続ければ、世界中から、信頼はもちろん尊敬をも勝ち取ることが可能です。近年、中国が大国化しつつあること、途上国の追い上げが激しいことを考えると、日本にとって、この選択肢こそが最善の道であると思います。
このところ円高、株安、そして雇用吸収力の急減が大きな社会問題になっています。あらゆる製造業のあらゆるレベルでこの目標をシステム思考に基づいてきちんとブレークダウンし、真に持続可能な新たな豊かさを実現する開発・生産システムを作りだせれば、それ自身がグローバルな場でのビジネスの対象となります。そして掛け声倒れの新しい産業の創出以上に大きな雇用吸収力を生み出すとともに、若い人たちが情熱を持ってチャレンジできる対象になるのではないでしょうか。
5つの風をどう乗り越え、どう変えるか
以下に、現在のモデルをどう乗り越え、どう変えることを前提に目標を定めるか考えてみたいと思います(図7)。
(1) オープンから多様化に向かう
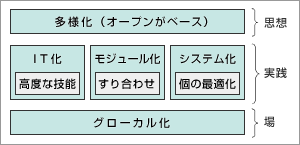
これまでクローズドからオープンへ、ローカルからグローバルへの道を辿ってきましたが、オープン化とグローバル化の影響は人間世界にとどまりません。10月に名古屋で生物の多様性をどう守っていくかという世界会議が開かれます。人間による生態系の破壊でその一部でも欠ければ、全体のバランスが崩れて連鎖的に多くの生きものに悪影響を及ぼします。そのことの重大さを世界で共有し、開発や気候変動などで急速に減っている種や生態系を守るための対策について話し合うことになっています。この動きから分かるように、地球や生物にとって、「豊かさ」の重要な要素の一つは「多様性」にあります。人間の世界も同様で、クローズドからオープンへの変化は、文明の画一化と多様な文化の消滅をもたらすことを生態系が教えています。これからはオープンを維持しつつ多様性をどう守るかを追求する時代に入っていくと予測されます。その課題にどう応え解決するか、日本が、あるいは日本の製造業が果たすべき役割はとても大きいと思います。
(2) グローカル化を目指して
1990年以降の、発展途上国も巻き込んだ新たなグローバル化時代に大きく取り残された日本ですが、一方で今の延長線上でのグローバル化だけでは決してうまくいかないことも徐々に明らかになってきました。今後は、多少言い古された感もありますが、ローカルでもグローバルでもない、'Think Global Act Local'、すなわちグローバルな枠組みで発想し、場としてはそれぞれの地域の考えを大切にする、いわゆる「グローカル化」の優劣が市場競走の決め手の一つになるように思います。もちろん、新しい追い風にするために、「オープンを維持しつつ多様性を守る」という考えとセットで目指さねばなりません。
(3) IT化、モジュール化、システム化の徹底とコンテンツに日本的強みを
次に、実践として掲げたIT化、モジュール化、システム化についてどう取り組むべきか考えてみたいと思います。この三者は前回、システム化を中核にして密接な関係にあると述べました。これまで分析した欧米の強みを、まずは素直にそして最大限の努力を払って取り入れ、競争優位を獲得します。そしてその上で、それぞれの項目ごとに、1990年以前の日本の強みを内挿することで更に差別化を図ります。すなわち(図7)にあるように、IT化にあたっては強みであった高い技能の形式知化(例えばナレッジの体系化とニューロネットの活用など)にチャレンジし、ITシステムに埋め込みます。モジュール化については、そのインターフェースを確保したうえで、同様に得意技であった設計段階でのすり合わせを可能な限り行い、モジュール内に強みとして隠ぺいします。そして最も重要なシステム化については、システム思考を徹底したうえで、構成する要素個々の最適化を追求します。そしてその場合でも要素自体より要素の相互関係のほうが常に重要であるというシステム化の本質を見失ってはなりません。
日本の果たすべき役割
人間が地球に対し修復ができない傷跡を残すいかなる権利も与えられていない、ということを日本の文明が前提にしてきたことは、自然との共生のこころを持つ「八百万(やおよろず)の神」の思想や、かけがえのない地球資源に対する'もったいない'という言葉からも推し量れます。もったいないという言葉自身は、アフリカのワンガリ・マータイさんがその価値を地球に広げるべきと語ったことで有名になりましたが、日本の提案する地球システムとはある意味、「もったいないシステム」という言葉で言い表してもよいかもしれません。そして日本のもの作りが再び評価されるようになるのは、この「もったいないシステム」が世界中で広く受け入れられた時であろうと思います。
『世界は人間なしにはじまったし、人間なしに終わるだろう』という、レヴィ=ストロースの言葉を改めて考え、生物でもある人類が多様性や多様な文化を残しつつ、豊かな文明を享受する世界の構築に向け、日本全体が、とりわけ日本の製造業が先頭をきって走ることができれば、失われた20年から再び蘇ることができるのではないでしょうか。
(相談役 間瀬 俊明)
PICK UP












