DIPROニュース
技術で世界の輪の中へ ~ICAD/SX 国際会議発表報告~

ICAD/SXのコア技術はどこまで世界に通用するのか?アメリカのフロリダ州オーランドで行われた国際会議 SIAM Conference on Geometric and Physical Modeling (GD/SPM11) に10月24日~27日の日程で参加し、ポスターセッションでの発表を行いました。
GD/SPM11は、SIAM(国際応用数理学会)とACM(アメリカ計算機学会)が2009年から合同で行っている幾何モデリング分野の著名な会議で、今回が2回目となります。また、この会議では曲面分野において大きく貢献した研究者に、ベジェ曲線考案者の名を冠したPierre Bezier Awardが贈られます。数学者やCAD開発者を中心に、大学や企業から150名もの研究者が集まりました。
ディズニーの街、オーランド
オーランドはテーマパークや、ゴルフ場などが多数存在する全米屈指の観光都市として有名です。特にウォルト・ディズニーワールドには世界中から観光客が集まります。会場はディズニーワールドから10km程度離れていたのですが、どの商店も多くのディズニーグッズで埋め尽くされていました。避寒地として多くの人が訪れることもあり、10月でも晴れた日中は日差しが強く暑いぐらいでしたが、一方で朝晩は想像していた以上に冷え込みました。
巨大ポスターでどう伝えるのか
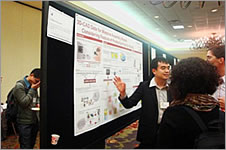
今回の発表のタイトルは “3D-CAD Data for Massive Assembly Models Considering Feature of Production Facility Models”。ICAD/SXがターゲットとする生産設備や工作機械の3Dモデルには、実は自由曲面がほとんど含まれていません。このことに着目することで、モデルのデータサイズを大幅に削減し、大規模なモデルを高速に扱えるよう工夫したことを発表しました。これはICAD/SXにおける超大規模モデルの高速処理を支えるコア技術です。
しかし、ポスター発表の準備は、英語の苦手な私にとって容易なものではありませんでした。まず、横1.7m×縦1m、A4用紙で27枚分にもなるポスターの大きさに圧倒されました。また、先日上海で行われた国際会議 ACDDE2011(DIPROニュース 2011年10月号)で発表したときの経験から、技術での勝負に持ち込むには、まず自分たちの考えや技術をいかに伝えるかが重要になります。
今回のポスターでは、まず「何の発表なのか」を短い時間で伝えることに重点をおき、ポスターの上の方を見れば流れがわかるようにしました。また、日本語であっても言葉や文章だけで伝えるのは難しさを感じることから、ポイントとなる図表をポスターの中心におきました。特に、データ量削減をアピールする図は、処理の手順を従来の手法と比較しながら説明することで、直感的に理解できるよう工夫を凝らしました。
“Great!”
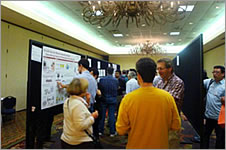
ポスター発表当日。この会議に参加する多くの方は、自由曲線や曲面を扱う研究者です。自由曲面を扱わない我々の発表に本当に興味を持ってもらえるのかと、不安が募ります。そしてその不安が的中。ポスター発表の序盤は、ポスターを見に来てくれる人に説明するも今ひとつ深い話にならず、質問も無く立ち去られる状況。隣のポスターが盛況な中どうすれば良いかと悩みました。
少し落ち着いて考えてみると、早く興味を持ってもらおうとするあまり、説明を飛ばし過ぎてかえって伝わっていないのではないかと気付きました。そこで、重要な箇所に少し丁寧な説明を加えてみたところ、話が伝わったのか「Great!」と全身を使って反応されたり、「開発にどれぐらい時間がかかったのか」と質問を受けるなど、研究者との話が盛り上がりました。伝えたい内容を明確にして、わかりやすい説明を心がければ、十分に興味を持ってもらえることを肌で感じた瞬間でした。
研究者の輪の中へ

会議では、どのセッションでも時間が足りなくなるほど活発な質疑応答が行われていました。私自身も、本年Pierre Bezier賞を受賞された米国パデュー大学のChristoph M. Hoffmannさんの発表をはじめ、有意義な発表を多数聴くことができました。
本会議に参加して強く印象に残ったのが、参加者にフレンドリーな方が多かったことです。今回は単独での出張であったため、ともすれば誰とも話さないまま孤独な時間を過ごしてしまうところでしたが、Coffee Breakの場で積極的に参加者に声をかけ、技術討議をしたことは大変刺激となりました。また、3日目には私と同じくポスター発表していたベトナム人の研究者から食事に誘われ、まさに研究者の輪の中に入っているのを実感。単に会議に参加するだけでなく、自分自身が発表することで参加者に刺激を与え、興味を持ってもらうことでさらに輪が広がることを実践で学ぶことができました。
今回、この会議に参加して、生産設備や機械装置にターゲットを絞り大規模高速処理を実現するiCADの考え方を多くの方に理解いただけたこと、そして研究者の輪の中に入っていけたことは私にとっても、iCAD社にとっても大きな収穫になったと考えております。この体験を活かして、今後もICAD/SXを世界に通用する製品にすべくさらなる努力をしていきます。そして、またその成果を国際学会の場で発表し、さらにiCADの技術をアピールしていきます。
(iCAD株式会社 松波)
PICK UP












