DIPROニュース
「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2011」 開催

11月30日(水)、パシフィコ横浜で「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2011」が開催されました。開催にご協力いただきました皆様、ご来場いただきました皆様に厚く感謝申し上げます。
本年は100年に一度のリーマンショックからようやく立ち直ろうとしていた矢先に、1000年に一度の大震災と津波に襲われ、それに続く原発事故による停電、節電の夏がようやく終わったところで、欧州の経済不安による超円高、一過性とはいえタイの洪水による生産のストップと二重三重の試練の年でした。そのような中で開催した今回のセミナーは、製品や市場の新しい方向と挑戦を軸にしたものとさせていただきました。
通算で19回目となった今回、基調講演として元三菱航空機株式会社社長で、現在三菱重工業株式会社の特別顧問の戸田 信雄様に『MRJを世界の空へ』と題して、MRJの開発についてのお話をいただきました。また自動車メーカー様からのご講演として、東風汽車有限公司の中村 公泰様による『中国における自動車ビジネスの展開と課題』と題して、最新の中国事情をお話しいただきました。

山田代表取締役社長 開会ご挨拶
また、毎年ご好評をいただいているパネルディスカッションではトヨタ自動車株式会社 大平 宏様、日産自動車株式会社 山本 泰司様、株式会社本田技術研究所 中嶋 守様、マツダ株式会社 岡村 一徳様、三菱自動車工業株式会社 太田 晃様、スズキ株式会社 倉田 効市朗様に『将来に向けたエンジニアリングITの方向性と課題』というテーマで熱く語っていただきました。
本年は午後からの開催となり、開催時間も短いものとなりましたが、ご来場いただいたお客様からは参加しやすくなったとの声も聞かれ、ご満足いただけるものとなったと考えております。
基調講演:
『MRJを世界の空へ』
三菱重工業株式会社 特別顧問 戸田 信雄 様

MRJの話題に先立ち、まず航空機産業の歴史と現状からお話しいただきました。1903年のライト兄弟の初飛行から、日本での初飛行の歴史、戦時中に劇的な発展を遂げた日本の航空機産業の歴史を紐解かれたあと、日本の航空機産業の概況についてご説明くださいました。産業規模にして年間約1.2兆円、内防衛関連が約0.5兆円、民需が約0.7兆円となっており、防衛関連の減少傾向に対し、民需が著しく伸びています。産業構造を見ると欧米では専業で大規模であるのに対し、日本では重工メーカーの一部門であり、それぞれの規模も小さいことから、競争力強化に向け、これらの統合も一つの考え方であるという見方もお話しいただきました。
続いて、戦後の航空機開発の歴史に触れられ、航空機開発が禁じられた空白の7年間の後、米国の戦闘機ライセンス生産から始まり、国産戦闘機の開発に至った防衛関連開発での進展、民間機としては、YS11の開発、その後のボーイングとの共同開発を経て、最新の787では最も重要な部位である主翼を初めて海外の企業として開発・生産するまでに至っているとの経緯、そして、防衛関連開発で得たインテグレーション技術と複合材料技術などの要素技術、民間機国際共同開発で培った高効率生産技術などが組み合わされて、MRJの開発に結実しているというお話をいただきました。
加えて、航空機で開発された技術は、セミモノコックボディの自動車への適用、複合材のゴルフクラブへの応用、その他GPSや燃料電池など、多くの製品に展開され、極めて技術波及効果の大きい産業であることを説明いただきました。
本題の純国産初のジェット旅客機MRJの開発は、経済産業省主導の『環境適応型高性能小型航空機』開発事業に端を発し、平成20年に三菱重工業株式会社を中心に三菱商事株式会社、トヨタ自動車株式会社などからの出資により、三菱航空機株式会社が発足、事業化に向けた動きが本格化したとのことです。
MRJは70人乗りと90人乗りの2つの機体を開発中ですが、現在最も機体数の多い120~170人乗りの市場から経済性を考えてもっと少ない乗客数で運行したいという需要と、50人程度の小さい機体では収入が見込めないのでもっと大きな機体がほしいという需要に応えるという両方を狙ったものになっています。
セールスポイントとして、乗客に対しては快適な客室、環境に対しては少ない排出物と低騒音、航空会社に対しては優れた経済性を訴求し、それらを実現するために、自動車の技術を活かした新型スリムシート、プラット&ホイットニー社の新型エンジン、CFDを活用した機体の空力設計を採用したことなどについてお話しいただきました。
ご講演の中で「MRJは『Mitsubishi Regional Jet』の略称ですが、多くの人々の期待を背にした『みんなのリージョナルジェット』と呼びたい」と言われていたことが大変印象的で、戸田様のMRJに対する熱い思いが感じられました。
航空機産業の歴史から始まり、最先端技術のご紹介まで、大変幅広いお話を聞かせていただき、会場からの満場の大きな拍手の中で約1時間の基調講演の幕が閉じられました。
ご講演:
『中国における自動車ビジネスの展開と課題』
東風汽車有限講師 総裁 中村 公泰 様

まず前段では、現在世界中で最も大きく、目を離すことのできない中国の自動車市場の概況についてお話しいただきました。
2005年時点では全世界に占める中国市場の割合は10%程度でしかありませんでしたが、2010年には28%にまで増加し、やや鈍化したとは言え2011年度も全体で約3.3%の増加、乗用車に至っては9.5%もの増加を示しています。
市場の保有台数は1億台と、既に日本の7,900万台を抜いた水準になっていますが、100世帯あたりの保有台数では、日本の108台に対して中国は8.8台とまだまだ少なく、混雑を理由に規制のかかった北京市でさえ23台という状況で、潜在需要という面では極めて大きいと言えます。また、購入者の内訳は全体の60%が一台目、つまり初めて車を買う人で、日本の10%以下と比べ大きな差があります。一時代前の私達日本人が初めての車を『わくわく』して買っていたあの時代が、まさに今の中国の状況であるというお話をされていました。
中国国内販売の国別シェアを見ると、早い時期に進出していた欧州メーカーで2005年時点の約40%が2011年には約20%に低下、日本車も約30%が20%に低下しているのに対し、中国民族系メーカーが35%を占めるまでに伸びてきています。そして、中国政府は国内自動車産業の発展を強力に後押ししており、国の12次5カ年計画で、2015年までに自主ブランドのシェアを40%にすること、輸出を10%に増加させること、省エネ・新エネ車を100万台にすることが目標に掲げられています。特にEVなど新エネ車に対しては最高6万元の補助金が交付されているなど、大きな力が入れられているそうです。
そして、後段では、中村様が総裁を務められている東風汽車有限公司(以下、DFL)についてご説明をいただきました。
DFLは、日産自動車株式会社が50%、東風汽車公司が50%の折半出資で、傘下に乗用車、トラックの開発・生産会社、さらに部品から生産設備の開発・生産までを含む多くの会社を擁する従業員約7万人の非常に大きな企業集団となっています。
そしてDFLでは、親会社である日産自動車株式会社の中期計画『日産パワー88』の下で中国での販売シェアを10%にするという目標に向け、今年アップデートした実行計画である『Plan13(3乗)』で、
①2010年比で2015年までに販売台数“1”00万台の上乗せ、 ②“1”stクラスの品質とサービス、 ③信頼される“1”つの企業DFL、
を掲げ活動されるとのことです。
中国政府の自主ブランド振興策に対しては、新ブランドである啓辰(ヴェヌーシア/VENUCIA)での新車展開を推進し、特に今後大きな成長が見込まれる内陸部の市場を重点において販売拡大に力を入れていくとのお話をされました。
以上のお話をいただきましたが、現在日本の製造業、特に自動車産業にとって最も重要である中国市場の動向についての具体的でわかり易い解説は、大変参考になるものであったことに加え、最前線でご活躍されている中村様の熱のこもったお話から、今後の発展に向けた『力』をいただけたように感じられました。
パネルディスカッション:
『将来に向けた、エンジニアリングITの方向性と課題』

パネルディスカッションは、「将来に向けた、エンジニアリングITの方向性と課題」をテーマに、 ①「3Dデータ活用の現状と目指すところ」 ②「機能安全規格ISO26262発効のインパクトとMBD」 ③「新興国市場展開とグローバル協業におけるE-ITの方向性」 ④「データ標準化や業界協調の方向性・実現性」 ⑤「システム構築の考え方とIT費用」 ⑥「今後のE-IT」の6項目について具体的に論議をしていただきました。
前回同様、最初に各項目について事前に準備いただいた内容をご紹介いただきましたが、今年は東日本大震災の関係から、危機管理上の教訓と対応について一言ずつお話をいただいてからのスタートとなりました。
まず、設計での3D活用の定着が進む中、今後の課題として、生産工程への3Dデータ活用、またCAEへのデータ連携強化について議論いただきました。近年特に3D単独図活用の取り組みが取り沙汰されていますが、そのかたわらでは2Dとの共存や整合の保持といった取り組みを進められている、といったお話が多くありました。
先般ようやく発効された自動車の安全規格ISO26262については、各社とも業務側主体での組織や体制を整備しプロセス改革から、という基本的な取り組みに着手されたという状況をご紹介いただきました。
超円高時代を迎え、今後ますます加速化される新興国への対応については、情報セキュリティ問題は大きな課題となっており、効率化に反比例しコスト増に比例するセキュリティ管理を、仕組みとしてどこまで取り入れるかについては、大きな悩みどころというお話がありました。
次にデータの標準化については、ISO化が進められているJTを中心にお話いただき、基幹CADに関わらず、JTにかける大きな期待というものを伺うことができました。同時にITベンダーに対してはJTでの確実なデータ流通の実現を要請され、自動車業界内部の協調だけでなくIT業界との協調の必要性についても言及されました。
IT費用をいかに削減していくかは共通の課題として挙げられていました。特に積みあがっていくソフトウェアの保守費については、ベンダーとして耳の痛いお話もありましたが、ソフトウェアの整理統合やライセンスの見直しなど、各社様での施策や方向性をご紹介いただきました。改めてベンダーの役割の重要性を問われているように感じました。
最後の話題としてE-ITの今後ということで、既にスタートされている具体的な取り組みや重点施策、方向性について、各社様の熱い思いと共にお話いただきました。
複雑化する業務の中、OEMメーカー様間のみならず、部品メーカー様を含めた自動車業界とIT業界とが協調しながら自動車産業を発展させていきたいという司会者の思いが語られ、パネルディスカッションが締めくくられました。

全体を通して
例年通り講演会場の外側通路で弊社製品やソリューションの展示を行いました。今回は午後からの開催だったこともあり、セミナー開始前にデモ展示をご覧いただくお客様が多くいらっしゃる一方で、講演の合間30分の休憩時間だけではゆっくり見られない、といったご意見もいただきました。短時間ではありましたが、お客様からは具体的なご質問やご相談をいただきました。
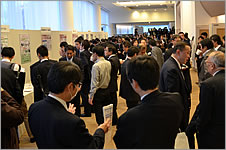
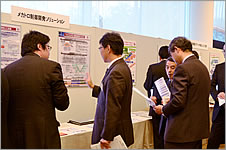
セミナー終了後の懇親会は、遅い時間からのスタートとなってしまいましたが、例年以上のお客様にご参加いただきました。中には、料理が用意されていることに気づかなかった、と言われる方もおられるほど会場がお客様で溢れんばかりとなっていました。二重三重の試練となった年ではありますが、グラスを片手にご歓談いただいているお客様にご挨拶をさせていただけることの有り難さを実感いたしました。お客様にとって有益なお時間となっていれば幸いです。
お客様からいただいいたアンケートの一部をご紹介させていただきます。
- 貴重な講演を聞くことができ大変参考になった。
- 今後も継続してもらいたい。
- 他に例のない自動車各社のパネルディスカッションを毎回楽しみにしている。
- 自動車各社のITの現状、方向性が分かって参考になった。
一方、内容に関してのご要望もいただきました。
- 講演数を増やしてほしい。
- デモや展示が見られる時間を増やしてほしい。
- パネルディスカッションはもっと長くてもよい。
- パネルディスカッションにサプライヤーやベンダーも加えてはどうか。
いずれのご意見も、今後のセミナー運営の参考にさせていただきたいと思っております。
また、お客様の業務に関するさまざまなお悩みについては、弊社営業、SEより詳細をお聞かせいただき、より良いご提案をさせていただければと思っております。
今後もお客様のお役に立てる情報を発信しながら、お客様のお悩みを解決できる企業を目指し、社員一同精進してまいります。今後ともデジタルプロセスをご愛顧いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。

多くの方にご参加いただいた懇親会
(DIPROニュース編集局)
PICK UP












