DIPROニュース
ベトナムにおけるオフショアを活用したサービス提供への取り組み
~日本での受け入れ研修実施報告~
1年前の本紙で、「サポートサービスへのオフショア活用」についてご紹介し、ベトナム現地要員の日本での受け入れ研修にも触れました。今回は、1年間にわたった研修の経過についてご紹介させていただきます。
短期間で質の高いサービススキルを
サポートサービスは、ソフト開発や解析などの分野と比べ、お客様の様々な環境や多様なニーズへの対応が必要とされるため、言葉や文化の異なる技術者に取り組んでもらうにはとても高いハードルを伴います。
このような背景から、現地での作業に先立ち、日本の現場で、いわば肌で感じるといった研修が必要と考え、企画したものです。

意外な感想と強い向上心
研修は、日本のビジネスマナーをはじめとする一般教育と、CADサポートスキル習得に加え、お客様の業務を理解するための工場見学などからなる専門教育で構成されています。
一般教育では、工場見学を終えた後の研修生の感想がとても印象的です。最も関心が高かったのは、ロボットをはじめとする日本の象徴的な先進技術ではなく、工場での徹底した品質管理への取り組みであり、環境への取り組みでした。
これは私たちにとっても新鮮で、ともすれば忘れがちな、現場での地道な改善の積み重ねの価値を再認識させられた瞬間でもありました。
専門教育は、CAD操作のトレーニングから、教育講師、さらにはお客様先でのサポート実習と大変幅広く、研修生にとっては未経験な分野への挑戦の連続だったはずです。
しかし、落書きでもされたかのように、メモと付箋紙で埋め尽くされた日本語だらけのテキストが、1年間を通じて持ち続けた強い向上心を物語っているように感じられました。

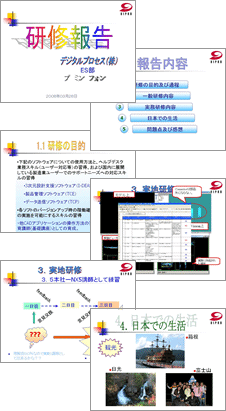
研修中の課題は“灯台下暗し”
意外にも、「日本語力をいかに向上させるか」ということが、1年間にわたって実施してきた研修の課題となりました。読み書きのレベルは格段に上がりました。ところが、会話力を考えると、研修の進め方を再検討せざるを得ません。この点は研修生自身も実感しており、報告会でも問題点として挙げていました。もともと研修生は、日本語に重点を置いた人選を行っているため、言葉が障害になることはありません。
しかし、専門技術の習得に力を入れるほど研修生のみでの作業が増加することになり、日本語での会話の機会が少なくなる傾向となってしまいます。
今後は、日本語によるコミュニケーションの頻度を高めるべく、研修プログラムに改善を加えていきたいと思います。
10件の○より3件の×
研修最終日には、1年間の研修成果について日本語でまとめた資料による成果報告会を実施しました。
印象深かったのは、教育講師担当中に受けた質問への回答についてです。結果は13件中10件即答という立派なものでしたが、「3件即答できず(>_<)」という自己評価。向上心の片鱗が散見される報告でした。
ちなみにその日は、ベトナムの民族衣装であるアオザイを披露しての発表会となりました。緊張しながら立っている研修生に良く似合っており、とても印象深い発表会となりました。
ベトナムでの現実
日本で身に付けた技術を糧に他社へのステップアップを図ろうと離職するケース、あるいはせっかく習得した技術を活かすことができないジレンマから離職してしまうケースなど、帰国した研修生の離職率が思いのほか高いそうです。向上心が強い国民性であるが故に、そういった結果が顕著に現れるのかも知れません。
帰国後のフォローも含めて「人と技術の定着」に向けた工夫をしていきたいと考えています。
最後に
この3月末に当社で初めての研修生が帰国しました。桜を楽しみに来日した1年前は、開花時期が例年になく早まってしまったために、既にほとんどが葉桜になっていました。今年満開の桜が見られたことを、とても喜んでいた研修生の「帰りたくない」という言葉を聞くと、寂しくもあり、同時に嬉しくもありました。
研修生の帰国は、仲間がベトナムに増えたことを意味すると同時に、“ベトナム+DIPRO”の切磋琢磨パワーの次なるステップへのスタートでもあります。お客様のご支援をさせていただく、という目的をベトナムの仲間と共有し、今後とも取り組んでまいります。
(エンジニアリングサービス部 課長 藤原 智子)
PICK UP












