DIPROニュース
NX-CAM Feature Based Machining 機能のご紹介
厳しいコスト競争、納期短縮が求められる中で、機械加工業界においても例外なくさらなる業務の効率化が求められています。3次元化や自動化が比較的進んでいる業界とはいえ、設計部署で作成された3次元データだけで業務が進められるわけではなく、2次元図面から公差などの情報を読み取っている事例が未だ多くあります。
また、パスを生成する段階においては自動で行うCAMは多くありますが、その前段階で各種条件は手動で設定するため、多くの工数と期間を必要とします。特に、金型の構造部や自動車のシリンダーヘッドなどの幾何形状を多く加工するような製品に対しては、毎回同じような加工を設定するにもかかわらず、多くの手間をかけて業務が行われています。
そこで、NCプログラム作成業務において、手動で行っていたそれら設定作業を自動化し、工数の削減や納期短縮に貢献するFBM(Feature Based Machining)の機能をご紹介いたします。
FBM(Feature Based Machining)機能概要
NX バージョン7では大きく進化したFBMの機能が3つあります。
① フィーチャー認識機能
3次元モデル形状を読み取り自動で加工部位をフィーチャーとして認識します。以前のバージョンに比べ、複雑な穴や溝の形状など認識できるフィーチャーの種類が格段に増えました。
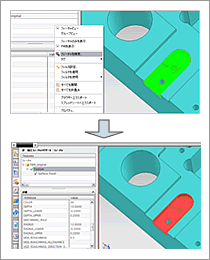
② 自動オペレーション作成機能
予め登録した加工ナレッジ(ルール)に従って、①で認識したフィーチャー(加工形状)に対してオペレーション(カッターパス)を設定します。
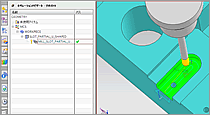
③ 加工ナレッジ登録機能
加工を行う形状や公差に対して、必要な工具や加工パスの種類、各種切削条件のルールを設定します。以前のバージョンでは加工パスのバリエーションをテンプレートを選択することで設定していましたが、バージョン7では詳細な形状や公差などのパラメータを用いてルールを登録することが可能になりました。そのため、同一のルール上に複数のバリエーションを設定することができ、より多くの工数の削減が見込まれます。
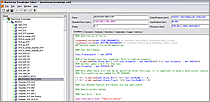
フィーチャー認識機能
3次元形状を読み取り、穴や面などの加工形状を自動的にフィーチャーとして認識します。製品形状(パート)だけでなく、加工前形状(ブランク)も登録すると、取り代なども認識することが可能です。
加工形状はパラメトリックに形、大きさなどが幾何形状として認識されます。あくまで形状を見て認識をするので他CADなどで作成されたデータを取り込んでも使用することができます。
また、3次元形状に入力した面粗度や径公差などの公差情報(PMI)、色、各種属性情報など設計で3次元形状に付与された情報も合わせて認識することが可能となったため、手入力していた属性情報を自動的に読み込めるようになりました。
以下に認識できるフィーチャーの代表的な例を示します。この他にも50種類以上の形状を認識することができます。
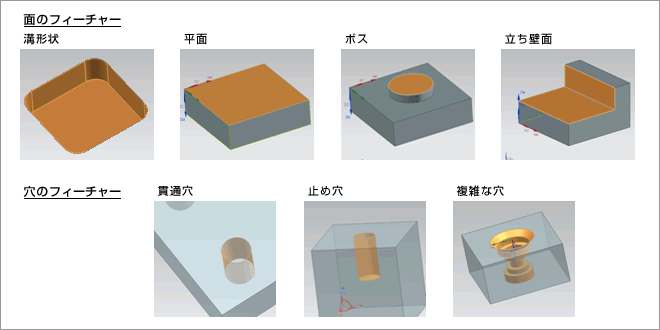
自動オペレーション作成機能
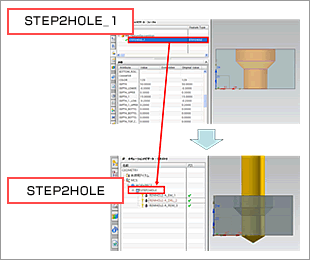
認識したフィーチャー情報の形状タイプ、大きさ、公差、各種属性情報に対して、あらかじめ登録した加工ナレッジに従い、最適なオペレーションを自動で設定します。また、同時にそれぞれのオペレーションに対してDBに登録した工具が選択されます。工具DBには工具形状のほかに、切削条件も入力することができ、その工具に最適な切削条件でカッターパスを設定することができます。
加工ナレッジ登録(MKE:Machining Knowledge Editor)
従来は3次元形状を作成フィーチャー認識させた上で、認識させたフィーチャーとそれを切削するパスおよび工具、切削条件の全てを入力したテンプレートファイルをバリエーション毎に各々作成して登録しなければなりませんでした。また、穴形状のモデリング方法が異なる場合も、それぞれに対してテンプレートを作成しなければなりませんでした。
現バージョンでは、認識したフィーチャーのパラメータに対して条件式を入力することでルールを設定するだけなので、テンプレート作成のためにモデリングなどを行う必要がありません。パラメータと条件式によって設定するのでモデリング方法によらず設定できます。もちろん、他のCADで作成した製品モデルやJTなど中間フォーマットからインポートした形状も同じルールを適用することができます。
各ルールには優先順位が設定でき、同じ形状に対しても複数のルールを持つことが可能です。例えば、同じ製品形状であっても表面精度によって、面加工のパス数や取り残し量、切削条件などを変更したり、フライスの径をコーナーRに合わせて選択したりすることが可能です。穴加工では、穴の径と同じ工具径のドリルを選択したり、L/D>5ならばG83(深穴サイクル)それ以下ならG81(ドリルサイクル)を区別して選択することも可能です。
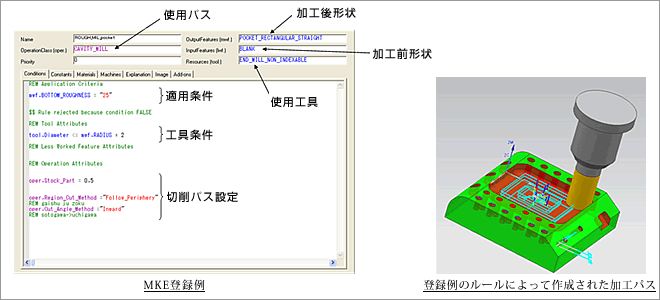
多くの充実した機能を有するNXを使いこなし、業務の効率化を推し進めていただきたく考えております。
弊社ではFBMの機能に関するお問い合わせとともに、ルールのまとめ方や標準化の進め方などのご相談も承っております。
NXを既に導入されていて、さらなる効率化を検討されているお客様、あるいは業務への適用にお悩みのお客様など、弊社までお問い合わせいただければ幸いです。
(デジタルコンテンツサービス部 清水)
PICK UP












