DIPROニュース
オートモーティブデジタルプロセスセミナー2013開催

12月6日(金)、パシフィコ横浜において「オートモーティブデジタルプロセスセミナー2013」を開催いたしました。一昨年より午後からの開催になりましたが、同時開催の「DNCデンタルスペシャルセッション2013」と併せて大勢のお客様にご来場いただきました。ご来場の皆様ならびに開催にご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
昨年は超円高環境下にあり、これにあえぐ日本経済や製造業の話題にふれましたが、今年のセミナー前日の時点でドルは24%、株価はなんと61%も上昇しています。きわめて大きな変化ですが、いまだ日本の製造業の業績はまだら模様の状況にあり、新しい技術の開発やQCDの向上など地道に取り組んでいくことが重要であると考えています。
今回のセミナーは、変化が激しく先の見通せない時代に、日本の製造業の新たな可能性や方向性を考えていく上で、ヒントとなるべく状況認識や考え方をご提示いただき、今まさに進みつつある自動車メーカーの新たな動きをご紹介いただくことを企画しました。

通算で21回目の今回は、基調講演としてNTTデータ経営研究所所長、千葉商科大学大学院名誉教授の斎藤 精一郎様に「日本経済再生シナリオ~変化の時代にどう挑むか~」と題してお話しいただきました。
また、日産自動車株式会社 執行役員の松村 基宏様に「CMF(コモンモジュールファミリ)の考え方と今後の展望」というタイトルで日産自動車が中期経営計画NP88(Nissan Power88)を達成するための最重点方策であるモジュール開発について、わかり易くご説明をいただきました。
続いて、トヨタ自動車株式会社 エンジニアリング情報管理部 部長の江口 浩二様から、同社のグローバル化を支える技術情報マネジメントのご講演内容を受けて、最後に、毎回ご好評をいただいておりますパネルディスカッションにて、自動車メーカーの設計・技術管理のキーマンの皆様、トヨタ自動車株式会社の江口 浩二様、日産自動車株式会社の笹川 正彦様、株式会社本田技術研究所の前川 忠由様、マツダ株式会社の縄 淳二様、三菱自動車株式会社の野村 雅彦様、スズキ株式会社の市原 誠様にご登壇いただき、各社の現況、課題及び解決策などについて語っていただきました。
基調講演:『日本経済再生シナリオ~変化の時代にどう挑むか~』
NTTデータ経営研究所所長 千葉商科大学大学院名誉教授 斎藤 精一郎 様

斎藤様は、変化の時代にどう挑むかというタイトルで3つの観点からお話をされました。
まず、日本経済をとりまく今の環境ですが、不透明でどこに向かっていくのかわからなくなっていて勢いがありません。成長が低成長軌道に乗ってしまっており、株価や土地などの資産価値が上がっているが過熱感が無く、金融緩和をやっているのに長期金利があがらないからです。原因として、BRICsが経済成長に突入して世界経済をリードしていることが挙げられます。BRICsだけで労働人口は14億人で、これは日本の30倍、賃金は1/6~1/15です。さらに製品のモジュール化により技術が移転したため、家電製品のような物が作れるようになってきました。これでは、円が25%安くなってもかないません。このように産業構造が新興国にシフトしていることが、勢いのない現状の理由です。
次に日本経済の現況です。2003年から産業構造の大転換が起こり、世界経済がグローバル化したことから新興国市場が増加してきました。しかし、株価は1989年に比べるとまだ1/3の水準、欧米では3~6倍、これは儲けていた家電等が新興国に取られてしまったためです。1990年から10年間はゼロ成長、その後の13年間は0.5%成長で、この間賃金は下がったままです。非正規社員も小泉首相の時は23%ですが、現在は40%。これは企業に自信がなくなってきているからで、製造業の事業構造が錆びついてしまったためです。自動車産業はどうかというと、新興市場を中心に海外生産が伸びてきており、海外生産の比率は60%ぐらいです。海外生産にシフトすると、円が25%安くなると海外生産分の売上は25%増加します。今日本で利益が出ているところは海外生産をうまくやっている所ですが、本当に生き残ろうとすれば、事業構造全体を刷新することが必要です。
最後に今後の自動車産業のお話です。自動車という製品は、イノベーティブ、グローバル、カルチュラルという3つの特性を持っています。イノベーティブとは、製品に創造性が組み込まれていること、美的価値があること、つまり時代の要請を組込んで製品化するということです。グローバルとは、日本は急速に人口が減少し、海外マーケットはどんどん変化するのでクイック&ジャストミートで現地に行かざるを得ない状況で、このための体制整備が必要です。カルチュラルとは、日本文化の持っている伝統、習熟技術を車が受け継ぐ必要があるということです。そのために日本にホームベースを置いて基本的な戦略を考え、デジタル革命からくる要請を受けた自動車作りを行います。車は社会と時代の変化とともに進化してくる可能性があります。そこに日本の製造業の原点があり、それがうまくいくことで日本の新しい製造業が出てくると思います。
そして最後に、① 設計力を磨くこと、摺合せや共同していくことが大事。これで、1+1=2ではなく3以上にしていくことができる、② 中小企業が海外に出ていくには、関連メーカが経営基盤強化のためM&A、統合を積極的に行うこと、③ 本物の職人芸をホームベースに置き、世界に活かしていくこと。人材育成を行う新しい教育システムを民間企業が作ることが必要、という3つのポイントで、“日本経済再生シナリオ”のご講演を締めくくられました。
講演:『CMF(コモンモジュールファミリ)の考え方と今後の展望』
日産自動車株式会社 執行役員 松村 基宏 様

松村様からは、日産自動車株式会社様の会社紹介に引き続き、コモンモジュールファミリー(以下CMF)開発の考え方、日産とルノーのアライアンスとCMF開発、CMF開発の留意点、デジタルプロセスに期待することのお話をいただきました。
CMFでは部品種類の削減による生産の効率化、調達の最適化により大幅にコストを削減することを目的としています。そのために、従来のプラットフォームの考え方から、エンジンコンパートメント、フロントアンダーボディ、コックピット、リヤアンダーボディ、それにE/E(電気/電子)アーキテクチャを加えた5つのモジュールを定義しています。その各モジュールを重量とキャビンの大きさなどで大括りにしたモジュール群に分けて共用化を図ることがCMFの基本的な考え方になっています。CMF開発のベースとして大変重要な要素となっているのがデジタル化技術で、実験のシミュレーションやBOMとPDMの連携、ビュアーによる見栄え確認などにより、開発期間を大幅に短縮しています。
次にルノーと日産のアライアンスの中では、スケールメリットの創出と開発の効率化、投資の削減という面で、CMFが大きく貢献しています。例としてステアリングメンバーという部品ではルノーと日産で合わせて7種類あったものを1種類にすることができたことを紹介されました。そのほかにもHVACやラジエターという部品でも共用化が進んだということです。
CMFの留意点ということに関しては、各モジュールの適正なサイズへの適用や将来的にどのように進化させていくかという考え方が非常に大切なことで、これを間違えると共用化が大きく崩れることになります。また、品質、信頼性の確認をFMEAやFTAなどを駆使して合理的に実施しないと、実験の効率化は期待できないことにも注意が必要だとのことでした。
最後に、デジタルプロセスに期待することについてお話をいただきました。CMF開発にデジタルプロセスは必須な条件になっており、今後はさらなる処理速度の向上、オペレーションの簡素化などが期待されています。将来的には感性の世界のデジタル化や判断の人工知能化が期待されているということで、例として車体のあわせ品質などをデジタルに表現することなどがあげられました。
講演:『トヨタの持続的成長を支えるグローバル技術情報マネージメント』
トヨタ自動車株式会社エンジニアリング情報管理部部長 江口 浩二 様

最初に、トヨタ自動車株式会社様の会社および組織概要から始まり、江口様が所属されるエンジニアリング情報管理部(EDC)をご紹介いただきました。EDCは4つのビジネスユニットを連携させる機能部署である、IT・ITS本部に属されています。「情報管理部」という言葉から、技術情報管理部下に配される部署と考えられますが、トヨタ自動車株式会社様では、経営資産であるエンジニアリング情報を、生産領域を含め、全社的かつグローバルに有効に扱うことを推進する機能を持った組織、との位置付けから、情報領域下に配されているそうです。
次に技術情報管理の現状ということで、ツールとデータの流れ、運用についてご説明いただきました。トヨタ自動車株式会社様では、車両系CAD、ユニット系CAD、内製CADそれぞれのデータを管理できる内製化PDMと、車両仕様書・部品表とを連携させ、それらデータを生産技術や他拠点の設計部門で活用し、さらにはサプライヤ様に配信、といった仕組みを構築されています。また、PDMを活用した出図日程管理を行い、設計の出図率も向上し、問題点の摘出が前倒しされてきている、といった運用面での効果もお話しいただきました。さらにPDMのグローバル展開については、世界中の生産拠点への展開が進み、PDMデータを参照しながらの業務が進められている中で、中国への展開を重視しつつ、また、遠隔地でのレスポンスが課題であることなどご紹介くださいました。
続いて、直面している課題としてデータ作成・管理時の設計情報の継承や、技術情報の長期保管、協業先あるいは合弁会社との技術情報の運用、特に情報を開示する中でのセキュリティコントロールなど、他社にも通ずるような課題をいくつかご紹介いただきました。
最後に、EDCの大切な機能として、日常業務の中で、標準化、改善・改革のサイクルを推進し、企業の持続的成長を継続させるために貢献できる人材を育成することの重要性と、そういった人材で構成されるEDCが、国内のみならずグローバルで活躍できる一つの機能となる“Global One EDC”構想への熱い思いを語られました。
パネルディスカッション:
「データ基準による開発業務革新を推進するための技術情報管理のあり方」
昨年は、海外でのビジネス拡大や国内における開発および生産領域でのデジタル化に伴い、仕事のやり方が大きく変化していく中、技術情報をどのように管理していくべきかといった点で議論いただきました。今年も同じ枠組の中から、自動車メーカーだけでなくサプライヤも含めた共通課題を3つのサブテーマに絞り、先に行われた江口様のご講演内容を参考にしながら、議論を進めていただきました。
先ず「技術(設計)情報管理のあるべき機能」という一つ目のサブテーマの下に、技術情報の管理体制や役割について、設計者が効率的に仕事を進めるための業務風土の構築をポイントに、課題を織り交ぜながらご紹介いただきました。また、開発プロセスにおける情報管理部署の役割を理解するために出図日程管理への関わり方を例に、出図日程を守るための取り組み、業務の進捗を可視化するためのシステム構築や設計者が自己管理するための環境整備といった、ツールやデジタルデータを活用した日程管理業務を具体的にご説明いただきました。
次の「車両開発における合弁や協業の進め方」というサブテーマについても事例を中心に分かり易くご紹介いただきました。海外の開発や生産拠点に対し、明確な役割分担の下でツールの共通化や開発情報の一元管理、そして技術情報を共有化することにより、同じプロセスで時間差なくグローバルな開発を進められている事例や、逆に文化の違いなどにより思うように進められていない、といったお悩みについてもお聞きすることができました。また、グローバルなビジネスを進める上で、想定した様々なリスク対応への取り組み事例や、特にセキュリティ管理についてはシステム的なものから教育への取り組みなど、大変興味深い事例のご紹介もありました。
最後は「デジタルデータの活用における今後の進め方」についてのお考えをお話しいただきました。
DMUによる革新的な開発プロセスによりデジタルデータが行き渡り、一気通貫で仕事を進められる環境が整いつつあります。デジタルデータの活用を更に進化させて開発期間の短縮を目指す、といったお話の一方で、活用の狙いを明確にした上で時間をかけてでも人手を介してデータを最新に維持することの必要性といったお話もありました。また、設計者にはマニュアル冊子が重宝されているといった現場ならではのお話もあり、目的に応じた使い分け、デジタルとアナログの両輪による効果的な進め方、というベンダーとしても考えさせられるご紹介もありました。
そして最後に、パネリストの皆様から技術情報管理に関わる今後の取り組みや思い、ベンダーへの要望など含めたコメントをいただき、議論いただいた内容が参加者皆さまのご参考になれば、との司会者の思いでパネルディスカッションを終了いたしました。

全体を通して
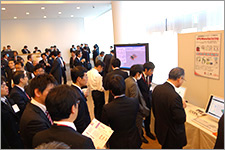
講演の合間の休憩時間には、講演会場の外側通路で弊社製品やソリューションのデモ展示を行い、お客様から具体的なご質問やご相談をいただきました。
セミナー終了後の懇親会は、今年初めて同時開催しました「DNCデンタルスペシャルセッション2013」にご参加いただいたお客様も合流いただき、会場はいつも以上に溢れんばかりの賑わいとなりました。親しい方同士はもちろん、知らない方同士も和やかに談笑されていて、まさに異業種交流の場になっているのを拝見することができました。
アンケートやご要望でいただいた、”大変参考になった、また来年もやって欲しい”という声や運営に関する多くのご意見を今後の参考とさせていただきます。また、お客様の業務に関するさまざまなお悩みにつきましては、弊社営業やSEが詳細をお聞きして、より良いご提案をさせていただければと思っております。
お客様のお役に立てる情報を発信しながら、お客様のお悩みを解決できる企業を目指し、社員一同精進してまいりますので、今後とも弊社をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
(DIPROニュース編集局)
PICK UP












