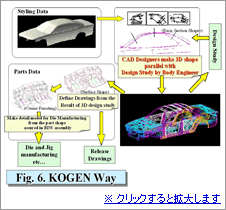DIPROニュース
「안녕하세요!(アンニョンハセヨ)」 ~韓国訪問記~
日韓・工学設計ワークショップ2008に参加して
日韓・工学設計ワークショップ2008に参加して
機械学会 設計光学・システム部門の活動
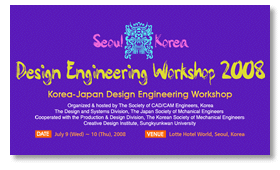
日本機械学会は、歴史もあり、かつ総会員数38,000人の日本で最大級の学術専門家集団です。20の部門を擁し、大学の先生方を中心に積極的な活動をしている団体です。
この中の一部門として、設計工学・システム部門が広く、設計工学とシステム工学をカバーして研究活動を行っており、「CAD」「最適設計」「知識工学」「感性設計」などのテーマで、設計とシステムに関する幅広い学術情報の交換の場として機能しています。弊社のビジネスに関係深いCAD分野に関しては、精密工学会と並び、研究など諸活動のベースキャンプの役割を果たしています。
筆者の加藤は2007年から当部門の運営委員を務めており、学会活動の活性化に貢献していきたいと思っております。
日韓ワークショップ
機械学会 設計工学・システム部門とThe Society of CAD/CAM Engineering, Koreaが共催し、CADと設計分野の技術的情報交換の場として、2001年から日本と韓国とで隔年で開催されています。8回目となる今年は韓国ソウルで7/9-10の2日間実施されました。地元韓国から50名、日本や中国などの海外から20名程度が参加する比較的小規模な技術交流会です。
今回、筆者も設計工学・システム部門のメンバーとして、論文発表とディスカッションに参加しました。
“KOGEN(構造原図)方式”をご紹介
(以下、論文の概要)
日本の自動車メーカーは、2005年に発売した新車の開発で、ついに1年未満の製品開発期間を実現した。日産自動車が世界に先駆けて、2000代半ばに実現した製品開発期間10.5ヶ月の「超短縮プロセス=V3P Process」は、1980年代の「5ロット・プロセス=CAD/CAM一元化Process」の第一世代改革と、1990年代の「短縮プロセス=データ衝Process」の第二世代改革を経て実現した第三世代プロセス改革といえる。
第一世代改革のCAD/CAM一元化は、「スタイリングCADの実現」「構造原図方式」「型製作のCAM化」の3方策で実現した。構造原図方式では、専任のCADデザイナーが車体構造原図(3次元CAD形状)の作成から修正、仕上げまでの責任を持つ。設計者と分業することによりCADデータ品質を確保し、効率的にデータを作り、下流にデータを保証することが可能になった。KOGEN方式がCAD/CAM一元化を支えるキーファクターであり(図1)、現在では多くの自動車会社がこの分業方式をとっている。
構造原図方式により実現した1980年代のCAD/CAM一元化が、今日の超短縮プロセスの基盤を作った。その3方策のなかでも組織的な打ち手である構造原図方式を確立し発展させたことが、大きな成功要因となった。日産自動車では、構造原図方式により、工機部門、組立て工場、部品メーカーの下流に対して、B.I.W(Body in White)のアセンブリとしての保証を設計部門が責任をもち実施することになった。
構造原図方式の優位性は下記の3点である。
- 設計者と分業し専門化することによりCADデータ品質を確保できる。
- 専門特化により技能が上がり、CADデータ作成の工数削減と期間短縮を実現しやすい。特に型製作に不可欠なフィレットRまで一貫して同じ作業者が集中して作成することによる効率化は大きい。
- 設計部門が一元的にデータ保証をすることにより、下流の複数部門での重複作業を排除できる。
しかし、構造原図方式によるモデリング分業が進展するにつれ、近年別の問題が起こってきた。設計者自身がCADモデリングに手を下さないことにより、必要なときに必要な検討を自分ひとりでできなくなってしまった。また、細部形状をCADデザイナーに任せることにより、自分の担当部品でさえ、形状全部を把握できなくなってしまった。担当部品について「全体から細部まで」「性能から製造性まで」把握している設計技術者が少なくなりつつある。
構造原図方式がもたらした設計者の力量低下に対し、当面有効な方策はないが、強いて挙げるとするならば、構造原図方式のCADデザイナーを経験した設計者を育てることしかなさそうである。
将来、この問題を解決できる設計意図で駆動でき、設計者が簡便に使える“次世代のCADシステム”の実現に尽力していただくことを要望して結びの言葉にしたい。
韓国のエネルギー

筆者の発表に関しては、「一般に行われているCADオペレーターによる設計支援と何が違うのか?」などの質問もあり、活発な論議ができました。韓国のこの分野のスペシャリストと知り合いになり、意見交換できたことで、今回の参加の目的を果たせたように感じます。
それと同時に、今回のワークショップへの参加は、韓国の学者・専門家の勢いに圧倒された貴重な体験でもありました。日本の参加者が冷静に自身の成果を報告している態度に比べると、韓国の参加者は皆、ややもすると誇張してでもと捉えられるくらい積極的に自身の業績をアピールする一方、堪能な英語を駆使し、活発に質疑応答を繰り広げていました。米国での研究活動を通し、韓国で活躍しているエキスパートがこの分野の学会をリードしていることがこのことからも窺えます。
これは決して学会活動に留まらず、企業活動にも相通じるのではないかと思います。正直、「韓国恐るべし」と実感した次第です。
DIPROにとっての意義とお客様への貢献
筆者が参加している機械学会の活動は、弊社のビジネスの基盤作りに役立つのみならず、お客様への産学連携の橋渡しの役割も担えるのではないかと感じています。大手自動車メーカーなどのビッグユーザー様は別として、大学などの研究機関と協議するきっかけは少ないお客様が多いように感じます。弊社の学会活動が、この面でもお客様の研究活動へのご支援と仲立ちでお役に立てれば幸いです。
今後も、CAD/CAM/CAEや設計に関する研究動向を掌握し、DIPROのプロダクトとサービスに生かすために、大学などの研究機関との積極的な連携を図っていきたいと思います。
(取締役 加藤 廣)
PICK UP