DIPROニュース
VPSビジネス部のご紹介
この7月、新たにDIPROに仲間入りしたVPSビジネス部のご紹介をさせていただきます。
VPS(Virtual Product Simulator)は、一般的に「デジタル・モックアップ」と呼ばれるカテゴリのソフトウェア・パッケージです。VPSビジネス部ではこのパッケージの開発から、セミナー開催などのプロモーション、お客様への提案、導入のコンサルティング、カスタマイズなど、パッケージビジネスに関する全ての活動を行っています。
VPSの「歴史」
VPSは、もともと富士通グループにおける情報機器や通信機器の製品開発のために、富士通のハードウェア開発支援部門で開発されたソフトウェアでした。これは1997年から現場での使用が始まり、現在、富士通グループでは3次元CAD導入数の3倍ものVPS導入実績があります。
1999年からは富士通グループ外への販売が開始されました。電機会社である富士通発のパッケージであるため、当初はキヤノン様、ソニー様などの電機・精密分野のお客様が多かったのですが、現在では工作機械、輸送機器、産業用装置などへも適用分野が広がっており、約250社にものぼるお客様にご使用いただいています。
現在、パッケージの要素技術の研究は富士通研究所が行い、開発は富士通アドバンストテクノロジ(FATEC)とDIPROが共同で行っています。また、富士通グループ外のお客様に対する全ての活動はDIPROが行っています。
仮想試作
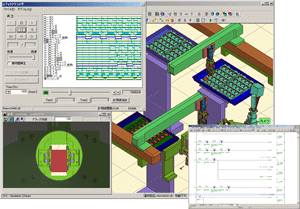
図1.組み込みソフトウェアと仮想メカを結合したDR
このモデルは右下に示したラダープログラムにより駆動。
画面左上は装置の動作状況を表す、仮想ロジックアナライザ。
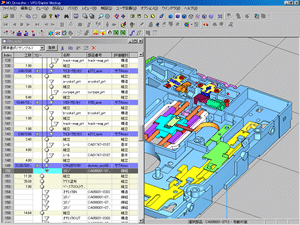
図2.組立フローとそれと連動したアニメーションによるDR
組立フローを作成し、作業時間や製造容易性などを把握。
右モデルはフローと連動し、視覚的にフロー改善の検討が可能。
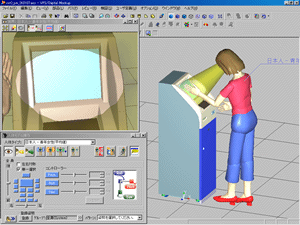
図3.人体モデルを登場させて、操作性の確認を行うDR
実際の操作シーンを想定して、DRを実施。
左上は人体モデルから見た視野。楕円は有効視野範囲。
VPSの目的は、「試作前(出図前)の段階でVPSを使って仮想的に試作を行い、その仮想試作機でデザイン・レビュー(DR)を実施することにより、設計品質を高め、開発リードタイムを短縮する」というものです。
仮想試作機を実現するために、VPSは大きく二種類の機能を用意しています。1つ目は、「プロダクトの可視化」です。これは、「あたかも実際のプロダクトがそこにあるかのように、コンピュータ上に再現する」機能です。3次元CADで作成した形状データのほかに、「動作機構」、「ハーネス、フラットケーブルなどの柔軟体」、「組み込みソフトウェア」など、製品の構成要素としては一体不可分なデータが定義できるようになっていて、これらを用いたDRが可能です。(図1)
2つ目の機能は、「プロセスの可視化」です。プロダクトは開発が完了すると、工場で組み立てられた後、出荷・販売され、エンドユーザーによって使用されます。その後、製品によっては、リペアセンターで補修されたり、リサイクルのために分解されたりするでしょう。この過程(プロセス)を製品開発の出図前の段階で可視化するのが、VPSの大きな狙いです。
「プロセスの可視化」の中でもアセンブリ産業において非常に重要なのは、製品の組み立てフローを設計し、組み立て時間を見積もり、組立性(容易性、組立品質など)を評価すること(図2)、また実際の使用環境下での製品の操作性を確認すること(図3)です。
このようにプロダクトとプロセスの可視化を通じ、仮想試作機を用いたDRを強力に支援します。
VDR
仮想試作機を用いたデザイン・レビューのことを、VPSではVDR(Virtual Design Review)と呼んでいます。実は、VPSは単なる「パッケージ」ではなくVDRを企業にどのように導入していくか、という「手法・方法論(Methodology)」を含んでいます。この「VDR導入手法」によって、実際の顧客の現場では、
① 導入プロジェクトの設立
(トップ、プロジェクトリーダー、関連部門リーダー、支援チーム)
② 過去の開発した機種で、試作以降で起こった不具合点の分析
③ VDRの導入効果のデジタルな見積もり
④ VDRチェックシートの作成
⑤ VDR運用ルールの作成と実施
⑥ 試作後のVDRの有効度の確認と改善
という手順(概略)で導入が進むのが普通です。この手法を用いたコンサルティングが、VPSビジネス部の重要なミッションとなっています。
VDR導入をお客様に提案したとき、必ずといってよいほど「総論賛成各論反対」の状況になります。その各論反対の理由の大きなものが「時間がない、余裕がない」ということです。VDRは出図前に新たな工程を設けることになるので、設計部門にしろ生産技術部門にしろ、当然そういった意見が出てきます。そこを突破してプロセスを改革するためには、現場・現実に根ざしてVDR導入の効果をデジタルに表現し、「全体最適のためにはその方がよい」という、モノづくり関連部門の意思統一を図る必要があります。VDR導入手法の最大の狙いはそこです。
VPS事例セミナー
VPS導入は企業のモノづくりプロセスの改革になるため、その適用の実態や導入の細部は企業によってさまざまです。こういった企業のノウハウや導入効果を共有するため、富士通グループでは年2回の「VPS事例セミナー」を開催し、導入済み企業のプロジェクトリーダーから、ご発表いただいております。
このセミナーは2002年2月から始まり、2005年8月からはVPS以外のPLM事例も含めた「PLM実践フォーラム」に拡大し続いています。2008年の8月で14回を数えるに至り、ご発表いただいたVPS導入ユーザー様も延べ40社になります。
導入効果は各社多様ですが、「試作後の設計変更数が60%~80%削減された」という点は、どのお客様からも挙げられた共通の効果です。さらには、「組み立てに関する不良がゼロになった」、「作業標準書の作成工数が激減した」と、多くのお客様にご発表いただきました。こういった事例の集積が「VPSコミュニティー」の大きな財産になっています。
VPSはVDRという「場」を作ることによって、モノづくり関係部門エンジニアの方のノウハウ・経験を集め、品質向上と期間短縮をはかるツールです。これは本来「日本の製造業がもっとも得意とする、モノづくりスタイル」でしょう。そこをITとプロセスの融合で支援するのがVPSです。今後もパッケージを通して、日本における製造業の競争力の向上に貢献していきたいと思います。
当社では、この領域で自動車や航空機等の大規模アセンブリに強みを持つVridgeRと、電気・精密産業をベースとした豊富なアプリケーションを持つVPSを組み合わせ、お客様に最適なソリューションをご提供してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。
(取締役 湯浅 英樹)
PICK UP












