DIPROニュース
「eラーニングコンテンツ受託開発サービス」のご紹介
はじめに
製造業においては、厳しい事業環境の中、若年者の入社人数が減少するなど人材の高齢化が進み、熟練した技術者の知識やスキルをどのように伝承していくかお悩みのお客様もいらっしゃると思います。また、このような環境下で、効率化を図るためにCAD、PDM、BOMなどのデジタルエンジニアリングツールを導入はしたものの、導入後の教育に時間もコストもかけられないとお困りのお客様も多いかと思います。
本稿ではそのようなお客様をご支援させていただく「eラーニングコンテンツ受託開発サービス」についてご紹介します。
教育現場の課題に対するeラーニングのメリット
システム導入後の教育にはさまざまな課題が出てきます。業務が忙しくて教育を受けに行くことが難しい、とは言え社内で教育環境を整備するには、何台もの端末を準備し、システムを導入する作業が必要となります。また、今後グローバル展開していく際には日本語だけではなく、英語・中国語など多言語での教育に対応する必要も出てきます。このような課題に対しeラーニングを利用した教育は、ソフトウェアがインストールされていなくても、疑似操作で技術習得ができるため、いつでもどこでも気軽に受講でき、また翻訳のみで海外展開へも活用できるといったメリットもあります。
eラーニングだけで大丈夫なのか?
最初からeラーニングで本当に覚えられるのか、という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか。講師に自由に質問ができ、即時にFace to Faceで講師のフォローが受けられる集合教育にはeラーニングにはないメリットも数多くあります。
すべてをeラーニングに頼るのではなく、集合教育とeラーニングのそれぞれのメリットを上手く組み合わせることにより、大きな成果を挙げられたケースもあります。
たとえば、教育講座を受けたいけれど、普段設計業務をしている方たちについていける自信がないので予習したいというお客様については、任意で受講できる予習用eラーニングを提供することで、集合教育に遅れをとることなく受講でき、さらに、受講者全体のレベルのばらつきを減らす結果に繋がりました。
また、教育を受講させたいが、業務への支障をできるだけ抑えたいという教育担当者のご要望に対しては、全員が共通で覚える必要がある基本的な内容のみを厳選した集合教育を実施し、基礎知識を身に付けたあとの専門知識はeラーニングで習得するという組み合わせ教育を実施しました。これにより、業務への支障を最小限に抑え、日数を短縮化した集合教育を実現されています。
このように、お客様のさまざまなニーズに合った教育の改善方法をご提案させていただきます。
eラーニングはどれも同じ?
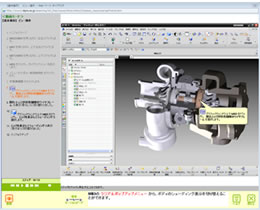
分かり易く表示することもできます
弊社では、お客様のご要望に応じてさまざまなタイプのeラーニングをご提供させていただいております。オプションの例として、音声付き、音声なしのタイプを選ぶことができます。
音声付きの教材は、「集合教育と同じように、説明を聞いて学習できる」、「聞きながら操作できるので理解しやすい」というメリットがあります。初心者向けの入門教材や、社内展開するソフトウェアの利点をアピールするためのデモンストレーションといった用途には、音声付きをお勧めいたします。
お客様によっては、「仕事をしながら勉強しているため職場でヘッドフォンをつけるのに抵抗がある」、「知っている内容も多い領域だと、文章は読み飛ばせるけれど音声はずっと聞いていなければならない」、「自分のペースで受講したい」といった声をお聞きするケースもあります。このようなケースでは、音声なしでも理解できるように、ポイントとなる箇所に「インフォステップ」と呼ばれる解説画面を入れるなどの工夫により、分かりやすい教材を提供させていただいております。
音声のオプション以外にも、教材の画面構成からオーダーメイドで承ります。サンプル教材によるトライアルなどを通して、お客様に最適な教材となるよう一緒に考え、アフターフォローも行っていきます。
eラーニング活用事例
それでは、実際にどのようにeラーニングが活用されているか、事例をご紹介いたします。
【事例1】経済産業省委託 産学人材育成パートナーシップ等プログラム開発・実証事業 東洋大学「バーチャル生産ラインシミュレータ」
弊社では、モノづくり現場出身者の経験を次世代の社員に伝承するため、社員向けに「モノづくり講座」を毎年開催しています。製品開発の企画→造形→設計→解析→試作→実験→生産までの一連の業務と、現場におけるIT技術の活用を短期間で習得できる講座内容となっています。
東洋大学様向けには、大学の授業での学問がモノづくり現場においてどう生かされるのか、IT技術と人の技術はどう関わっていくのか、また環境問題といったところにも踏み込み、より実践に近い内容を学生にも広く知ってもらうことを目的として、経済産業省の支援の元、弊社の社員向け講座をブラッシュアップした教材をご提供しています。

造形、設計、解析、生産・・・と多岐にわたる一連のIT技術を、製品開発の流れに沿って体験してもらう講座ということで、通常であれば教育に必要なCAD/CAM/CAEソフトウェアを導入するというハードルがあります。そういった問題に対して、弊社が提供するeラーニングに搭載される「ガイドモード」の機能を活用すれば、ソフトウェアを導入しなくとも、Internet Explorerのブラウザ一つで実際のCAD/CAM/CAEのソフトを使用している感覚で疑似操作体験が可能です。弊社では、集合教育の中で、eラーニング教材を「実習用ツール」として活用する新しい学習スタイルをご提供させていただきました。
講義を受講した学生からは、「普通の授業では絶対に体験できない内容であった」「実際のソフトの画面を見ながら操作の体験ができたので、開発に関してとても興味が沸いた」といったコメントを多くいただいており、毎年多くの学生が受講を希望する人気の高い講座となっています。
【事例2】大手企業A社様での活用方法
A社様では、納期短縮の要請や開発機種の増加など、市場ニーズを背景とした業務量の増加とともに設計者も増加し、それに伴い3次元CADの利用が加速しました。その一方で、CADデータには生産側で望むような安定した品質が必ずしも得られないといった人依存による品質のばらつきがあり、「スキルに個人差がある」、「個人スキルが見える化されていないため、業務にあったスキルアサインができない」といった課題が開発業務の負荷へと繋がっていました。そこで、これらの課題を分析し、設計者が必要とする知識を体系化すると同時に、eラーニング化することによって社内への普及促進を図りました。
eラーニング採用の理由として、いままでの教育では柔軟性に欠けるところがあり、実務レベルとして一番活躍して欲しい人材の時間が取られてしまうのが課題でした。そこで、いつでもどこでも自分のペースで受けられる『eラーニング』を活用することになりました。
コンテンツの内容としては、3次元CADの操作方法に限らず、データ作成におけるルールまで含めて教材化されています。また、設計者が必要とする最低限の生産知識や製図知識、業務ルールに関する分野も幅広くコンテンツ化し、最終的に教材が理解できたかどうかをはかる「理解度テスト」も同時に作成しています。テストは各レベルに合わせ、業務の合間に気軽に取り組めるボリュームで、多忙な設計者にも無理なく受講できるものになっています。このテストを実施することにより、設計者スキルの定量評価が可能となり、各設計者のスキルの差、強み弱みを的確に把握することができました。
なお、現在もeラーニングとテストのトライアルによる評価が実施されており、設計者スキルの底上げ、更なるスキルアップを促進しています。またeラーニングとテストの内容に関しては、受講済みの設計者からのフィードバックも取り入れながら継続的にブラッシュアップされており、今後は関連部署にも順次普及させていく計画とのことです。
最後に
製造業におけるグローバル展開が加速する中で、それに伴う教育は、拠点・言語などの問題により、国内における教育以上に難しくなってきています。弊社のeラーニングツールは日本語だけではなく、英語・中国語・韓国語など15ヶ国以上の言語にも対応することができます。日本語版のeラーニング教材を1つ準備しておくことにより、その教材を翻訳するだけで、どの拠点でも同水準の教育を受講することが可能となります。
弊社ではモノづくりの豊富な知識に加え、製造業におけるeラーニング適用の経験を活かし、お客様に最適な教育方法をご提案させていただきます。
モノづくり教育に関するお悩みがございましたら、DIPROへのご相談をお待ちしております。
(第一・第二エンジニアリングサービス部 高野、菅原)
PICK UP












