DIPROニュース
新しい年を迎えて
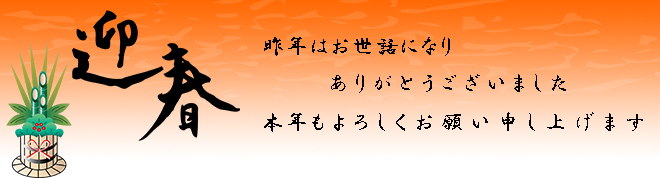

明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になりました。本年も引き続きお引き立ていただきますようお願い申し上げます。
さて、約二年前の政権交代以降、所謂『アベノミクス』と呼ばれる経済政策により、経済環境も大きく変わってきました。当時12月5日の為替レートは1ドル=82.01円、日経平均株価は9,380円37銭であったものが、昨年同日には7年4カ月ぶりに1ドル120円を突破、8日には終値121.42円、日経平均株価17,935円64銭まで進んだため、この間実に、約48%の円安、約91%の株高と、極めて大きな環境変化が起こったと言えます。直近では予想外のGDPマイナス成長、そして増税延期と解散総選挙、日本国債の格付けダウン等、更なる変化をイメージさせる出来事も起こっています。
一方この間、実体経済が明らかに力強く歩み始めたかと言えば、決してそうとは言い切れず、逆に以前の様に円が安くなれば価格競争力が増し、輸出産業が牽引車となって経済も成長するといった単純な構造では無くなっていることも明らかになってきました。
ここで見方を変えて、輸出の増加や、海外に移転した仕事が国内に戻り生産を初めとする仕事量が増大したらどうなるかを考えて見ます。そこで気になるのは、そうした活動の担い手が十分に確保できるのだろうかという問題です。少子高齢化そして人口減少は日本にとって大変大きな問題であるとは認識されていますが、文部科学省のまとめた18歳人口の推移をみると、平成27年度は120万人であり、25年前、ちょうど団塊ジュニアが18歳となった頃の平成3年度204万人からみると40%強も減少しているのに、今更ながらに驚かされます。そして、平成20年度に130万人を割込んで以降、この先見通せる限りその数が増加する事はありません。
また、近年では工学部の学生が好んで金融等の製造業以外の進路をとるといった傾向も有り、製造業にとっては質量ともに、労働の担い手不足という問題に直面しています。この傾向は数年前から数字の面では現れていたものの、リーマンショックや震災といった外乱により企業の採用意欲も弱かったために目立つ事はありませんでした。しかし、昨年あたりから景気が上向き加減となり、採用の現場を中心に急に顕在化して来たように思います。マーケットの縮小という観点もさることながら、今後国内製造業にとっては、その現場を支える若手・中堅層の不足は今後の深刻な制約条件になると思われます。
これに対し、近年言われているように女性、外国人そしてシニアの活用拡大といった施策も今後一層重要度を増していくと考えられます。同時に、労働力の流動性の高まりや非正規雇用の増大等の中で、若干忘れられていた感も有る『企業は人なり』『企業人を育てる』という視点を再度強く意識し仕事をしていく事が極めて大切である様に思います。ここ1~2年『ブラック企業』という言葉が取り上げられましたが、今後、労働条件や企業風土が社員にとって受け入れられるか否かが企業の競争力あるいは存続要件に即つながっていく事を肝に銘じておく必要が有ると思います。
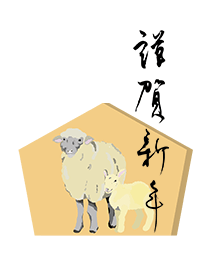
さらに、人を惹きつけ、力を結集して行く為には、大きな目標を据え、製造業であれば、ブレることなく新たな技術のフロンティアを追求していく、それを実現する為に愚直に足元のQCD向上に努めて行く姿勢を持ち続けていく事が何より大切だと思います。
今年は未年(みどし、ひつじ年)、『未』という字は元来植物の実や生い茂る様子であり、羊というのは後から付けられた意味との事ですが、『羊』は群れで生活し、そのおとなしい外観からも、平和や家族安泰といった意味に例えられます。前段で触れたように外部環境の変化は今年も続く様に思え、企業もその荒波に晒されていく事になります。しかし、そこで働く個々人にとっては、厳しい状況の中でもやりがいのある仕事ができる一年にしていければと願っています。
重ねまして、本年もお引き立てのほど、よろしくお願いいたします。
PICK UP












