DIPROニュース
オートモーティブデジタルプロセスセミナー
2016のご報告

11月25日(金)、パシフィコ横浜において「オートモーティブデジタルプロセスセミナー2016」を開催いたしました。ご来場の皆様ならびにご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
世界の自動車産業では、自動運転に代表される車の知能化に向けた開発競争が激化し、製造業全般においては生産革新に向けた取り組みが加速化されています。これらは、いずれも最先端のICTを活用した高い目標に向かう挑戦となっています。そこでは自動車会社とICT 企業の連合や競争等、従来の産業構造からは考えられなかった形態での技術開発競争が繰り広げられており、そうした活動を支える開発プロセスやエンジニアリングIT、またICTインフラも変革を迫られています。

こうした大きな流れを受け、今年は生産革新における取組事例をご紹介いただくことを軸として、挑戦すべき新たなテーマや方向性についてご講演いただき、また国内主要自動車メーカーのIT及び技術情報管理のキーマンの皆様にパネリストとして熱く語り合っていただきました。
基調講演:モビリティとロボット技術が創る新しいライフスタイル
千葉工業大学
未来ロボット技術研究センター所長 古田 貴之 様

「何をお話しするか実は細かく決めていません、会場のお客様の顔を拝見しながら話す内容を決めていきます」と、独特のお話しぶりで、592枚の資料のページを移動させながら、講演をスタートされました。
古田様が所長を務める千葉工業大学未来ロボット技術研究センター(fuRo: Future Robotics Technology Center)は、福島第一原発事故では、唯一、原発建屋全フロア踏破可能な災害対応ロボットを開発・提供し、政府の福島原発冷温停止ミッションを遂行・成功させました。お客様と共同開発した「ILY-A(アイリーエー)」というパーソナルモビリティは、時と場所に応じて四つに変形し、使う人によって役割を変える三輪車型のロボットで、2015年度グッドデザイン賞を受賞しています。
どんなに良いものを作ったとしても、それだけでは世の中は変わらないし未来は創れません。新しい技術を世の中に出していく際には、どういう未来を描いてどういう社会の営みを作り出したいのかという「ものごとづくり」の視点が重要です。そして「ものごとづくり」で少子高齢化社会を解決したい、と力強く言われています。高齢者が快活に活動し、文化活動や経済活動をけん引する社会、そんな社会を実現するために、あらゆる世代の活動範囲を広げ、シーンを選ばず、誰もが欲しくなる乗り物の一つとして「ILY-A」を開発されたそうです。さらには、つくるだけでは意味がないということで、東京オリンピックに向けた内閣府・首相官邸プロジェクト「改革2020」では、こうした技術が実際に活躍する未来都市エリアを作る計画とのことです。
1時間という限られた時間の中で、膨大な資料を前に後ろにとスライドさせながら、本当に様々な興味深いお話をいただきました。残り少ない時間となったところで、「1号機と2号機」というタイトルの古田様の愛娘のスライドで手を止め、子供たちが大人になったとき、日本の基幹産業である自動車をはじめとする産業界が元気で豊かな社会であってほしい、そのためにも、日本にしかできない技術、サービスを埋め込んだ「オンリーワン」をどんどん開発していくことこそご自身の命題である、と熱く語られました。
自動車産業は素敵な未来を実現するための要です、機会があればぜひロボット技術と「私」を使っていただき、子供たちのための素敵な未来を一緒につくりましょう、とのお言葉で講演を締めくくられました。
講演:マツダのブランド戦略とモノ造り革新について
マツダ株式会社
取締役専務執行役員 品質・ブランド推進・生産・物流統括 菖蒲田 清孝 様

2020年に創立100周年を迎えられるマツダ様は、創立以来「モノ造りで世界に貢献する」という精神に立脚して事業を拡大してこられました。2001年、幼少期に感じた”動くことへの感動”を提供し続けたいというブランドメッセージ“Zoom-Zoom”(日本語の擬音語ブーブー)を打ち出し、2007年、 すべてのお客様に走る歓びと優れた環境安全性能を提供するという「サステイナブルZoom-Zoom宣言」を発表し、同時にゼロからの理想的なクルマを目指した「SKYACTIV TECHNOLOGY」を確立されてきました。
並行して「モノ造り革新」をスタートさせました。「多様性」「共通性」の相反する特性を生かしたモノ造りを実現するためのブレークスルーとして「一括企画」「コモンアーキテクチャー構想」「フレキシブル生産構想」の3つの考え方を軸に、自動車製造を取り巻く環境から見た様々な課題に取り組まれました。例えばデザイン意匠を再現するために、「魂動」というテーマの下、デザイナーの想いを製造にかかわる全エンジニアと共有し、徹底的にこだわったモノ造りに取り組まれました。
今後は、より海外生産機能を強化していくために、MBDを活用した量産準備プロセスの構築、データ活用領域を拡大したモノ造りを目指されています。そしてそれを実現するために大切なのは人、と断言されます。生技エンジニアにも開発を経験させるなどの経験を通して、強固な基盤を持った「骨太エンジニア」の育成を図られています。
「私の好きなビデオ」と、工場の皆さんが制作された、量産立ち上げ時の社内セレモニーで流した動画をご紹介くださいました。社内外業種問わずクルマ造りに携わった様々な人たちの熱い思い。胸が熱くなるのと同時に、これこそがSKYACTIVE TECHNOLOGYを揺るぎないものにしたのだと確信いたしました。
講演:日産自動車のモノ造り革新
日産自動車株式会社
理事RSVP(生産事業 日本 アセアン&オセアニア) 松本 昌一 様

自動車生産のグローバル化が進む中、日本拠点は一層の競争力強化へ向けて“モノ造りの革新”を進め、それをグローバルに展開していく役割を担っています。各生産現場では、「APW(Alliance Production Way)に立脚した同期生産を基本に置きながら、ITやビッグデータを活用し、現場管理の強化や品質管理のレベル向上に務められています。
モノ造りの革新を支える柱の一つは現場管理です。Web カメラやプロジェクションマッピング等の映像技術を活用し、作業手順から設備監視までの全工程を見える化する取り組みを進められています。
OEE(総合設備効率)の向上も重要です。センサを活用したモニタリングにより設備故障の兆候を掴み、従来のTBM(Time-Based Management)から予防・予知的に対処するCBM(Condition- Based Maintenance)にシフトしています。
品質の同期という考え方も取り入れ、塗装や車体の工程で、品質のバラツキをコントロールする要因系管理の強化や、電気自動車リーフのトレサビリティ活用についてご説明いただきました。
冒頭に「今日は泥臭い話もご紹介します」と講演を始められましたが、2次キズ発生の真の要因をWebカメラを活用して解決するといった、まさに現場でどういったことが起こっているかについて様々な動画を引用しながら丁寧にご紹介くださり、日産自動車様のきめ細かな取り組みを知ることができた大変貴重な講演でした。
パネルディスカッション
これからのEITに求められるもの~道具の使いこなしに向けて~
- トヨタ自動車株式会社
- エンジニアリングIT部 部長 細川 昌宏 様
- 日産自動車株式会社
- グローバル情報システム本部 エンジニアリングシステム部 主管 松木 幹雄 様
- 株式会社本田技術研究所
- 四輪R&Dセンター デジタル開発推進室 室長 田中 秀幸 様
- マツダ株式会社
- ITソリューション本部 エンジニアリングシステム部 部長 細川 大 様
- 三菱自動車工業株式会社
- グローバルIT本部 エンジニアリングIT部 部長 和田 賢二 様
- スズキ株式会社
- IT本部 デジタルエンジニアリング部 部長 市原 誠 様

トヨタ自動車㈱ 細川 昌宏 様

日産自動車㈱ 松木 幹雄 様

㈱本田技術研究所 田中 秀幸 様

マツダ㈱ 細川 大 様

三菱自動車工業㈱ 和田 賢二 様

スズキ㈱ 市原 誠 様

司会 吉野 琢也

パネルディスカッション
1980年代以降、3Dデータの活用による製品開発の効率化と期間短縮を目指した取り組みが進められ、ITの浸透に伴い急増した情報を活用するための管理システム(BOM/PDM)の構築が加速しました。これらと並行して、年を追うごとに市場要求の変化、ものづくりの場の変化、情報活用の高度化、さらにはエンジニアの枯渇問題等々、EITを取り巻く課題は増え続け、幾つかの施策によるトレードオフにも悩まされるようになってきました。この折り合いをどうつけていくのかが、各社の悩みともなっています。
ディスカッションに先立ち、各社様から組織の紹介、課題と取り組みの状況について、ご紹介をいただきました。
続いて、テーマ別ディスカッションが行われましたが、ここでは、注目したい課題に対する仮説を司会が提示し、それに対してパネリストがこれまでの取り組みに照らし合わせ、賛成/反対、あるいは話せるかどうかを手元の◯☓のプラカードで意思表示いただく、という進行でディスカッションが進められました。
「ユーザ/業務部門抜きでは成立しない。PLMツール利活用の作業分担はどうあるべきか」という最初のテーマに対して、「『ITを駆使した未来のクルマ作りを思い描き、ビジョンと技術戦略を提示し、方策を定義すること』がEITの役目である」という仮説を提示しました。即座に◯、☓を上げられる方もいれば、◯☓を交互に示し、両方の回答を表される方もいました。様々なご意見を伺う中で各社様に共通しているのは、EITはシステム間、部門間をつなぐ役割を担っており、そのためにも幅広い視点が必要ということがありましたが、中にはジョブローテーションといった人事的施策を合わせ取り組まれている、といったご意見もありました。
次に、「メカ・エレキ+ソフトの時代。ソフト管理と仕事の改革はどう進めていくべきか」というテーマに対しては、司会からソフトウェア管理システムのイメージ図を表示したうえで、「今後はこれら管理システムとデリバリー/リプロ(販売後のソフトウェア更新)の仕掛けが必須となる」という仮説を提示しました。これについては、「今後、膨大な情報をクルマに乗せていく時代にリプロは必須、そうした情報を扱っていく設計者の負担を軽減するためEITが開発の初期段階から関与していくべき」、「デジタルとフィジカルの一体化による開発をITでどう実現するか、また部品のライフサイクル管理の仕組みの必要性」といったコネクテッドカー時代に向けたご意見、取組みをご説明いただきました。各社様の取り組みは、あるべき姿に向けて未だ進行中だということが理解できましたし、EITの重要性の再認識ができた時間でもありました。
用意していたテーマすべてを議論し終わらないうちに、所定の80分があっという間に過ぎてしまいました。パネリストの皆様はもとより会場の皆様も、「まだまだ話し足りない」「聞き足りない」という雰囲気の中、ご登壇いただいたパネリスト皆様への惜しみない拍手をもってパネルディスカッションが終了いたしました。
全体を通して
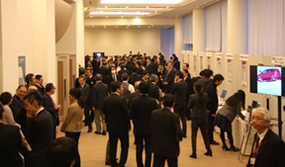
今回のオートモーティブセミナーは、おかげ様で例年にも増して盛況となりました。講演会場の外側通路では弊社製品やソリューションのデモ展示が行われ、講演合間の休憩時間にはお客様から熱心なご質問やご相談が寄せられました。
セミナー終了後に行われた懇親会も多くのお客様にご参加いただき、会場全体が溢れんばかりの賑わいとなりました。講演者、パネリストの皆様の周りはもとより、あちらこちらで既知・初対面を問わず談笑したり名刺交換したりする姿が見られ、まさに異業種交流の場ともいうべき様相を呈しておりました。
アンケートやご要望でいただいた、”とても参考になった、また来年もやって欲しい”という声や運営に関する様々なご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。なお、お客様の業務に関するお悩みにつきましては、弊社の営業やシステムエンジニアが詳細をお伺いし、問題解決に向けた建設的なご提案をさせていただきたいと考えております。
私どもDIPROは、これからも、社員全員が一丸となってお客様に寄り添いながら問題解決へ向けて歩んでまいります。今後ともご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
PICK UP












