DIPROニュース
オートモーティブデジタルプロセスセミナー2019のご報告


11月29日(金)、パシフィコ横浜において「オートモーティブデジタルプロセスセミナー2019」を開催いたしました。ご来場の皆様ならびにご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
昨今、デジタル化の急速な進展が、あらゆる産業に劇的な環境変化をもたらす中で、製造業のデジタルトランスフォーメーションの重要性も日々高まっていると感じています。自動車業界では、コネクテッド・自動運転等の頭文字をとったCASEや、移動手段のサービス化を表すMaaSといった分野での次世代技術開発が加速しています。そして、この動きは、人を取り巻くモビリティ社会の変革を推し進めると言われています。
一方で、自動車の既存技術や、従来型の部品の開発においては、更なる効率化、コスト削減の必要性に迫られていると伺っています。これに加えて、エキスパートの方々の高齢化や、少子化による労働力不足が深刻な問題となりつつあり、生産革新の必要性も日々増している様に思います。こうした次世代技術開発と生産革新の動きに呼応して、オープンイノベーションやアライアンスの報道も多く目にするようになりました。今後、企業連携による共創・Co-Creationと、グループ企業間でのグローバルな技術開発競争・Competitionの動きは、更に加速していくように感じます。そして、この動きは、今後5年から10年程度の間に産業構造に留まらず社会基盤や生活様式にも大きな変革をもたらす可能性が有ると思われます。
このような環境の中で、自動車メーカー様やサプライヤー様も、多くの変革への取り組みを進められていると存じます。それらの取組において、製品開発プロセスやPLMといった領域も、そのニーズやソリューションといった観点で大きく変容していくと思います。
プロセス革新をご支援させて頂いている私共にとっても、質的変化が求められていると考えています。今後も、弊社の4つのコア機能、パッケージビジネス、ソフト開発、エンジニアリングソリューション、コンテンツサービスを融合したトータルソリューションに磨きをかけ、お客さまのニーズにお応えしていきたいと思います。
こうした状況を踏まえ、今回のセミナーは、『ITが導く人とクルマの現在から未来へ』というテーマで構成いたしました。この分野の有識者、自動車業界の企業様を講師にお迎えして、最新の取り組みをご講演いただき、また、国内主要自動車メーカーのエンジニアリングITキーマンの方々にパネリストとして、日本の車づくりがどうあるべきかについて熱く語り合っていただきました。
次項より、DIPRO編集局にて各講師の講演概要およびパネルディスカッションの概要をまとめました。
基調講演:「5Gネットワークが作る自動運転技術とサービス」
慶應義塾大学教授
慶應義塾先端科学技術研究センター所長
工学博士 山中 直明 様

まもなく商用サービスが開始される5G(第5世代移動通信システム)が自動運転車や今後のネットワークコミュニティに与える影響、そこで飛び交う莫大なデータの活用方法、新たなビジネスの方向性についてご講演いただきました。
5Gは携帯電話のサービス向上を狙ったものではなく、自動運転、農業など、様々な産業における効率化に寄与するコンセプトであることから、来年のオリンピックを機として多くの先行導入ができる現在にあって、5G環境をそれぞれの分野でどのように利用していくかが課題となります。
S&CC(Smart and Connected Community:全てのものがスマートにつながるネットワーク社会)では、自動運転車はIoT装置の一つであり、また単独で存在するものではなくネットワーク社会の一部と捉えることが重要です。また、人と人が影響しあい、学習し、成長していくように、IoT装置同士も影響しあい、学習し、成長していく中で莫大なダイナミックビッグデータが生まれます。この増大していくデータを収集し、工夫し、活用しながら安全な社会を効率よくつくり出していくことが重要であるとご説明いただきました。
最後に、5Gを使ったM2M(Machine to Machine)データトレードで実現されるであろう、よりダイナミックなカーナビサービスや、効率的なピザ配達などの新ビジネスの可能性などのご紹介を通じて、自動運転技術にオープンイノベーション(データサイエンス、経済、法律など)の視点を入れることで成功する技術になる、是非ダイナミックビッグデータを使いこなすようなビジネスをお考えいただきたい、と会場のお客様に投げかけられ、講演を締めくくられました。
講演:「Hondaの新サービス・商品開発におけるデジタルイノベーション」
株式会社本田技術研究所 常務取締役
デジタルソリューションセンター担当
オートモービルセンター デジタル情報技術担当
伊藤 裕直 様

ホンダ様は、4輪、2輪、汎用機、航空機などのパワープロダクツを手掛ける世界最大のエンジン付き機器販売会社という社会的責任、影響力の大きさを踏まえてお話をいただきました。まず、多様な顧客ニーズの対応に向けた新サービスについては、電動モビリティサービス「MaaS」とエネルギーサービス「EaaS」をつなぐ「Honda eMaaS」のコンセプトをご説明いただきました。このコンセプト実現のため、リソースアグリゲート(電力の制御・管理)企業への出資やモバイルパワーパックの開発、また、モビリティサービス企業や蓄電池企業などと協業を拡大しながら開発を進められていることもご説明いただきました。先進のAIを用いたコネクテッド技術「Honda Personal Assistant」についても動画を用いて分かりやすくお話しいただき、ホンダ様が目指す移動と暮らしの近い未来像を感じとることができました。
「ホンダeMaaS」実現の為のデジタル技術活用事例として、①要求分析/MBSEの適用、②ALMの導入、③性能設計プロセスの最適化、④データ標準化の4つについてご説明いただきました。
MBSEやALMなど、コネクテッド化を進める上で必要不可欠な環境を整備し、ガバナンスを強化しながら、社内のみならずサプライチェーン全体でデジタル技術活用の効果を上げていくことを目指されています。取り組み事例として、MBSE人材の育成やPLMによる性能設計管理基盤の構築、さらにはサプライヤ連携をより良くするためのデータ標準化の取り組みなどについてご説明されました。
最後に、モビリティとエネルギーの連携にAIデータ分析も活用し、モビリティ・エネルギーの循環型エコシステムを形成し、社会変革に貢献したいとの熱い思いを語られました。
講演:「デンソーグループのFuture Mobilityへの取り組み」
株式会社デンソー 技術開発センター Global R&D Tokyo 執行職
株式会社J-QuAD DYNAMICS 代表取締役社長
隈部 肇 様

自動車業界は電動化、自動運転、コネクテッドといった分野で100年に一度といわれる大変革期を迎え、デンソーグループは必要な技術開発を加速しています。本講演では、自動運転分野に関わるセンシング技術の開発状況、および車両統合制御システムウェアの開発を加速するため、アイシン精機、アドヴィックス、ジェイテクト、デンソーの4社で今年4月に設立した新会社J-QuAD DYNAMICSの概要と取り組みを、同社代表取締役社長の隈部様よりご紹介いただきました。社名の「J-QuAD DYNAMICS」には、日本生まれ(J)の自動車部品4社が、品質(Quality)の高い、自動運転(AD)と車両運動制御(VD:Vehicle Dynamics)のための統合制御ソフト開発によって、安心・安全なモビリティ社会実現の原動力(Dynamics)になる、という想いが込められているとのことです。
これまで、クルマの「走る・曲がる・止まる」に関わるセンサーやステアリング、ブレーキを制御するソフトは、それぞれのコンポーネント会社毎で開発され、コンポーネントをまたぐ統合制御は国内外の各自動車メーカー依存となっていました。これからは、J-QuAD DYNAMICSが、親会社4社と連携して一体感を持った統合ECUソフト開発を加速することで、重複解消やソフト標準化で競争力を強化し、自動運転普及に貢献していきたい。そうすることで未来のモビリティ社会の創造に貢献し、誰もが安心・安全に移動できる自動運転の実現につながっていく、とご説明いただきました。
最後に、今後の統合ECU制御ソフト開発に向けたロードマップのお話をされ、新会社と設立した4社だけでなく、自動車業界・IT業界、通信業界など幅広い業界と連携し、安心安全な社会の創造に向けた取り組みを推進、自動運転普及を実現していきたいという強い意志を語られ、講演を締めくくられました。
パネルディスカッション「DX時代 All Japanの車づくり」
パネリスト
- トヨタ自動車株式会社
第1エンジニアリング情報部長 細川 昌宏 様 - 日産自動車株式会社
デジタルモノづくり本部 エンジニアリングシステム部 主管 松木 幹雄 様 - 株式会社本田技術研究所
デジタルソリューションセンター エンジニアリングソリューション統括室 室長 田中 秀幸 様 - マツダ株式会社
ITソリューション本部 エンジニアリングシステム部 部長 細川 大 様 - 三菱自動車工業株式会社
グローバルIT本部 エンジニアリングIT 部長 津田 孝博 様 - スズキ株式会社
IT本部 デジタルエンジニアリング部長 市原 誠 様

トヨタ自動車㈱ 細川 昌宏 様

日産自動車㈱ 松木 幹雄 様

㈱本田技術研究所 田中 秀幸 様

マツダ㈱ 細川 大 様

三菱自動車工業㈱ 津田 孝博 様

スズキ㈱ 市原 誠 様

司会 吉野 琢也

パネルディスカッション
今回は「100年に一度の変革期」と言われるように、近年複雑化してきている問題や日々変化する状況に対し日本の車づくりがどう対応していくべきか、という点についてディスカッションを行いました。
最初に司会より、昨今の時代・環境変化、世界市場の動向について説明し、それを受けてパネリストの方々とは、世界市場については、これまで取り組んできた欧州や米国を意識した車づくりから、近年動きが活発になっている中国やインドといった新興勢力に注目が移ってきており、日本としても新興勢力の動きを意識、理解していかなければならないという共通認識から、ディスカッションがスタートしました。
今回は、本パネルディスカッションに向け実施したパネリストの方々との中国への動向視察の結果を交えながら、以下の4つのテーマについて各社のお考えをご紹介いただきました。
まず一つ目のテーマ「基幹システムに対する考え方」については、視察に行かれた中国の新興OEMを例にあげ、インフラはクラウドを採用、PLMやERPなどの基幹システムは汎用パッケージを導入し、ユーザーインターフェースに力を入れているといった状況に対して、日本OEMは各社様ともレガシーシステムがあり、それらとMBSEやIoTなど新しい要件をどう組み込んでいくかが課題であるとの話題になりました。
二つ目のテーマ「ソフトウェア管理・開発の課題」については、中国企業でのクラウドシステムや車載システムと連携した自動運転の実現に向けた取り組み例を交えお話いただきました。各社様としては、これまでのメカ設計の技術が活かしにくく、ソフトウェア開発の人材増員やシステムサプライヤとの連携強化などを行い、継続して取り組んでいく必要があるとのお話に至りました。
三つ目のテーマ「社内のみでなくお客様を意識したIoT化」については、市場・開発・工場の3つの視点で考え、市場の声を開発で活かすという段階にはあるが、工場との連携には達していないとの意見が多く、今後、この3点を連携させより良い環境を構築していくべきとの結論に至りました。
最後のテーマは、今回の中国視察から新たに課題認識された「プラットフォーマーに対する考え方」についてです。中国を例に、クルマやユーザーの移動を含めた一連の行動情報を取得し、さらなるサービスに繋げる活動や、中国では車の利用管理(MaaS)やクラウドサービスまで整備されており、日本でもOEM、サプライヤ、IoT企業など業界全体でデジタル化の底上げに取り組んでいく必要があるとのお話を頂きました。
最後には司会より、この3年間同様のテーマでディスカッションいただき、聴講いただいたお客様にとって有益な情報となっていれば幸いです、との謝辞と、今回卒業となるパネリストの方々のご挨拶で締めくくられました。
全体を通して
今回のセミナーは、例年にも増して多くのお客様にお越しいただき、大変盛況となりました。講演の合間の休憩時間には、弊社製品やソリューションのデモ展示を行い、お客様から熱心なご質問、ご相談が寄せられました。また、セミナー終了後の懇親会にも多くのお客様にご参会いただき、会場全体が溢れんばかりの賑わいとなりました。
アンケートでいただきました“大変参考になった”という声や、運営に関する様々なご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。なお、お客様の業務に関する様々な悩みにつきましては、弊社営業やシステムエンジニアが詳細をお伺いし、問題解決に向けた建設的なご提案をさせていただきたいと考えております。
これからもDIPROは、社員全員が一丸となって、お客様に寄り添いながら問題解決へ向けて進んでまいります。今後ともご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
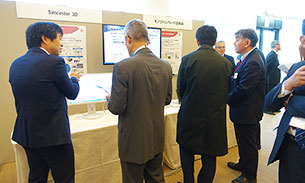



PICK UP












