DIPROニュース
先手が得か後手が得か
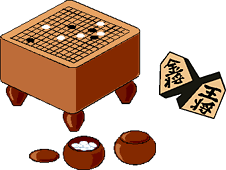
以前は下手の横好きで少し碁をやりましたが、最近は時々暇なときにテレビで対局を見るくらいです。大きな棋戦で日本人棋士の活躍が年々少なくなっていくのが寂しい気がしています。囲碁の起源は四千年ぐらい前の中国と言われていますが、19路盤上で白黒2種の石だけを使いこれだけ奥の深いゲームを考え出したことにつくづく感心します。
ところで、囲碁は取った地の多さで争うため、どうしても先手が有利になります。そのため先手にハンディ(コミ)をつけざるを得ず、日本では5目半のコミ出しが一般的でした。しかしこうすれば先手後手で公平、つまり勝率が同じになっているかというと実はそうではなく、統計学で著名な麗澤大学の宮川公男教授によれば、過去5年間の公式戦1万4000局を日本棋院で調べた結果では、黒番の勝率が51.9%(7266勝)だったそうです。素人から見ればこれでほぼ互角と考えそうですが、統計学的には5目半のハンディは妥当ではなく、この勝率からは(標準偏差や正規分布の考えからすると)明らかに黒番有利と結論されるとのことです。確かに新聞で見る最近の対局譜は6目半になっています。半世紀続いた5目半のコミが実は公平でなかったということで、日本棋院では2002年10月からルールを6目半に変えたということです。それから3年近く経った現在、どんな勝率になっているか、結果は知りませんがちょっと興味があるところです。
囲碁と並ぶ代表的なゲームである将棋の場合はどうなっているのでしょうか。これも過去の勝率を調べてみると面白そうに思います。皆さんは先手・後手のどちらがお好きでしょうか。先手・後手を自由に選べる場合、統計学に従って選択するより自分の得手、不得手で選んだほうが勝つ確率が高いように感じますがいかがでしょうか。
先手必勝という言葉は一般的にはよく使われますが、一方で先手必敗という言葉はあまり耳にしません。ところが世の中は必ずしも先手必勝というほど単純ではないようです。二人競輪や、かたまって走るときのマラソンなどでは、先頭に立つと風圧を受け不利になるのはよく知られていますが、ITの世界でも後手有利、つまり先手必敗の掟があるといわれています。確かに試行錯誤や不具合解消は他社に任せ、安定したら参入するほうが得なケースが多くあります。そのため多くの産業で余裕のある大手企業がしばしば取る戦略ともなっています。
しかしもう少し長期的に見た場合、現実には先手必勝とか、先手必敗とかの単純な理論には納まらない様々なケースが起きています。特にデジタルな世界ではソフト開発に多大なコストがかかっても生産にはコストがかからない、いわゆる限界費用が殆どゼロのため『収穫逓増の法則』といわれるような、経済学的にあるいは自由競争の視点からはあまり面白くない現象が起こりがちとなります。
ご承知の方も多いと思いますが、マーケティングの世界では新しい製品やサービス、とりわけハイテク製品が生まれ普及していく過程は次の5つの段階があるといわれます。
- Innovators(テクノロジ熱狂者)
- Early Adopters(空想家、初物好き)
- Early Majority(実用主義者)
- Late Majority(保守主義者)
- Laggards(懐疑論者)
このマーケティング論のなかに、有名な『キャズム(深い溝)』といわれる言葉があります。『キャズム』は、Early AdoptersとEarly Majorityの間にあり、自社だけではどうにもならない、市場の確立を待つ期間が存在するという意味で使われます。 新製品を出す時、それがどの段階にあたっているのかを見極める事が重要ですが、仮にキャズム理論が正しいと仮定すると、たまたま発売する新製品が斬新すぎ、キャズムの前の段階での製品化であった場合いくら頑張ってもそんなには売れず、本格的な需要はある一定期間置いた後でないと生まれないということになってしまいます。
デジタル産業での技術革新はとりわけ早く、すでにEarly MajorityやLate Majorityの段階に入りつつある製品(液晶、プラズマ、DVDなど)のシェア争いは激烈で、めまぐるしい首位交替や順位変動が起きているとのことです。日経新聞による2004年「主要商品・サービスの世界シェア調査」の結果では、デジタル機器・関連部品で、14品目中2品目で首位交替、12品目では2-5位で入れ替わりが起こり、韓国や台湾メーカーが躍進し、日本勢のシェアの後退が目立ったとありました。
弊社も常々先進的で付加価値の高い商品やサービスを永続的にご提供していきたいと考えています。そのためには先手必勝とか先手必敗といった単純な見方ではなく、お客様の産業がデジタル化推進について全体として5つの過程のどの段階に位置づけられるのか、あるいはお客様がその産業の中にあってどの段階でのご購入を希望されているのかをよく理解したうえで最適な商品やサービスをご提供していくことが、とても大切なことと思います。
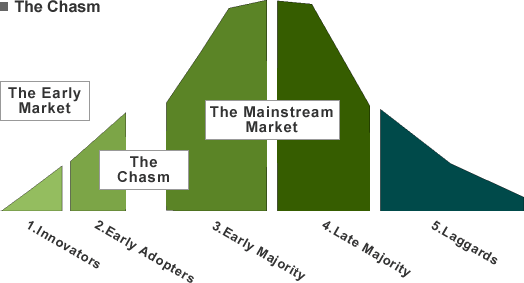
(代表取締役社長 間瀬 俊明)
PICK UP












