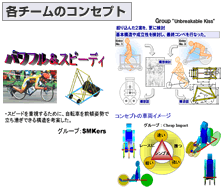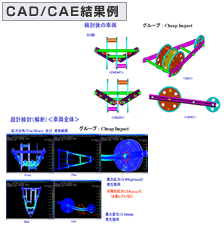DIPROニュース
新発想の"ものづくり研修" 「DIPRO Paper Bicycle Project」
"もの"を持たない会社で"ものづくり"を体験する

弊社では、"結果責任をとる"をスローガンにお客様に役立つITを提供するべく、新しい専門技術修得に各社員が挑戦しています。
このプロジェクトは、紙を材料として人が乗って走れる自転車を、3名編成のチームで、自分達でコンセプトを立案して、設計から製作を行い、実際に競技会でスピードや耐久性を競うものです。単に作って走るだけでなく、設計や製作の過程や内容も評価の対象となります。
CAD/CAM/CAEやPDM・BOMなどのシステム開発や各種技術サービスにおける弊社の強みは単なるITツールや技術の提供ではなく、ものづくりの現場を熟知し実際の業務に役立つITツールや技術の提供にある。またそうありたいと考えています。
そこで「ものづくり」を体験し、お客様とものづくりの「共感力」を高めると共に、問題発見・解決能力や創成能力の育成を目的に「DIPRO Paper Bicycle Project」を、昨年10月から本年1月にかけて実施しました。
米日の大学の研修コースを導入

プレゼンの様子
今回は初めての取り組みでもあり、スタンフォード大学でPBL(Problem Based Learning)として創始されたPaper Bicycle Projectを参考に2000年度から教育に取り入れている広島大学の全面的なご協力を戴きながら、実務リーダーの課長SE層が率先して参加し、一般層への展開に当たっての問題点の洗い出しも行ないました。
最初のフェーズは、決められた設計条件を満たし、自分達の想いをコンセプトとして立案します。そしてコンセプトと構造設計のプレゼンテーションを通して、改良点を解決しながら自転車を具現化していきます。
構造設計段階では、CADやCAEなどのITツールを駆使して構造レイアウト検討や力学的な強度の成立性の証明を行ないます。
製作段階では、材料表や作業工程表に基づき、QCDSに留意しながら、機械や手工具を動かし加工や組み付け・調整などを体験しました。
また、チームの役割分担や自主活動とベテランのアドバイザーとの交流を通して、様々な知識ノウハウの吸収と体験をしました。
作って走って「大変だったが、面白かった!」

穴あけ例
競技会では、全社員の見守る中、各チームが作成した愛車の性能を競い合い、「ものづくりの大変さと喜び」を体感しました。
≪参加者の声≫
- 「ものづくり」の一連のプロセスを体験でき、ものづくりの大変さと作る喜び・達成感やチームワークの大切さが味わえた。
- 自分達が提供するツールをお客様の視点で体感でき、ツールの強みと問題点も肌で感じた。
- 業務とのからみで、グループ活動の時間捻出に苦労したが、得るものが多かった。業務との両立性を考慮して部下にもぜひ体験させたい。
など、参加者からの反響がありました。この講座の結果を受けて、平成19年度は、一般層の社員教育として実施していく予定です。
今後も「ものづくり」に強く、世界最高水準のIT技術をご提供し、お客様から頼りにされるDIPROを目指して、「人財」の育成に取り組んで行きます。


(デジタルコンテンツサ-ビス部 次長SE 関戸 俊男)
PICK UP