DIPROニュース
日本人の心に響くこと
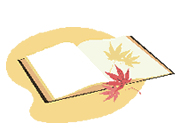
ここ3ヵ月あまり、弊社役員体制変更の御挨拶に各地のお客様を訪問させていただきました。
昨年秋のリーマンショック以来一年近くの時間が経ち、景気は底を打ったと言われているものの、いまだに大変厳しい経済環境にある上、先の見えない状況にあります。
訪問させていただいたお客様先も、まさにそうした厳しい経営環境の中にありますが、春先の何がどうなるのか全く判らないといった混乱の時期を越え、現実を見据え、したたかに耐え抜いていこうとされている姿勢に勇気付けられることも多々ありました。
一方、この間、新幹線を使った移動の機会も多かったのですが、これも春先の閑散とした状況から一転、ビジネス客や観光客で結構混雑していたことが印象的でした。そうしてみれば、盛り場も思いのほか人出が多いし、“百年に一度の不況”という表現とは裏腹に、何の変りも無いような気にもさせられてしまいます。これが、これまで日本が作り上げてきたストックのなせる業かとも思いますし、一方で、このような状況では“火事場の馬鹿力”を期待するのも難しいかなとも考えさせられてしまいます。

日本の経済発展は繊維・鉄鋼・造船などの官主導でスタートしましたが、自動車の排気規制対応やオイルショックに端を発する省エネ技術開発などでは、民間の努力で外乱による大波を乗り越え、結果として危機を国際競争力に転化してきたように思えます。今回の危機もそうしたプロセスをたどってくれれば良いのですが・・・。
さて、これから回復そして発展に向けて進んでいく上で、どのようなスタンスで、どこを目指してしていったら良いのでしょうか。たとえ、経済環境が好転したとしても製造業にとって数多く作れば売れるという時代はとっくに終わっていますし、日本や欧米は、ある意味で”飽食の時代”になっており、お客様が強く欲しがる目新しい製品も簡単に見つかるとは思えません。
最近、法政大学教授の王敏氏の「日中2000年の不理解」という本を読みましたが、その中で、中国人のアイデンティティは儒教中心の価値体系が支える理念型であり、欧米のそれにも似ている。そして、日本人の場合は論理を超える自然融合感が支える美意識という情緒型であり、こうした違いを認識し理解することが国際交流には重要と結ばれていますが、一方で自然との融合感をベースにした価値観は他国の文化がまねできない部分でもあると書かれています。

鳩山首相が国連でCO2削減目標▲25%を表明し、周囲から絶賛される一方で、産業界からは、懸念の声もあると報道されています。現在の危機をチャンスに、そして競争力に転化していくためには、上述のような、日本人の根っこにある自然を慈しむ心に共鳴する大きな目標を掲げ、高いハードルに向かっていくことは意義があると思います。幸いなことに、日本にはそれを支える技術の芽がいくらでもあり、何よりも心に響く目標であれば前向きに取り組んでいけるのですから。
(代表取締役社長 山田 龍一)
PICK UP












