DIPROニュース
成せば成る! ~ICAD戦士のヨーロッパ奮闘記~
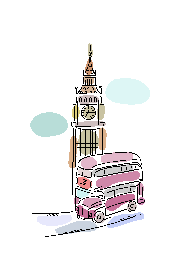
ICAD/SX Mechanical PROにおけるコア技術が世界的に見て、どのようなレベルにあるのか把握するため、ケンブリッジ(イギリス)とデュッセルドルフ(ドイツ)に出張してきました。ケンブリッジでは最先端の研究機関で、エンジニア同士の他流試合とも呼べる技術討議を行い、デュッセルドルフでは国際製造技術見本市を訪問しました。決して英語堪能とは言えないICADビジネス部2名が、見知らぬ国で彼らなりにコミュニケーションをとった奮闘ぶりをご報告させていただきます。
英語漬けの日々
共に日常英会話さえ、おぼつかない香田、大丸の両名が今回の訪問者でした。出発までの短い間に、できる限り英語に触れる時間を作るため通勤中や通常業務の合間はもちろん、帰宅後でさえ、家族に英語で一方的に話しかけるなど工夫をしました。そんな努力の甲斐あってか多少なりとも英語が身についたように思いますが、何より効果があったと感じられるのは、準備段階での訪問先とのメールのやり取りです。特に出発前の一ヶ月間、メールの大半が英語でした。メールではあるものの、英語によるリアルなコミュニケーションが英語力を進歩させてくれたように思います。
長い道のり



両名とも初めての海外出張となりますが、最先端の研究者とCADの方式や仕組みについて議論を交わし、自分自身の技術力を試してみたいという想いから、無謀にも今回のケンブリッジ大学での技術討議を計画しました。
とは言うものの現実はそう甘くはありません。慣れない英語に苦戦しつつコンタクトを取ろうと数人の研究者の方にメールを送りました。待つこと数週間、ようやく届いた返信も日程の都合がつかず、ぎりぎりまでの調整が続きました。出発直前にようやくケンブリッジ大学計算機研究室の方と約束を取りつけることができました。あきらめずに取り組めば、必ず道は開けるものだ、と安堵したのも束の間、議論で使用する資料の最終チェックなどで、出発前日まで準備に明け暮れ、あっという間に時間が過ぎていきました。
学問の街ケンブリッジ
最初に訪れたケンブリッジは、ロンドン・ヒースロー空港から電車で約2時間、古い建物が数多く残る歴史ある街です。市内には30以上のカレッジが存在し、ニュートンやダーウィン、チューリングなど、著名な研究者を数多く輩出した、誰もが知る学園都市です。街の南から流れるカム川と広く緑豊かな公園が、のどかな雰囲気を醸し出していました。石造りの古い建物に囲まれた狭い路地を、近代的な二階建てバスが駆け抜ける姿がとても印象的でした。
次世代CADを目指して
今回の訪問ではいくつかのディスカッションを予定していました。まず、幾何拘束に関するディスカッションを行いました。今後の機能拡張に向けた取り組みを土台に、既存手法の問題点などを論じる議論の中で、新機能への応用手法や今後の開発に向けた新しいアプローチ手法を得ることができ、期待していた以上に有意義な議論となりました。
ケンブリッジ大学ではICAD/SXが採用するデータ構造であるCSG(注1)方式について、その採用理由から議論を開始しました。次に今後さらなる大規模データへ対応するために改良を続けている、独自開発の超高速形状処理エンジンについて議論を進めていきました。
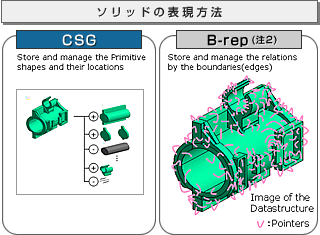
私たちがCSG方式を採用する理由について「機械・装置設計分野では自由曲面を採用するケースは極めてまれ。ほとんどが直方体・円筒・円錐などの形状で構成されており、基本形状を合成して表現するCSG方式が適している」と論じたところ、CSGの利用方法として“very interesting”との評価をいただきました。このことから私たちのアプローチが世界的に見てもユニークなものであるという自信を深めることができました。
独自開発の形状処理エンジンに関する議論では、今後の私たちの取り組みを基に活発な意見交換を行いました。私たちの取り組みの有効性は伝わったものの、実現に向けて解決しなければならない課題に対しては、研究者の方も“too difficult”との見解を示され、課題解決にあたっては一筋縄ではいかないことを改めて認識しました。
(注1) 基本立体を集合演算で組み合わせ、立体を表現する方法。形状の入力や修正が容易だが、自由曲面を正確に扱えないことが欠点。
(注2) 立体を囲んでいる境界面(実体が面のどちら側にあるかという方向の情報も含んだ面)で表現する方法。CSGとは逆に自由曲面を正確に表現できるが、データ量が大きくなる。
技術に国境なし
出張前は、二人共、ちょっとした英会話でさえぎこちない状態だったので、議論の過程で意思疎通が図れるかどうか非常に不安を感じていました。しかし、議論を進めるうちに、お互い技術者(研究者)ということもあり、大体の内容は理解し合うことができました。どうしても上手く伝わらない場合は、日々の業務と同じように、ホワイトボードに図や数式を描き、視覚的に意思疎通を図り、とにかく議論を続ける努力をしました。その結果、スムーズに議論が進まなかった部分もあったものの、全体的に非常に有意義な議論を行うことができたと考えています。技術は、国境を越え、言葉をも超え、理解し合うことができるんだ、と実感しました。
ICAD魂、本領発揮
最後に、ライン川沿いに位置するデュッセルドルフ・メッセにて開催された国際製造技術見本市(METAV)を訪れました。デュッセルドルフ・メッセは空港や市街中心部から公共交通機関でわずか10分程度と交通の便もよく、15もの展示ホールを有する広大な施設です。今回視察したMETAVは、その中の5ホールを使って開催されました。約700社もの企業が出展し、5日間で約4万5千人という多数の来場者で大変なにぎわいを見せていました。

会場内は、機械・装置分野の企業が多数出展しており、工作機械がいたるところに展示され、日本におけるJIMTOFのような印象を受けました。来場者の中には、Audi様など欧州系自動車メーカーの方々もおられました。
当初は出展企業の方に設計対象物などをインタビューするだけの予定でしたが、それだけに留まらず、いつの間にかICAD/SXの売り込みを始めていました。というのも設計対象物がICAD/SXの得意とする平面や円筒面を多用した機械装置や設備であるにも関わらず、ICAD/SXの知名度がゼロに等しかったためです。実際、数社の方々と話をしましたが、ICAD/SXをご存知の方は一人もいませんでした。この歯痒さは、ぜひともICAD/SXを利用していただきたいという想いと、近い将来この場でICAD/SXを出展したいという想いを、いっそう強いものにしました。
世界のICAD/SXに向けて
ネットワークが発達した現代とはいえ、実際に自分から行動し、現地に赴き、自分の目で確かめてみなければ分からないことは数多くあります。今回の経験を通し、数多くの知見を得ることができたのは、間違いなく積極的に行動したからだと思っています。溢れんばかりの情報の只中にいると、全ての事を知っているかのような錯覚に陥り、とかく行動を起こすことを躊躇しがちですが、「とにかく、やってみる」ことの重要性を改めて感じました。
また、英語が不得手でも臆することなく熱意を持って取り組めば、自分たちだってコミュニケーションができるんだということが分かり、英語力というよりむしろ、開発者としてどれだけのバックボーンを持っているか、ということの方が重要であると感じました。技術力は言葉の壁を越えるとでも言いましょうか、そういった感覚を得ることができました。
今回の訪問による一番の収穫は、CAD開発における私たちのアプローチの妥当性と技術レベルを確認できたことです。技術討議の結果、私たちの採用する方式は、最先端の研究からも引けをとらないことが分かりました。これらの収穫は、今後の開発に向けての大きな励みとなりました。この経験を基に、これからも世界中の設計者の「ものづくり」を支える日本発のCADとしてICAD/SXを幅広くご提供できるよう、さらなる努力をして参ります。
(ICADビジネス部 香田 秋生、大丸 哲徳)
PICK UP












