DIPROニュース
大震災と安全について思う
東日本大震災から6ヵ月経ちました。この間に様々な媒体と視点から膨大な報道や論評がなされてきました。毎日大津波のような勢いで伝えるマスメディアだけでなく、皆さまもいろいろ考え、また何かの集まりがあれば一度ならず話題にされたであろうと思います。そう考えれば殆どのことがどこかで語られ、そして言い尽くされているに違いありません。そんななか今さらとも思いますが、多くの方々が有史以来の巨大津波に呑まれ亡くなられていったその時間を共有しながら全く気づかずにいたものとしてなぜか後ろめたさを感じるとともに、何か書き留めておかねばとの思いにも駆られます。とはいえ災害があまりにも大きく、一体何を書いたらよいか正直よく分かりません。とりあえずここでは今回の災害を機に、「安全とは一体何か」について改めて考えてみようと思います。
1. 自然の大災害に対する安全について
今回の大地震に伴う津波は想像を絶する凄まじいものでした。ほんの数分、数十分の間に、津波は数百キロに及ぶ東日本の太平洋沿岸を襲い、2万人の尊い命と美しい自然、そして幾多の人工物や人々の思い出、更には積み重ねられた文化を根こそぎ奪いつくして行きました。あたかも空襲後の焦土のように、しかも戦争と違ってほんの一瞬の間にその何十倍も広い範囲を・・・。
なぜ美しい自然が突然豹変し、瞬時に人々の平穏な時間や生活を奪い去ってしまうのでしょうか。
そんな、人や生き物から見れば獰猛な振る舞いに比べ、‘つなみ’という言葉の持つ響きのなんと優しいことか、以前からそのギャップに大きな違和感を覚えていました。
‘津波’は、湊(みなと)を意味する‘津’と‘波’という漢字から成っています。つまり湊の波です。いつ頃出来た言葉か知りませんが、恐らく津波がどんなものか十分に分かっていなかった時代に作られたからでしょうか、とりわけ巨大津波の持つ計り知れない破壊力とは裏腹に、語意、語感とも実際の現象とは違う優しさを感じます。
津波は実は波ではありません。波は上下の動き(または左右の動き)、つまり振動がとなりからとなりへと伝わって行く現象で、物質(海水)が横に動いたり流れたりするわけではありません。子供のころ波乗り遊びでうまく波に合わせて飛び上がれば高い波をやり過ごせたことを覚えておられると思います。つまり波は振動の一種で本来横方向への力は働きません。しかし津波は海底プレートが広域に亘って滑って隆起し、その上に乗って持ち上げられた膨大な海水が、行き場を求めて四方に向かって高速でこぼれだす地球規模の海洋水の塊と言えます。その流れの先が陸に向かった場合、高速で押し込まれる膨大な海水の全てが納まるまで、どこまでも陸地を遡上します。今回の津波の最高到達点は40メートルを超えたそうですが、地形の条件が悪いところでは、100メートルでも200メートルでも遡上するでしょう。
そんな津波を軽視しがちなのは、たとえ高さ10㎝の小さな津波でも(とはいえ波と違ってスピードがあれば力は大きい)、同じ津波ということで、苦労して避難しても無駄であったという経験からでしょうか、大津波の警報が出てもすぐには体が動かなかった方々がいたというのもうなずけます。更に巨大津波は何百年に一度という頻度のため、怖さが伝承されにくいこと、そして先述のように、津波をそのやさしい言葉通りに理解しイメージすることも影響しているのではないかと思います。
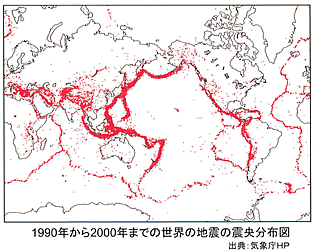
これまで進められてきた地震予知の研究は、実際は極めて困難であるだけでなく、今回のように予測が間違っていた(この規模の大地震は起きないと予測されていた)とき、それに頼って対策をしていた場合の被害は計り知れません。それよりも発生時に今以上に正確に把握し、数秒間、数分間そして数十分の間に、目や耳の不自由な方々も含め対象となる全ての人に、的確に伝え、一刻も早く逃げられる方法をもっと研究した方が有効に思います。そして伝達も単に津波という表現ではなく、例えば(といってもあまりセンスがないかも知れませんが)大津波には「大隆海」とか「大遡海」といった表現や大きさの表示も含め、語意や語感から本当の現象とその怖さを直感的に理解できるようにしたらいかがでしょう。
いずれにしても海水の流速と隆起高、そして総体積などの正確な観測データをもとに、どれくらい陸地が埋まるか、何メートルの高さまで遡上しそうかなどを即座に計算し、一刻も早く伝えられるようにしてほしいものです。
さて今回の地震規模、マグニチュード9.0とは一体どれほどのエネルギーでしょうか。2010年のチリ沖地震は、マグニチュード8.8だったとのことです。マグニチュード8.8は広島型原爆の22,000発分になるそうです。地震エネルギーの5%が津波に変換されたと考えると1,100発分に相当します(「津波災害」 河田恵昭著 岩波書店より)。マグニチュード9.0となると更に0.2大きいので、計算するとエネルギー量はチリ沖地震の2倍となります。巨大なエネルギーを表現するのに対数は確かに便利ですが、マグニチュードが一つ上がるごとに32倍のエネルギー量になる(2つ上がると約1,000倍になる)という表現法だけでは実感がつかめません。今回の大震災は広島原爆の44,000発分となり、チリ津波同様、5%が津波に変換されたとしても2,200個分のエネルギーとなります。
このような巨大なエネルギーを持ち、どこで発生するか分からない津波を、防波堤や防潮堤で食い止めようとの考えには限界を感じます。巨大津波で破壊されれば、今度はそれが凶器となり人間を襲います。例えば高さ15メートルで秒速10メートル、長さ400キロに亘る巨大な津波を受け止められる防波堤や防潮堤を作れるのでしょうか。専門ではないので分かりませんがコスト的にもかなり難しそうに思います。また高さ10メートルの防潮堤に、15メートルの高さの津波が来た時、その差、5メートル分が陸に向かうのではなく、地形によっては、壊れなければ15メートルに近い高さで防潮堤を乗り越え進むはずです(エネルギー保存則から)。日本の四周に、15メートル以上の高さの津波を止められる防波堤や防潮堤を作ることは現実的でないだけでなく、作っても生態系はじめ様々な新たなそして更に大きな問題を引き起こしそうです。大切なのは、大きさに上限のない自然エネルギーを全て阻止しようとするのではなく、ある限度を超えたらうまく逃がし、あるいは逃げて被害を最小化しようとの思想にあると思います。
2. 巨大人工物に対する安全について
福島第一原子力発電所では3つの原子炉の炉心が溶融するという最悪の事態(レベル7)に至りました。長引く事故処理と拡散した放射線被害や汚染水問題など、様々な方面に影響が広がっています。

事故後、様々な立場から安全性について議論されてきました。安全性は基準や想定した災害の大きさで判断が異なります。また作った当時は安全と考えられたものでも、今の基準では安全とはいえない場合もあります。安全技術がいくら進歩してもそれを反映できなければ安全とはいえません。
福島第一原発は1号機が1967年9月着工、1971年3月営業開始となっています。稼働後丁度40年、8年後に稼動した6号機でも32年を経過していることになります。1号機は米国GE社製で、地震の少ない米国で開発されました。火薬庫の上といえるほど大地震が集中する日本に建設するに当たり、どの程度そのことが加味されたのでしょうか。当時の日本は、原子力発電の技術習得に精一杯で、地震や津波を十分に考慮する技術力や余裕はあまりなかったであろうと想像されます。
ところで福島原発が作られた、昭和30年代の後半から昭和40年頃までの日本の技術水準とはどんなものだったのでしょうか。私が身を置いた自動車産業の昭和40代初頭といえば、欧米の自動車技術を取り入れながらようやく国産の量産車を作り始めた段階でした。また設計計算は主に計算尺やタイガー計算機でした。大型計算機はようやく企業に入り始めたころで、計算用ソフトもほとんどなく、使うためには自らプログラムを作らざるを得ない時代でした。また製鉄技術や材料技術、各種材料の加工法や機械設備など、今から見ればはるかに遅れていました。当然ながら出来上がった車の機能や性能、そして品質はもちろん、信頼性や安全性技術も現在とは比較になりません。しかしその後、無駄とも言われた4年に一度のモデルチェンジを通してその時々の最新技術を取り入れ、結果として安全技術も高めることができました。
一方、原発のような巨大な人工物は事故発生時のリスクがはるかに大きいにもかかわらず、一度稼動したら現在の技術では大幅な設計変更は簡単にはできません。本当はリスクの大きい原発にこそ、最新の安全技術が反映できねばなりません。しかし現実は寿命が長いものほど遅れてしまいます。4~50年前の安全技術で設計したものに対し、今も安全ですと言わざるを得ないところに本質的な問題があると思います。加えて廃炉や使用済み燃料の最終処理技術についても未知や困難が多いとのことです。とりあえず原発という飛行機は飛び立ったが、未だ安全に着陸できる滑走路がないということでしょうか。リスクとの比較から、安全性については、大きく遅れているといわざるをえません。
もう一つ重要なことは、テロや戦争への備えも十分にされていなければならないことです。これは欧米諸国が最も恐れていることですが、たとえ核兵器がなくても相手国に原発があればそこを攻撃することで大損害を与えられます。日本では考えるのが怖いためか今まであまり問題にされなかったようです。しかし想定外はあってはなりません。自然災害はもちろん、テロや戦争で破壊されても大災害には決して至らしめないといったしっかりした思想とその実現に向けた決意を求められていると思います。
3. シビアアクシデント後の安全について
7,000万人以上もの日本人が免許を持つ自動車の場合、あらゆる事故が起きることを想定しなければなりません。衝突事故は必ずあることを前提に、衝突してもできるだけ人命が守られる車体構造と、エアバッグやシートベルトなどの乗員保護装置の開発に重点が置かれてきました。今では時速35マイル(約56km/H)で衝突しても人体に致命的な障害を与えないことを求められています。衝突安全技術への注力は、予防安全は他の手段に委ね、車自体はダメージのコントロール(事故後の災害対策)を優先したことになります。
一方、原発の場合は予防安全に注力し、大事故を起こさないための対策が主でした。隕石が落ちるリスクまでは考えない(しかし想定は必要です。その上で例えば対策が不可能との判断を持っていることが重要です。)にしても、巨大な地震や津波、テロや戦争による攻撃などで破壊される恐れは十分あります。特に大地震の多くが日本近辺で発生している事実から、重大な事故(シビアアクシデント)が起きることを覚悟した安全対策すなわちダメージコントロールが十分に施されていなければならなかったはずです。
ダメージコントロールについて十分に考えてこなかったことによる新たな課題は、実は他の分野でも起きています。急速なグローバル化が進んだ今日、リーマンショックのようなシビアアクシデントが起きたとき、生産の平準化や在庫ゼロの追及などで平時に強かった日本経済は、震源地の米国以上に大きな打撃を受けました。日本の宇宙ロケットは、部品個々の信頼性を極限まで高めることで二重、三重のバックアップを極力省き小型軽量化を追及してきました。そのため、万一ある部品に故障が起きた時、救済策が限定されてしまいます。一方、Googleはサーバーを百万台以上使っていますが、多少信頼性が低くても安いものを購入しているとのことです。予め故障を前提にシステムを組めば、高い信頼性で高価なサーバーより結果として安いコストでより高い安全性(停止しないこと)が得られるとのことです(確かにあれだけの情報を扱うGoogleが検索できなくなったという話は聞きません)。特に人命にかかわるシビアアクシデントの場合には、信頼性が高くて安全性の低いものよりは、多少信頼性が低くても安全性が高いことがより重要になります。想定外とは、信頼性は考えたけれど安全性はきちんと考えなかったということになります。
このように様々な分野でリスクが増大していることに照らし、今回のあまりに悲惨な大災害は、全ての日本システムでシビアアクシデントに対する備えは本当に大丈夫か、脆弱ではないか、一度見直しなさいとの警鐘と受け止めるべきと思いました。
巨大な人工物は社会・経済システムも含め必ず壊れます。完璧はありえないことを前提に、起きた後の対応を徹底して考え、備えることが今最も求められていると改めて思います。今回の災害に絞って考えれば、以下のようなことが挙げられます。
- (1) 自然災害の大きさに上限はない、最後は「逃げる」、「やり過ごす」、「いなす」思想を生かす。「疾風に勁草を知る」が如くスムーズに‘勁草’に移行できる社会構造(システム)にする。例えば海岸から3キロメートル以内にいる人は、日本中どんな田舎でも数分以内に、車いすの人も病の人も乳児も全員が巨大地震や津波でも破壊されない(例えば)高さ20メートル以上の、ビルや避難施設に避難できるようにする。
- (2) 今ある原発は(使い続けるなら)事故が起きても地上に影響しない深さまで地下化する。どうやって移設するか、冷却や運転も含め相当な困難を伴うと思うが、被災したときの被害の大きさ(数兆円?)を考えれば研究の価値は十分にある。
- (3) シビアアクシデント発生直後の数秒、数分、数十分を最大限活用する。ネットワークやスマートグリッドは事故や災害の伝達、非常時のコミュニケーションや電力エネルギーの供給、そして全ての危険性ある設備を安全に自動停止するなど、すでに実施あるいは取り組んでいる事例の他に、既存の延長線上だけでない様々な開発や活用手段を幅広く深く追求する。
4. おわりに

書き始めてテーマの大きさと難しさが徐々に分かってきて、途中でやめようと何度も思いました。色々な思いが浮かぶ半面、知らないことがあまりにも多いことを悟ったからです。きっと間違っていることも多いと思いますが、大災害に遭遇し、未だ平常心でないときの率直な気持ちとして記させていただきました。
日本列島が存在すること自体、地球の地殻変動が長い時間をかけて作り上げた証です。美しい富士山も火山の噴火でできたことを思えば自然災害は避けられないと分かります。また人が作った原発に対し、狭い日本で日本人同士が、推進、減、脱、反原発と敢えて色分けして諍うのはとても不幸な事です。できればクリーンな自然循環型エネルギーで賄いたいのは万人の願いであると思います。そのベクトルさえ一致していれば、お互い力を合わせ、心を合わせて解を見つける作業を一緒にできるはずですし、それを日本人が得意としてきたことは、明治維新や戦後の復興の歴史を見れば明らかだと思います。
今回の大災害を機に、日本という地理上の条件を再確認し、今までの歴史や風土、文化がどのようであったか改めて振り返ったうえ、未来に向けあらゆる分野の安全、とりわけシビアアクシデントに対応するために、自然科学・人文科学・社会科学の全てを動員し、日本に、そして東北の地をはじめその土地に適した新たな歴史と文化を創造する出発点にすべきではないでしょうか。
(最高技術顧問 間瀬)
PICK UP












