DIPROニュース
新年度を迎えて

日本経済もようやく明るい兆しも見えるようになりましたが、今度こそは本物の景気回復につながってほしいと願う今日この頃です。新年度のスタートにあたり、日頃のご支援を感謝申しあげますとともに、弊社のこれまで目指してきたものや、今後の方向の一端について多少の雑感もあわせご紹介させていただきます。
'デジタルプロセス'という社名になって、前身の時代も含めはや7年目を迎えました。文字通り'デジタルプロセス'を、会社としてお手伝いさせていただくお客様のあるべき姿と考え、それを社名にいたしました。
当時はそんなにポピュラーな言葉ではなかったように思いますが、最近では自動車産業だけでなくあらゆる製造業で、物を基準にしたエンジニアリングプロセスからデータを基準にしたプロセスへの変革の要請が益々強くなってきています。今年度はそういったニーズに先んじて取り組んできた弊社の強みやノウハウを生かし、お客様のご要望に更に的確に応えられるよう努力してまいりたいと思います。
このような時代にあって弊社の設立以来、私たちがお手伝いできる最大の強みは、「物づくりとITの融合」にあると考えてきました。3年半前に弊社の株式が譲渡されたのち富士通の機械系3次元CAD部隊が弊社に移管されましたが、その際にDIPROのコンセプトを表現するものとして、葛飾北斎の有名な「神奈川沖波裏」という浮世絵を、「DIPRO入魂の図」として掲げました(図1)。
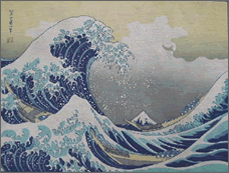
図1. 「神奈川沖波裏」葛飾北斎
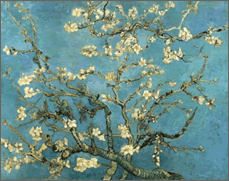
図2. 「花をつけたアマンドの枝」ゴッホ
この世界的に有名な浮世絵の図柄のなかで、荒波に飲まれそうな小さな舟を弊社の姿にたとえ、株式が譲渡されたのを契機に、いよいよひとり立ちしなければならないとして、たとえ小さな舟であっても(日産グループのお客様に支えられた)穏やかな相模湾から、荒波の世界へ自ら漕ぎ出そうという意味で「相模湾から太平洋へ」をあわせて掲げてまいりました。さらにDIPROが目指すべき物づくりとITの融合の場を、黒潮(物づくり)と親潮(IT)のぶつかり合う場になぞらえ、そこを目指そうというおもいもこの絵に込めました。これらの初心をこれからも失わないことが弊社にとって最も大切なことと、心してまいりたいと思います。
ところで少し話がそれますが、1999年に米国の雑誌『ライフ』が行った、「この1000年間で、もっとも重要な業績を残した世界の人物100人はだれか?」というアンケートのなかで、ただ一人ランクインした日本人は、葛飾北斎だったそうです(「日本の美をめぐる-視覚の魔術師北斎、小学館刊」より)。
北斎は没後7、8年にして欧州の画家や知識人の間で注目され始め、19世紀末には、ほかの浮世絵師らとともに印象派の画家たちに大きな影響を与えるようになっていったそうです。確かにゴッホやモネをはじめ、印象派の絵を見ると浮世絵の影響を強く感じる名作がたくさんあることがわかります(図2)。
世界の100人に、たった一人入るほど欧米で有名なわりには、日本人の北斎像は驚くほど貧しいという事実は、大変興味深いというか、きわめて日本的な風景という感がします。同じように、「この1000年間で、もっとも重要な業績を残した日本の人物100人はだれか?」を日本でアンケートしても北斎は入らないかもしれません。
ところで、ここ10年、日本で最もよく使われたキーワードの一つは'グローバル化'であったと思います。日本人のグローバル化とは、多くのTVや新聞・雑誌などのメディアの論調では、海外の仕組み(システム)を導入したり、欧米に同化することを意味してるように思われます。影響力のあるメディアの言葉をそのまま受け入れ、そのような施策が熟慮することなく様々な世界で取り入れられるのを見るととても残念な気がします。私がときどき社外でお話する機会に申しあげるのは、「それらはグローバル化ではなく、植民地化(コロニアル化)ではないか」ということです。真のグローバル化は北斎やその他の絵師の描いた浮世絵のように、ローカルであった日本の本当に優れた価値を世界に認めてもらうことではないかと思います。
今年度、弊社は'真のグローバル化'に対し、以下のような二つの視点で取り組みたいと思います。
一つ目はお客様自身のグローバル化へのご支援です。「お客様が海外に展開されるとき、弊社がご提供しているプロダクトとサービスを、海外においても同様に行わせていただけるようにする」ことと考えます。日本の多くの製造業は中国をはじめアジアへの進出を精力的に進めておられます。そのためにはインフラとしての情報システムの整備は不可欠な条件です。弊社はそのようなとき、最大限のご支援をさせていただきたいと思います。
図3. サポートDBは10万件を超えました
現場密着型でお客様満足度を向上させたいと努めてまいりましたサポートサービスの経験やノウハウを是非海外でも活用させていただきたいと思います(図3)。
二つ目は弊社のソフトウェアプロダクトのグローバル化、すなわち海外への発信です。前述しましたように、お客様が海外に進出される時必要な国産あるいは内製ソフト(たとえばαCAD-II)などは、従来も海外でお使いになる場合ご支援をしてまいりました。ここでの意味は、弊社が共同であるいは自ら開発したソフトの価値を海外のお客様に問うてみたいという意味です。
発足時から、「自らのエンジニアリングツールの 世界への発信を」を目標に掲げてまいりました。北斎ほどではないにしろ少しでも夢に近づきたいと願っています。
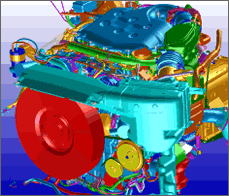
図4. DIPRO VridgeR
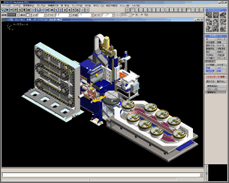
図5. ICAD/SX
具体的には弊社の、また日本の技術で開発されたプロダクトである「VridgeR」と「ICAD/SX」の二つについてその可能性を追求しようと思います。
勿論日本からの発信という、真のグローバル化の困難さは過去の例からだけでなく、十分に理解しているつもりです。一方で残念なことですが、日本人は日本のよさを自ら理解しようとしない、逆に海外で評価されたものは国内でも評価されるとよくいわれます。勿論そういったことを狙うわけではなく、純粋に世界に通用するのかスタディし、チャレンジしたいと思っています。「VridgeR」は、そのベースは日産自動車様が図面レス化に必要なツール(Spacevision)として開発されたものです(図4)。
したがってユーザーの立場、すなわち 「真のエンジニアリングツールとして必要な機能は何か」から発想されたプロダクトです。そのうえに、弊社で独自に開発された'DVX'という高速、高精度のモデリング・表示技術を搭載し汎用化したものです。今年度は更なる性能・機能向上に努め、オンリーワンを目指したいと考えます。
「VridgeR」につきましては、米国のこの分野の有名なコンサルテイング会社であるDaratech社に客観的評価をお願いしていますが、大変高い評価を戴いており、今後は実際のお客様の評価も確認していく予定です。
もうひとつのICAD/SXも、VridgeR同様国産の技術で作られた、精密・機械・装置産業に適した、2、3次元連動型の独創的な設計ツールです。コアとなるモデリングテクノロジーもCSGといわれる沖野教授の提唱されたものを用いており、日本的なものつくりの強みを反映しやすいCADであると確信しています。VridgeR同様にその分野のオンリーワンのツールを目指したいと願っています(図5)。
このように今年度も物つくりとITの融合をテーマに、真のグローバル化を追及しつつお客様のご期待に応えるプロダクトとサービスを提供してまいりたいと思います。DIPROは今まで下記のようなメッセージを発信してきました。
- 『真のソリューションプロバイダー』を目指します。
- 『結果責任を取る気持ち』でお手伝いさせていただきます。
- 『製造業から製像業へ』のご支援をいたします。
- 『製像力で創造力を加速する』お手伝いをしたい。
- 『SEではなくPSE』、すなわちプロセスをシステム化する集団(Process Systematizing Engineers)を目指します。
このようなメッセージやアイデンティティに込められたマインド(少しかっこよくいえばSoul)を忘れることなく今年度も努力してまいりたいと思います。これからもご指導、ご鞭撻をいただけますよう、どうかよろしくお願いいたします。
(代表取締役社長 間瀬 俊明)
※掲載されている車両(または、その一部)の画像は、日産自動車株式会社様のご提供によります。
PICK UP












