DIPROニュース
オートモーティブ デジタルプロセス セミナー 2005開催
~自動車メーカー代表が知識の蓄積伝承とIT活用について活発な論議~
第14回となる「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー」を去る2月10日(木)に開催いたしました。例年とは開催期が異なり、寒い中での催しとなりましたが、おかげさまで会場が満員となる1000名近いご参加を戴きました。ご多忙の中、会場のパシフィコ横浜までご来場戴きました皆様に、厚く御礼申し上げます。
今回は、『製造業における知識の蓄積・伝承とIT活用』というテーマとさせて戴きました。バブル崩壊後の10数年、日本経済を支える製造業企業は、厳しい経営環境の中でグローバルな競争力強化に懸命に取り組んできましたが、ここへ来てやっと努力が成果へと報われるように変わってきたように思えます。ものづくりをする企業が勝ち続けていくためには、商品開発力を支える「技術」を常に高め、「知識」を蓄え創造し続けることが、大変重要な課題となってきていると言えます。本セミナーでは、知識をどのように蓄積し共有していくか、知識を活かすためにITをどう使うかをテーマに取り上げました。
基調講演をお願いした一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授の 野中 郁次郎先生は、知識創造の方法論や知識創造企業のあり方について世界的な権威として知られています。野中先生には、「21世紀のモノづくりと知識創造」といった内容でお話をして戴きました。
ご講演・パネルディスカッションにおいては、今回も自動車業界のトップリーダーの方々にお集まり戴きました。日産自動車株式会社 取締役副社長の大久保 宣夫様、株式会社 本田技術研究所 CIS1ブロックマネージャーの岩本 淳様、トヨタ自動車株式会社 常務役員の天野 吉和様の三名の方にご講演を戴きました。パネルディスカッションでは、トヨタ自動車株式会社 常務役員の天野 吉和様、日産自動車株式会社 VP兼コストエンジニアリング本部長の増田 譲二様、株式会社 本田技術研究所 CIS1ブロックマネージャーの岩本 淳様、マツダ株式会社 車両コンポーネント開発本部長の藤崎 康博様のご参加を戴き、知識創造とITについて議論を戴きました。
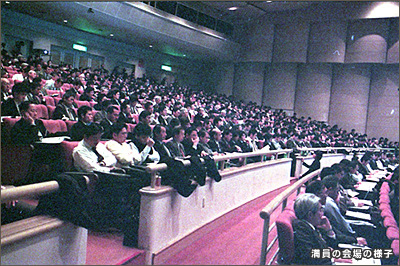
基調講演: 『21世紀ものづくりと知識創造 -イノベーションをクセ化する-』
一橋大学大学院 国際企業戦略研究科 教授 野中 郁次郎様
まず基調講演として、野中先生から、「知識とは何か、知識の創造の仕組み、創造の目標や場、手段、組織とリーダーシップ」について著名人や現代企業の実例を挙げながら、説明をして戴きました。
持続的にイノベーションを続ける企業は、「個人の真の思い・信念を社会的に正当化していくプロセス」を基本命題として持つという話題からスタートし、知識は、暗黙知と形式知の相互変換の中で創造されていくというお話を戴きました。著名人の言葉を例に挙げながら、擬音や隠喩において暗黙知と形式知が変換されることや、物語や論理・分析における知の変換の例を説明戴きました。
この後、組織的知識創造プロセスのモデルとして「SECIモデル(知識がSocialization[共同化]→Externalization[表出化]→Combination[連結化]→Internalization[内面化]のサイクルの中で、暗黙知・形式知が変換されながら創造されていくという原理)」を解説戴きました。主観と客観の往還運動を通じて知識が創造されることや、SECIスパイラルの高速化、高速回転が重要であことを説かれました。また、知識創造企業のモデルはどういったものか、ビジョン・駆動目標・対話・実践という個々の要素、日本企業における知の型や意味空間としての“場”の重要性など説明戴きました。
更に、人の繋がり・組織の再編成の中で知がラディカルに結合するというお話や、リーダーシップは“場”をベースに人間力を開発するということ、不確実な環境では感情の知の共有が重要であることなど、実例を用いながら興味深い話題を一つ一つ紹介されました。最後に自律分散系のリーダーシップにより、知が“場”を得て創出・実践されることや、知識創造企業とは「どう在るか」「どう知るか」といったことを“綜合”したプラグマティズム(実用主義)を実践していく、一つの「生き方」であるとのお話で結ばれました。
大変熱心に「知とは何か、知を創造する企業として何が必要なのか。」を興味深い実例を豊富に用いて、分かりやすくご講演戴きました。

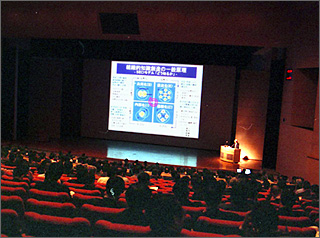
野中郁次郎様 略歴
1958年 3月 早稲田大学政治経済学部 政治学科卒
1972年 9月 カリフォルニア大学バークレイ工 経営大学院博士課程修了(Ph.D)
1978年 4月 南山大学経営学部教授
1979年 1月 防衛大学教授
1982年 4月 一橋大学商学部付属産業経営研究施設教授
1995年 2月 北陸先端科学技術大学院大学教授併人
1997年 5月 カリフォルニア大学ゼロックス知識学 ファカルティ・フェロー
2000年 4月 一橋大学院国際企業戦略研究助教授
主な受賞
日経・経済図書文化賞(1974年11月)、組織学会賞(1984年10月)、経営科学文献賞(1991年1月)、米国アカデミー・オブ・マネジメント フェローグループ選出(2002年 4月)、紫綬褒賞(2002年5月)
主な著書
失敗の本質(共著、ダイヤモンド社、1984年)、知識創造の経営(日本経済新聞社、1990年、経営科学文献賞)、識創造の方法論(共著、東洋経済新報社、2003年)、イノベーションの本質(共著、日経BP社、2004年)
ご講演:『日本の自動車開発技術 ~欧米との違いについて~』
日産自動車株式会社 取締役副社長 大久保 宣夫様
大久保様からは、開発部門トップとしてのご見識と長年のご経験を踏まえて、欧米と日本の自動車開発がどう異なるか、どう変わりつつあるかなどをお話戴きました。

先ず、「欧米の自動車開発の特徴」として、国民性から来る日本と欧米の考え方や行動の違いや、日本の開発体制と欧米との差異、サプライヤーや生産部門との関係やモノづくりに関する意識の違いを紹介されました。次には「ルノーとのアライアンスから学んだこと」として、欧米の収益に対する考え方、アイデンティティに対するスタンスや日本のモノづくりの長所などを説明戴きました。また最後に、今後に向けて「将来の日本の自動車産業とITへの期待」ということで、クルマ作りの変革とITについて思うことをご紹介戴きました。
豊かなご経験と深い洞察力に基づく「日本の自動車開発技術」のご講演は多くの参加者に大きな感銘を与えました。
ご講演:『自動車開発における開発ノウハウのIT活用事例と今後の展望』
株式会社 本田技術研究所 CIS1ブロックマネージャー 岩本 淳様
岩本様からは、ホンダ様の組織や風土としての特徴、ありたい姿とIT化の狙いや課題、将来に向けた思いを、様々な資料を用いて御紹介戴きました。
先ずは、ホンダの組織、研究所の役割、ホンダイズムと呼ばれる特色溢れる風土と経験に根ざした技術蓄積・共有の重要性とありたい姿の紹介を戴きました。現場・現物・現実を重視する“三現主義”や組織や上下の隔て無く議論する“ワイガヤ”に、知識創造企業としてのエネルギーと強さを感じることが出来ました。

次には、ITに関する話題をご説明戴き、情報活用の目指す姿・狙いや活用事例を紹介戴きました。IT化の目的・ニーズの重要性とシステムの実情、効果の実際など大変興味深い内容のお話を伺うことが出来ました。
また今回の知識創造と蓄積・活用のテーマに合わせ、3次元設計の効率化とナレッジ活用についてお話を戴き、今後の展望や将来に向けたのアイデアをご紹介戴きました。独自の視点で、今後求められるナレッジや事例を考察戴き、他には無いユニークな知識創造企業の姿を定義して戴きました。最後に紹介された「先取(さき)をいく」「為になる」というキーワードに、次世代のモノづくりに挑戦する強い姿勢と熱意をうかがうことができました。
ご講演:『グローバルな成長をめざして ~トヨタの技術とITに期待すること~』
トヨタ自動車株式会社 常務役員 天野 吉和様

天野様からは、トヨタ様でのグローバルな成長への取り組みと課題、ITへの期待をご講演戴きました。トヨタ様の危機感を背景にしたグローバル市場での成長や取り組みの現実、設計部門におけるトヨタ流の創意工夫などをお話し戴きました。豊富な事例を引用してのご説明や、今後に向けた強い思いを交えての様々なお話があり大変分かりやすく、かつ興味深い内容でした。
モノづくり技術やITの話題のみならず、経営や人材育成に関する事まで、幅広くお話をして戴きました。最後に、城の石垣の絵を引用され「城の石垣では石の大小では無く、個々の石がそれぞれの特性を持って、組み合わされて機能することが大事である。」と語られたお言葉が大変印象に残りました。
パネルディスカッション:『製造業における技術の蓄積・伝承とIT活用』
| パネラー | |
| トヨタ自動車株式会社 | 常務役員 天野 吉和様 |
| 日産自動車株式会社 | VP兼コストエンジニアリング本部長 増田 譲二様 |
| 株式会社 本田技術研究所 | CIS1ブロックマネージャー 岩本 淳様 |
| マツダ株式会社 | 両コンポーネント開発本部長 藤崎 康博様 |
| 司会 : 弊社社長 間瀬 俊明 | |

パネルディスカッション


パネルは、日産様から、VP兼コストエンジニアリング本部長の増田様と、マツダ様から車両コンポーネント開発本部長の藤崎様を加えて4名で行いました。テーマは、「自動車開発の技術蓄積と伝承」、「ITで何が出来るのか、IT化したあとの技術伝承」が議論されました。
「技術蓄積と伝承」のテーマにおいては、知識創造のモデル(SECIモデル)における各社の強みや特徴、現状の取り組みを紹介戴きました。現場に即した知識の蓄積と、取り組みの中で夫々に知識創造のスパイラルを回す試みをされていることがわかりました。また、グローバル化の波の中での日本の強みと、グローバルな視野での知識創造のあり方や、サプライヤーとの協業のスタイルについても論議されました。
「IT活用」のテーマにおいては、現状のツール(CADシステム)に関する機能・操作性・変換機能等の改善の必要性が話題となりました。また、データ管理(PDMシステム)については、「やりたい事を決める」ことの重要性や、市販パッケージ適用の課題などが議論になりました。
他に、モノづくりの中での"図面"の意味付けや利用方法が変化していること、変わりゆく業務に合わせ、システムは暗黙知(Black Box)とする部分、形式知化する部分を切り分けて、改善していく必要がある等々の話題がありました。
各々の会社様での実体験を元にした活発な意見交換が行われ、「知識創造として望まれている事」と「ITに期待されている事」について、夫々が浮き彫りにされたように感じました。

岩本 淳様

藤崎 康博様

司会 間瀬 俊明
出展
講演会場に続くスペース(フォワイエ)と通路で、商品展示をさせて戴きました。「ICAD/SX」、「VridgeR」、「PLM Solution」など合計6カテゴリの展示を行いました。例年とは異なり、会場に展示場所を併設したことで、盛況感のある出展になったと思います。
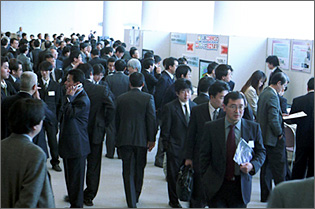

懇親会

パネルディスカッション終了後に、会場を変えて懇親会を行いました。例年通り多くの皆様にご参加戴きました。和やかな雰囲気の中で、参加者の皆様がお互いに交流を深めながらご歓談をお楽しみ戴けたと存じます。
ご参加を戴きました皆様に厚くお礼申し上げます。
アンケートより
参加者の方々より頂いたアンケートを御紹介いたします。おかげ様で例年のように、好い評価を戴いたものが多数ありました。以下、一部を原文のまま紹介させて戴きます。
「キーワードとして耳にしたり目に触れたりしていた暗黙知・形式知について直接先生から講演を聴くことが出来、大満足であった。」
「他社のIT化の考えなど、判り参考になりました。」
「パネルディスカッションは、本音がでていたようで、たいへん参考になりました。」
「プログラム内容も会場もパネルも展示も満足できました。次回も参加させて戴きたいと思います。」

一方、ご要望やご指摘も戴きました。以下に紹介させて戴きます。
「ナレッジ活用についての具体的な事例紹介をしてほしい。」
「サプライヤーさんの状況も聞かせて戴きたい。」
など。
今回も、皆様のおかげを持ちまして、大盛況の内に終わることができました。
ご参加頂き誠にありがとうございました。
(業務部 企画グループ 吉野琢也)
PICK UP












