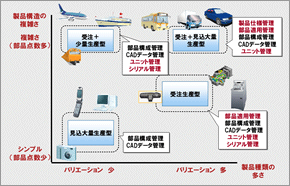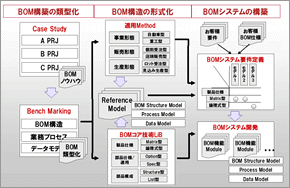DIPROニュース
PLM/BOMソリューションのご紹介
はじめに
弊社では、自動車業界中心にBOMおよび周辺システムの構築・コンサル経験が多数あり、各種ノウハウを体系化、保有しております。そして、これらを背景として、組立製造業のお客様を中心に各種ソリューションを提供させていただいております。
本稿では、PLM/BOMソリューション概要(BOM概要、構築アプローチ)とその適用事例を紹介させていただききます。
PLM/BOMソリューション概要
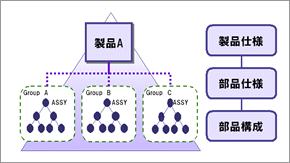
企画に始まり、設計、生産、販売、アフターサービスといった一連のものづくりプロセスにおいては、商品仕様を出発点に、様々な製品情報データが発生していますが、設計仕様や部品構成などに代表される材料情報を管理するのがBOM(図1)であり、ものづくりプロセスにおいて、非常に重要な役割を担っています。
近年、BOM構築にあたっては、次のような市場からの要求が引き金になり、構築が進められています。
- 顧客要望の多様性に伴う製品バリエーションの増大化
- 製品開発期間の短縮化
- グローバル化に伴う地域特性の考慮
これらの背景のもと、BOMおよび周辺システムの構築では、お客様の製品特性、業界、業務形態などの違いにより、BOMに求められる機能とその役割に違いがあるため、お客様ごとのBOMシステムの構築が必要になります。(図2)
また、お客様ごとのシステムの構築では、投資(期間・費用)をいかに抑制できるかが重要になります。弊社は、過去10年にわたり多数のBOM構築を支援してきており、その中で、『Case Study』、『Benchmarking』を行い、BOM構築の類型化を志向してきております。そして、これらをPLM/BOMソリューションとして活用できるよう、『適用Method』、『BOMコア技術LiB』としてBOM構造の形式化を図っています。(図3)
BOMシステムの構築では、お客様のBOM構築を強力にご支援するために、多彩なBOM構築支援活動を通して抽出された『BOMコア技術LiB』と、最適なシステム構築に向けたコア技術の 『適用Method』を用いて、お客様の要件・BOM仕様と弊社のノウハウをマッピングし、お客様の業務特性や業務成熟度にJust Fitする『BOMシステム要件定義』をご提案します。さらに、お客様の業務とその成長にあわせ、拡張性高いブロックビルディング方式(BOM機能Moduleを組み合わせたセミオーダー方式)による、『BOMシステムの開発』を行い、システム投資を適正に抑制します。
次に、PLM/BOMソリューションの適用事例をご紹介します。
PLM/BOMソリューション適用事例 (半導体製造装置メーカー様)
受注から保守・サービスまでの製品情報管理の実現
PLM/BOMソリューションを活用し、製品ライフサイクルを通しての製品情報管理を実現した、半導体製造装置メーカー様の事例をご紹介します。
このメーカー様の製品は、お客様の製造要件と工場の設備・環境に依存する受注生産型の製品です。個々の製品がお客様仕様となっているため、製品構成や製作に使用する図面などを個々に管理することが重要です。そのうえ、製品の出荷、納品後もお客様の満足するアフターサービスを行うために、お客様ごとの製品は現在どのような製品構成になっているか、素早く確認できることが必要です。これまでは、お客様ごとの管理に多大な労力を費やしておりました。
営業から設計、生産、さらにはアフターサービスまでの製品ライフサイクルを通して、効率よく製品構成と技術情報を管理する仕組みが求められていました。そこで、設計出図から生産手配までのお客様ごとの製品情報を一元管理し、出図のリードタイム短縮と海外を含むグループ会社との情報連携による効率化を実現するためにグループ全体で活用できるPLMシステムを構築しました。(図4)
設計部品表を中核とした統合管理
今回のPLMシステムで改善された業務機能を4つほどご紹介します。(図5)
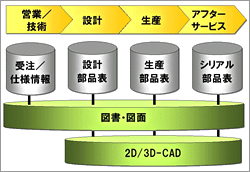
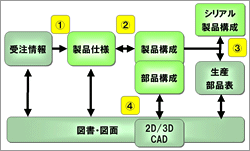
1.受注時からの仕様管理
仕様検討の段階から部品表システムで情報管理を行うことができるようになりました。これにより、受注から設計までの連携が迅速化しました。
2.製品構成の自動作成
お客様からの要求仕様を受注時に入力することで、以降の工程で利用される製品構成が自動作成されるような仕組みになりました。
3.製品のシリアル管理
お客様ごとに製品構成が異なるため、それを識別するためのシリアル番号を発行し、製品の情報を個体単位で管理することが可能になりました。
4.CAD/図書の一元管理
今回のシステムでは、関連する技術情報の管理システムであるCADデータ管理や、図面・図書管理システムの情報が連携できる仕組みになっています。部品表をインデックスとして、必要なCADデータや技術文書などが参照できるようになりました。
今後の計画として、営業受注段階での製品スペック選択を可能とする製品仕様管理へと機能拡張していく予定になっています。また、お客様は部品表の中身を早急に整備していき、営業システムだけでなく、コスト管理や見積もりシステムなど様々な周辺の仕組みを充実させていきたいとの構想をお持ちになっています。
最後に
BOM本体のみではなく、昨今はBOM周辺における、原価・重量管理や部品種類と点数の低減、環境負荷対応、KPI関連(SOX法)など市場の要求はますます高度化しています。この領域でも、今までの豊富な経験をもとにご支援させていただきます。まずは、ご相談から、お気軽にご用命いただけると幸いです。
(第二技術システム部 次長SE 羽賀 晴比古)
PICK UP