DIPROニュース
オートモーティブデジタルプロセスセミナー2017のご報告

11月10日(金)、パシフィコ横浜において「オートモーティブデジタルプロセスセミナー2017」を開催いたしました。ご来場の皆様ならびにご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
自動車産業は「100年に一度の変革期」にあると言われ、近年続いてきたクルマの電動化・知能化に向けた流れは、世界各国の電動化に向けた大胆なマイルストンの提示、国内においては、高齢化やドライバー不足といった社会問題を背景にした自動運転に向けた動き等で、よりはっきり、大きく加速したように感じます。
これらの流れの中では、既存の自動車産業はもとより、異業種やベンチャーなどの企業間、かつグローバルでの開発競争も激化しており、今後10年程度の間に、産業や社会、生活様式に対しての大きな変革の可能性を感じます。

こうした背景を受け、今年は「知能化」に焦点を当て、人工知能と自動車の関わりから、安全かつ自由なモビリティ、それらが暮らしに与える変化についてご講演頂き、また国内主要自動車メーカーのエンジニアリングITのキーマンの方々にパネリストとして熱く語り合っていただきました。
基調講演:人工知能の現在と次世代オートモーティブ
国立情報学研究所 教授・総合研究大学院大学 教授・東京工業大学 特定教授
山田 誠二 様

本講演では、先ずAIの歴史からお話いただきました。60年代、80年代に続く第3次ブームとなる現在は、ビッグデータの活用や計算機の高性能化を背景に、実用的問題解決が可能になりました。また、AIは探索空間やルールが限定されている分野を得意とする一方で、背景が無数にあるような分野や常識的な推論などを不得手としていますが、従来不得手としていた人間の骨格を捉えるスケルトン抽出などの技術は時代とともに改良されているそうです。
これからのAIとしては、人とAIがそれぞれ単体で作業するのではなく、人とAIが得意分野を補い合い、協調して作業を行うシステムをつくることの重要性、またその課題を、ロボットが副操縦士を担当する飛行機の例、工場ラインでの人間・ロボットの例などを交えながらお話しいただきました。
AI・自動運転技術による近未来の車社会については、人がAIを過信しすぎること、人とAIの役割分担をどうすべきかなどの課題と共に、ドライバーや歩行者の意図を理解するクルマの実現や最適走行ルートを遵守することによる自動車交通最適化への期待をお話いただきました。
最後に、自動走行を爆発的に普及させるには、歩行者や相手ドライバーといった人間のモデルを取りこむことの必要性を説明され、そういった技術開発を続けることにより、人とAIが協調していくようなクルマ社会、次世代オートモーティブの実現が可能となるとの、自動車メーカー様への期待を含めた言葉で結ばれました。
講演:トヨタの先進安全・自動運転技術開発の取組み
トヨタ自動車株式会社
先進技術開発カンパニー 常務理事 鯉渕 健 様

自動運転の発想は、約80年前のニューヨーク万博にてGMが出展した「Futurama」での自動運転の未来構想から始まりました 。2000年代に入るとアメリカ軍による戦地での地雷回避を目的とした無人運転の研究が自動運転を大きく飛躍させる原動力となりました。さらに近年ではセンサーの高感度化、CPU能力の劇的な向上、ソフトウェア技術の大幅な進化を契機に自律型自動運転の風潮が盛り上がってきています。
トヨタ様では、自動運転のコンセプトとして『MOBILITY TEAMMATE CONCEPT』をベースに、3つの“知能化”を軸として人とクルマが協調する自動運転を目指しておられます。まず、自動運転に必要な“運転の知能化”のために、高精度のセンシング技術による認識技術や、AIを活用した判断技術、自己学習技術の開発を進めています。“人とクルマの協調”のためには、自動運転から手動運転へのスムーズな切り替えなどにより人とクルマの気持ちが通った関係を築くことが重要です。また“つながる知能化”として、自律センサーだけでは困難な空間情報の認識を無線で補完し、自動運転において重要である3D地図を車のカメラ画像から自動生成することや、Connected技術により自動車のソフトウェアを常に最新状態に保つことが可能となります。
安全性、信頼性を向上させるためには膨大な検証が必要であり、シミュレーション技術の構築、活用が不可欠です。現実的な課題として、法規、責任の所在、社会受容性などの側面にも取り組む必要がありますが、これからも自立した生活、ゆたかな社会、Fun to Driveを目指して前進していくと締めくくられました。
講演:AIなどのデジタルテクノロジーがもたらす「移動」と「暮らし」の進化
株式会社本田技術研究所
執行役員 R&DセンターX担当 兼 ロボティクス統括LPL 脇谷 勉 様

ホンダ様は、今年4月に新価値領域を担う研究開発組織R&DセンターXを設立されました。今までの開発技術を活かした、「ロボット」、「モビリティ」、「スタビリティアシスト」で人が中心となる新たなロボット社会を実現することがR&DセンターXのゴールとされています。
「人と共存するためのAI=Cooperative Intelligence(CI)研究でなければ意味がない」と強調されています。CIによる新たな社会の実現、そのキーワードとして3E、「Empower」、「Experience」、「Empathy」という3つの単語を掲げられました。そして、芝刈り機の自動化によって、休日の過ごし方が変わり、家族団欒が増え、予想外の効果をもたらしたという、3Eが具現化された例をご紹介くださいました。さらに、今後AIや自動運転により、渋滞緩和、燃費向上、移動コスト低減を挙げられ、移動手段が変化することによるライフスタイルの変化を考察していただきました。
一方、プライバシーや倫理の問題についても触れられ、自動運転車が取った選択行動が裁判になった場合など、議論していかなくてはならない課題が多いこともお話いただきました。こうした中、基調講演でご登壇いただいた山田様が理事長を務めておられる人工知能学会では、倫理委員会を発足させ、AIの研究開発における倫理指針をまとめたという、世界に先駆けた取り組みについてもご紹介くださいました。
最後に、「すべての人に生活の可能性が拡がる喜びを提供したい」との思いを強く語られました。AIなどのデジタルテクノロジーの開発は社会全体でオープンに対応していく時代、「機会があればぜひお願いいたします」という言葉を、会場のお客様に投げかける形で講演を締めくくられました。
パネルディスカッション
自動車開発のデジタル化 一気通貫プロセスへの飛躍
~エンジニアリングシステムの実力と方向性~
- トヨタ自動車株式会社
- エンジニアリングIT部長 細川 昌宏 様
- 日産自動車株式会社
- グローバル情報システム本部 エンジニアリングシステム部主管 松木 幹雄 様
- 株式会社本田技術研究所
- 四輪R&Dセンター デジタル開発推進室長 田中 秀幸 様
- マツダ株式会社
- ITソリューション本部 エンジニアリングシステム部長 細川 大 様
- 三菱自動車工業株式会社
- グローバルIT本部 エンジニアリングIT部長 津田 孝博 様
- スズキ株式会社
- IT本部 デジタルエンジニアリング部長 市原 誠 様








本セミナーのテーマでもあるAIの活用は、ものづくりの現場でも革新的な効果が期待されています。しかし、実際にはEIT部門は「実績のある安定的な技術で、いかに日々の自動車開発を支えて行くか?」という現場・現実の悩みに取り組まざるを得ない立ち位置にあります。PLMシステムとしては、一昔前から一気通貫によるものづくりのデジタル化とその効果創出を標榜してきましたが、そこには様々な現実の課題が残されており、部品表情報を繋ぐBOMの情報流と形状情報を主体とするCAD/PDMの情報流の2本の軸の周りで、各社毎に最適解を探しつつ、そのレベルを高めてきました。しかし、近年の自動車の電子化・電装化、ソフトウェア活用も新たな重たい課題を投げかけています。
今回は、BOM/PDM領域の課題、ソフトウェア管理の課題、開発の初期段階で使われるツール、生産現場のIT化の課題という4つのテーマについて、ディスカッションを行いました。司会は、本田技術研究所の田中様に進行役をお願いしました。
「BOM/PDM周辺の課題」については、アライアンスにおけるCADデータ交換について、推進中の事例の紹介をいただき、その課題や取組みといった実状をご説明頂きました。「BOMと情報連携及びその運用」については、仕様の増加による設計者の負荷増大やEBOM-MBOM連携の課題、現状の取り組みをディスカッションして頂きました。「ソフトウェアの管理」については各社とも、まだまだ試行錯誤の段階のため、DIPROがベンダー視点で課題の説明やソリューション紹介をさせて頂きました。「商品企画から統合仕様管理の領域」については、早期の性能開発ツールとして、Excelが多用されている実態をご説明頂きました。「ものづくり領域の課題」については、生産現場のIT管理/運用の現状と取り組み、IoTやセキュリティの問題などに関してディスカッションして頂きました。
最後には各社から、一言ずつコメントも頂きましたが、それぞれに納得・共感できる内容でした。これまでの取組みや環境は各社とも違いがあり、互いに学ぶべきことが多々あるのと同時に、その課題認識や方向性については、共感を持てる話が多数あります。ツールや選択した打ち手が違えど、互いに協力し合って、効率的な解決策を模索して行きたい、という思いにおいて、6社で合意ができたと思います。
例年通りのプログラムで長丁場でしたが、興味深い内容に過ぎていく時間を忘れた1時間20分でした。
全体を通して
講演の合間の休憩時間には、講演会場外にて弊社製品やソリューションのデモ展示を行い、お客様から熱心なご質問やご相談をいただきました。また、セミナー終了後の懇親会にも多くのお客様にご参加いただき、今年も大盛況のうちに終えることができました。
アンケートでいただきました“大変参考になった”という声や、運営に関する様々なご意見につきましては、今後の参考とさせていただきます。なお、お客様の業務に関する様々な悩みにつきましては、弊社の営業やシステムエンジニアが詳細をお伺いし、問題解決に向けた建設的なご提案をさせていただきたいと考えております。
これからもDIPROは、社員全員が一丸となってお客様に寄り添いながら問題解決へ向けて進んでまいります。今後ともご愛顧いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
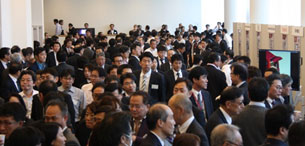

PICK UP












