DIPROニュース
オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2012 開催

11月28日(水)、パシフィコ横浜において「オートモーティブ デジタルプロセスセミナー 2012」を開催いたしました。本年も昨年に引き続き、午後からの開催でしたが昨年より多くのお客様にご来場いただきました。ご来場の皆様ならびに開催にご協力いただきました皆様に厚くお礼申し上げます。
昨年の東日本大震災や原発事故、タイでの洪水被害の記憶が冷めやらぬうち、欧州発の経済の混乱や長期化する歴史的な超円高など、国内製造業は極めて厳しい経済環境に直面しています。そして、政治課題の顕在化による中国ビジネスの急激な落ち込み、さらには国内政治情勢の混迷などの新たな要素も加わり、先行き不透明な状況が続いております。さて、今回のセミナーは、こうした状況下、日本の製造業の新たな可能性や方向性を考えていく上で、ヒントとなるべく状況認識や考え方をご提示いただき、今まさに進みつつある自動車メーカーにおける新たな挑戦をご紹介いただくことを軸に企画いたしました。

通算で20回目の今回は、基調講演として東京大学大学院経済学研究科教授、総合研究開発機構(NIRA)理事長の伊藤 元重様に「内外の経済潮流と日本のもの作り」と題してお話しいただきました。また、トヨタ自動車株式会社常務役員の友山 茂樹様に、「次世代エコカーとつながる未来」と題し、次世代エコカーの普及により、社会、そして自動車ビジネスはどう変わろうとしているのかというお話を、続いて、日産自動車株式会社執行役員常務の坂本 秀行様には、「生産技術における日産バーチャル開発の現状と将来革新技術への考察」と題し、最近のモジュール設計や自動化要素技術の進化が創り出す生産技術の将来像についてのお話しをいただきました。最後に、毎回ご好評いただいておりますパネルディスカッションでは、昨年までのエンジニアリングITサイドから業務サイドに視点を移し、自動車メーカーの設計・技術管理のキーマンの皆様、トヨタ自動車株式会社の三嶋 保夫様、日産自動車株式会社の八代 宏様、株式会社本田技術研究所の中嶋 守様、マツダ株式会社の縄 淳二様、三菱自動車工業株式会社の渡邉 勝二様、そしてスズキ株式会社の永井 利典様にご登壇いただき、各社の状況および最新の課題について語っていただきました。
基調講演:「内外の経済潮流と日本のもの作り」東京大学大学院経済学研究科 教授/総合研究開発機構(NIRA)理事長 伊藤元重様

伊藤様は最初に、BRICsなどいわゆる新興国は今後も発展していくと思いますか、とお客様に問いかけられました。そして考えるためのヒントとして、新興国の世界GDPに占める割合を挙げられ、今後も新興国は伸びるという説と、この10年間は特殊で、今後は元に戻るという2つの仮説を提示されました。どちらになるかによりあらゆることが大きく変わってきます。今後、一つの見方だけで判断するのではなく、お客様自身がアンテナを高くしてどちらの説が正しいのかを見極めて欲しいと話されました。
次に、今後の景気動向について考察されました。伊藤様は、今後の景気を考えるヒントとして1996年に亡くなられたハイマン・ミンスキー教授の理論が近年注目されていることをご紹介されました。ミンスキー理論を鑑みると、米国は底をついたと言われています。欧州はまさにミンスキー理論の下り坂が始まったばかりです。新興国で最も注目されている中国は、輸出依存、安価な農村労働力、外資系企業参入の3点セットで著しい成長を遂げてきましたが、潜在成長力の低下も見られはじめています。一方、日本の場合はというと、ミンスキー理論の下り坂を終えた注目される存在となっています。今こそ差別化政策、そして海外進出といった次の一手が期待されています。モノづくりの基礎部分である、素材、デバイス、製造機器など自分たちの得意分野に特化した投資をすべきで、ドイツに例を見るような、無名ではあるがグローバルに高いシェアを占める「隠れたチャンピオン」企業をいかに多く作っていけるかが重要である、とのことです。
そして最後に、これからの日本企業の進むべき道ということでお話しいただきました。
まずは、アップル社のような「チャネルリーダー」になれる企業がどれだけあるかが、日本のモノづくり、さらには日本経済にとって重要であるということです。素材、デバイスなど日本の強さを100%生かすためには今起きている変化を正面から受けて立つ必要があります。可能性を持った企業がたくさんある中、特に自動車は日本にとって最もチャネルリーダーになってもらいたい企業である、との伊藤様の思いもお聞かせいただきました。
次に、日本の国内企業を活性化させるためには「イノベーション」しかない、と明言されました。かつてのGEのイノベーションを例にとり、これからの日本経済にとっても重要となるエネルギー・環境分野と医療・健康分野において、どういう改革ができるか、何を生み出せるかが非常に重要であると述べられ、セミナーにお越しいただいたお客様向けにエネルギー・環境分野についてお話しくださいました。
日本経済は今、それらの分野においても大変厳しい課題を突きつけられています。しかし、まさにそこにイノベーションのカギがあり、大事なのはトレンドを読み誤らないことです。上述の二つの分野において日本のモノづくりの可能性を今後も議論したい、との言葉で、日本のモノづくりの果たすべき役割に対する大きな期待に触れられながら、講演を締めくくられました。
講演:「次世代エコカーとつながる未来」トヨタ自動車株式会社 常務役員 友山茂樹様

昨今のエネルギー問題を背景に、社会におけるクルマのあり方が大きく変化しつつある中、友山様からは次世代エコカーや自動車ビジネスの将来像についてお話しいただきました。
冒頭、友山様はご自身がGAZOOレーシングの役員を担当されているというお話から、先般行われた全日本ラリー選手権のエピソードを紹介されました。アトラクションとして、往年のWRCチャンピオン、ビョルン・ワルデガルド氏に試走してもらいましたが、氏の駆るセリカツインカムターボを子供の頃にラジコン模型で作ったと言うファンの男性が、持参して来たその模型の上にサインをもらい、「25年越しの夢が叶った」と涙を浮かべて喜ばれていたとのことです。クルマはいつの時代も「夢と笑顔を運ぶもの」だ、というお話から講演は始まりました。
次には、車の動力源についてのお話でした。走行距離や車のサイズによって、電気、ハイブリッド、燃料電池が使い分けられていくのではないかとの考えと、その中で特にプラグインハイブリッド車の現況についての紹介がありました。講演中、友山様は、実際にご自身のプリウスPHVにスマートフォンでアクセスし、愛車の燃費データを紹介され、こまめに充電すればほとんどガソリンを使わないで走ることができる様子も見せてくださいました。そして、このような電動車の普及においては、いかにその電力を自然エネルギーで賄うか、またいかにピーク時の電力を使わずに充電するかが課題となることを示唆されました。
また、低炭素交通システムの実証実験では、豊田市でのスマートグリッドの紹介がありました。公共交通機関の利用を促進する課題となっている、目的地までの「最後の1マイル」の移動手段を確保するために、電気自動車を駅や公共施設に配置することが試みられています。また、通勤時など時間帯によっては駅から電気自動車がなくなってしまうこともあり得るので、逆方向に車を利用する人にはインセンティブを与えることなどにより、偏りを緩和して利便性と稼働率を向上させる試みも進んでいます。観光地の能登半島などでも、充電スタンドと観光情報基地を兼ねた拠点を20㎞毎に配置して、地域振興とプラグインハイブリッド車の普及を両立させるような取り組みもされているそうです。
加えて、エージェントシステムの紹介では、カーナビの情報をPull型からPush型に変えていくことでよりタイムリーな情報サービスが実現できるというお話をされました。過去の利用履歴を基にこれから走るルートを予測することで、途中の道路事情やいつも経由するコンビニの商品情報などを提供することができます。さらに近未来のパーソナルカーとして、スマートフォンに4つのタイヤを付けるというコンセプトで開発された「走る情報端末、Smart Insect」の紹介がありました。
また、本年から稼動開始したトヨタ自動車東日本では、大型の発電施設を併設し、自社工場はもちろん、工業団地内の複数企業にも電力を提供し、さらにその排熱を利用して大規模な温室で野菜栽培を行うという、農工融合型の「次世代ファクトリーグリッド」が計画されているそうです。
最後に、車は単なるプロダクトではなくお客様や社会との接点であり、車を生産することはお客様や社会との接点を増やしていくことにつながり、そこから新しいモータリゼーションが始まるという未来に向けた熱いメッセージもいただきました。
講演:「生産技術における日産バーチャル開発の現状と将来革新技術への考察」
日産自動車株式会社 常務執行役員 坂本秀行様

坂本様からは、バーチャル技術が物を作るということにどう貢献していくのかについてお話しいただきました。まず、生産技術の役割を、新しい技術を車という形にできるのかという仕事、実際に車を作る工場を準備するという仕事、そして生産されている車の品質、原価、納期を改善するという仕事、と3つの仕事に定義されました。そしてそれらについて、今取り組んでいる技術、少し先の技術、そして将来の技術についてのお話をいただきました。
今取り組んでいる技術としては、サイマルテイニアスエンジニアリングを挙げられ、企画、設計、生産準備の仕事をデジタルなプロセスを用いて同時並行で行い、開発プロセスを大幅に短縮されています。その中で特筆されたのが、ノウハウの標準化による設計工程の短縮と、シミュレーションによる性能の実験確認工程の短縮で、側面衝突実験の例を挙げてご説明いただきました。これらにおいてはフィジカルとバーチャルのシミュレーション結果における相関性の高さが求められます。また、デジタルプロセスに引き続いたフィジカルなプロセスにおいては、生産技術センターでの世界の工場に対応した生産設備の設置や作業者の育成などにより、全世界で同じ品質の設備が準備できるようになっています。
次に、少し先の技術としては、コモン・モジュール・ファミリー(CMF)という考え方についてご紹介いただきました。従来のプラットフォームの考え方では、同じプラットフォームでも重量に1トン以上の差が出ていたため、部品を分けてしまうということが起こっていました。CMFの考え方では、車を4つのモジュールと1つのE/E(電気/電子)アーキテクチャに分けてその共用化を重量や車両の形などの特徴で分類して分けていく考え方を取っています。エンジンコンパートメントはフードの高さ、コックピットは車両の形、そしてフロント、リアのアンダーボディは重量などで分けていく考え方になっています。このことで共用化率は、従来のプラットフォームの考え方では40%の部品が対象でしたが、これを最大80%までの部品を対象とすることができるようになり、実際約52%の部品を共用化することが可能になりました。
最後に将来の技術として、生産の形を根本的に見直していくということをお話しいただきました。今の自動車の生産形態は、T型フォードの量産化ラインの考え方が引き継がれていて、人の動きをロボットに置き換えたものになっています。将来的には、今の計測技術やロボットの特徴をもっと生かした生産方式が考えられるのではないかということです。例としては金型レスのプレス加工や、ドアの組み立て時に、隙間などを瞬時に計測することで最適な組み立てを行うなど新しい生産技術を考えられているということでした。これらの取り組みにより、コスト競争力の向上と多様化したニーズへの対応を狙っているとのことです。
日産様での生産技術の今と将来の姿をお聞きすることができ、大変得るところの大きな講演であったとの反響をいただきました。
パネルディスカッション:「複雑化するビジネスと今後のエンジニアリング情報管理」

今回はエンジニアリングITから業務側の設計・管理領域へと目を移し、従来とは違った視点からのパネルディスカッションでした。海外での開発や生産拠点でのビジネス拡大、あるいは他メーカーとの業務提携や新興国の活用などさまざまな形でグローバル化の動きが加速しています。また、3Dデータ活用による業務の大きな変革が進み、このような中で扱われる技術情報をどのように考え、今後に繋げていくべきかについて「複雑化するビジネスと今後のエンジニアリング情報管理」をテーマに議論を展開していただきました。
最初に、各社の技術情報管理部署のリーダーの皆様が所属されている、組織の位置付けと役割という大変興味深いご紹介と共に、一つ目のサブテーマである「技術情報管理の考え方と日常の取り組み」についてお話しいただきました。昨年の大震災を踏まえた防災対応の取り組み、BOM、CAD、技術情報、さらにはプロセスをグローバルに一元管理しようとする取り組みなど、皆様の所属部署がどのような役割を担い、推進されているかも含めご紹介いただきました。また一方で、グローバル化が進む中では避けられない、セキュリティ確保のための運用の効率化や、関係会社との連携強化などの課題についてもお話しいただきました。
自動車業界では90年代後半から3Dデータの活用が活発化し、現在では概ね定着化されてきていると言われている中、扱われる技術情報の増大化と共に、それら情報管理の重要性が改めて認識されています。次は「3Dデータ活用による業務や情報管理の変化」というテーマで、現在の課題や今後の方向性についてご説明いただきました。ここでは3Dデータの精度向上や効率化、具体的には新型車での基本構造の活用といったテクニカルな内容やDMUとBOMの連携機能のさらなる充実化がさまざまな課題とともに話題になりました。部品表の前倒しによる情報管理の複雑化などのハードルもありますが、3Dデータ活用に向けた次なるステップを垣間見ることができたと思います。また、やはり今年も2Dと3Dの共存について取り上げられました。各社様でどちらを正とするかは異なりますが、開発や生産拠点を海外へ展開していく上では、情報開示時の使い分けやルール作りも重要である、との認識で一致しました。
近年グローバル化という言葉が多用されており、各社様でも多岐に渡った取り組みを進められています。最後は「海外展開や業務提携などグローバル化に伴う情報管理」というサブテーマについてお話しいただきました。海外での生産や開発比率が増大し、企業グループ内だけでなくグループの壁を越えた技術提携も年々増加している中、グローバルエンジニアリング連携やサポートをしていく仕組み、海外同時開発における情報開示の内容やタイミングといった課題など、生々しい話も含めながらご紹介いただきました。
さらに、知財という視点でも、複雑化するビジネス形態の中で、ともすれば散在しかねない技術情報を管理できるかということについて、保護と活用の両立という観点を契約書に織り込むことの重要性についてのお話もありました。
会場のお客様からは、他ではなかなかご紹介いただけない内容を聞ける場として、各社の動向、現場の状況が聞けて良かった、担当業務と直結しており大変参考になった、との声もいただいています。私どもベンダーとしても、ますます複雑化していくビジネスに対応していこうと、各社様がいかに多くの課題に取り組まれているかを認識すると同時に、それらの課題をスピーディーに解決することの重要性を再認識させていただきました。
全体を通して
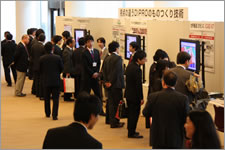
例年通り講演会場の外側通路にて弊社製品やソリューションの展示を行いました。短時間ではありましたが、各ブースでは、お客様からは具体的なご質問やご相談をいただきました。
セミナー終了後の懇親会では、昨年以上に会場が溢れんばかりのお客様にご来場いただき、あちらこちらでお客様同士が飲み物を片手にリラックスしたご様子で談笑されていました。初めてセミナーに参加された方にお聞きしたところ、予想以上に内容の濃いセミナーであり、経営トップに聞かせたい内容だったとのコメントをいただきました。情報交換の場としてだけでなく、異業種交流の場としてもご活用いただけたのではないかと思います。
アンケートでは、大変参考になったという多くのご意見と共に、今後の運営の参考にさせていただくべきさまざまなご意見もいただきました。また、お客様の業務に関するお悩みにつきましても今後、弊社営業やSEが詳細をお聞かせいただき、より良いご提案をさせていただければと思っております。今後もこのようにお役に立てる情報を発信しながら、お客様のお悩みを解決できる企業を目指し、社員一同精進してまいります。これからも弊社をご愛顧いただきますようよろしくお願い申し上げます。
(DIPROニュース編集局)
PICK UP












