DIPROニュース
オートモーティブデジタルプロセスセミナー
2015開催

12月4日(金)、パシフィコ横浜において「オートモーティブデジタルプロセスセミナー2015」を開催いたしました。ご来場の皆様ならびにご協力いただきました皆様に厚く御礼申し上げます。
自動車産業を俯瞰すると、直近では中国での自動車販売の変調をはじめとして、先行きが懸念される材料も有りますが、一方では、エマージェンシーブレーキの標準装着化や法制化等クルマの知能化に弾みをつける具体的な動き、そして、電動化の更なる進展や内燃機関の一層の効率向上に向けた新たな挑戦等、次世代に向けた技術開発が活発化し、世界的な開発競争となっているように感じられます。
こうした状況を背景に、今回は基調講演として、国立情報学研究所教授の新井紀子様に『人工知能の発達とそれにともなう社会変化』と題し、人工知能による大学入試への挑戦を切り口にAIが社会をどのように変えていくかをテーマにお話しいただきました。続いて自動車会社における先進の取り組み事例として、日産自動車株式会社 総合研究所長の土井三浩様に『都市交通のありかたと自動車の未来』と題し、自動車の電動化と知能化が未来の都市交通の中でどのような意義を持つかを、そして、マツダ株式会社統合制御システム開発本部 本部長の原田靖裕様に『高度なシステム開発とそれを支えるモデルベース開発』と題し、今や複雑化し、さらに電動化・知能化といった流れの中で更に高度化していく車載システムの開発を支えるモデルベースデザインについて、その現状と今後についてお話しいただきました。
そして締めくくりには、例年と同様に国内主要自動車メーカーのIT及び技術情報管理のキーマンであられます、トヨタ自動車株式会社の江口 浩二様、日産自動車株式会社の松木 幹雄様、株式会社本田技術研究所の中嶋 守様、マツダ株式会社の中村 貴樹様、三菱自動車工業株式会社の野村 雅彦様、スズキ株式会社の永井 利典様にご登壇いただき、各社の状況及び最新の課題について語っていただきました。

基調講演:『人工知能の発達とそれにともなう社会変化』
数理論理学
国立情報学研究所 情報社会相関研究系 教授
国立情報学研究所 社会共有知研究センター長 新井 紀子様

「ロボットは東大に入れるか」。新井様は冒頭、このプロジェクトをなぜ始めたか、という話から入りました。2010年の著書「コンピュータが仕事を奪う」の中で、2030年にはホワイトカラーの半分が消えるだろうという予測の下、社会インフラや教育の整備が急務であることを訴えましたが、当時何の反応もなかったことへの危機感がこのプロジェクトを始めるきっかけになりました。実は、「ロボットは東大に入れない」、「無人自動車も実現できない」とご自身では考えています。なぜそう思うのかについてを人口知能の可能性とともにお話しいただきました。
ビッグデータと機械学習によってロボットは東大に入れると考える人は多いが、果たしてそうだろうか。この問いに対して、犬と猫をどう分類するかといった身近な例を用いて、ビッグデータと機械学習(統計と論理)の成果と副作用について説明されました。
次に、東大の入試問題、国語の小林秀雄の論説問題、あるいは指定語句を用いて600字で論説させる世界史の問題を、人口知能(東ロボ君)にどのように考えさせて平均以上の点数をとることができたのかをご紹介いただきましたが、このことはもはや、ホワイトカラーの10人中5人は人工知能に間違いなく代替されるだろうと、近い将来を説明されました。
国家戦略的に集めたビッグデータから、分類と最適化により答えを出す手法を使う中国や、アメリカと違って、日本はビッグデータを集めにくい国であるため、ロジックと統計のハイブリッド手法により、日本のビッグでないデータ、ミディアムサイズのデータを深く読み込む技術を提供したいと考えています。
機械が得意な検索・検査・審査・最適化の仕事には、グローバル社会で勝ち残るためにも、人口知能を導入せざるを得ない、しかしながら機械は「意味がわかる」ということができない、そのため、“意味がわかる無人自動車”が作られる時代よりも、道路上のポテトチップスの袋と動物の違いがわかる“(新井様のような)免許を持たない人でも運転できる自動車”を実現する時代の方がはるかに近い、と断言されました。
「近未来の人口知能ができることを見極めることがこのプロジェクトの使命です。その成果を皆さんに毎年見ていただいて、ここまで機械がやれるようになった、人間よりも精度が出せるようになったと見極めていただき近未来のビジネスを考えていただく、そのためのプロジェクトなのです」。新井様は最後に力強く語られ、度々会場を笑いで沸かせ、お客様を惹きつけた1時間の講演を締めくくられました。
講演:『都市交通のありかたと自動車の未来』
日産自動車株式会社 理事 アライアンス グローバル ダイレクター
総合研究所長 土井 三浩様

土井様からは、これからの都市交通における自動車の方向性について、電気自動車日産LEAFの進化と自動運転化に向けての取り組みを交えお話いただきました。
1980年代以降、都市の発展と共に渋滞や事故、公害といった問題が顕在化し対策が講じられてきました。これからの都市交通は、単に乗り物側だけではなく道路環境等のインフラも同様に進化が続くと考えられるとのことでした。次に日産LEAFの状況ですが、これまで約20万台を販売しバッテリの重大不具合はゼロです。しかし、航続距離、充電時間など改善すべき課題もあります。一方、車をクラウドと繋ぐ試みを始めており、一例としては、データセンタに集まる日産LEAFの走行データをビッグデータを処理しているそうです。次に自動運転についてですが、自動運転化のモチベーションは、ドライバーのミスによる事故を無くしたいということです。基本は人が行う運転の3要素 認知・判断・操作 を機械に置き換えていくことですが、その上にAIを適用して安心して乗れる自動運転を目指します。しかし、“人が普通にできるようなことが出来ない”という場面はまだ沢山あるそうです。最後に『どこまで行けるかはチャレンジ。部分的な自動化から始まり、いつの日にか“完全”を目指したい。今日お越しの各社には、この取組みに積極的に参加いただき、一緒に車を進化をさせていきましょう』と結ばれました。
講演:『高度なシステム開発とそれを支えるモデルベース開発』
マツダ株式会社 統合制御システム開発本部 本部長 原田 靖裕様
マツダ様ではモデルベース開発(MBD開発)という言葉をプラントモデルを使った制御開発だけでなく、CAEを使ったシミュレーションなどを含めた広い意味で使っておられます。それを使って開発したのがデミオのSKYACTIVでした。デミオでは、エンジン、トランスミッション、ボディのすべてを一気に新開発しています。まさに失敗したら会社がつぶれるというほどの開発でした。その中でも特筆すべきなのが、圧縮比を15まで上げたガソリンエンジンの開発でした。圧縮比を上げるとトルクが落ちるという常識を破って、シミュレーションを徹底的に使いました。燃焼実験とシミュレーションが合わなかったときには、燃焼を可視化することで、圧縮時の渦が逆に発生していることを突き止めました。マツダ様では、今はシミュレーションが正なので、物をシミュレーションに合わせるという考え方になっています。最終的にMBD開発が目指すものは自動運転に代表されるような、巨大システムの開発です。自動運転によって安心・安全を提供することと走る喜びを提供することが両立できるのか。自動運転の技術によって、今は避けることができないような事故を回避できるようになります。マツダ様の求めるところは人を中心において、車がそれを助けるという自動運転です。それを支えていくのがMBD開発だと考えています。そしてその開発手法を日本の車メーカーで共通な手法として標準化していくことが、日本が第4次産業革命に勝ち残っていくために必要だと考えています。
パネルディスカッション
『自動車開発のデジタル化 PLM第2フェーズへの飛躍』
~エンジニアリング基幹システムの目指す方向性~

トヨタ自動車㈱ 江口 浩二様

日産自動車㈱ 松木 幹雄 様

㈱本田技術研究所 中嶋 守様

マツダ㈱ 中村 貴樹様

三菱自動車工業㈱ 野村 雅彦様

スズキ㈱ 永井 利典様

司会 半沢 克成

パネルディスカッション
自動車開発のデジタル化が成熟期を迎えている現在、自動車開発を取り巻くあらゆる周辺環境との密連携が重要になってきています。今回は「つなぐ」をキーワードに、何を目的に、何と何をつなごうとしているのか、またそれを支えるエンジニアリングITのあり方について、「自動車開発のデジタル化PLM 第2 フェーズへの飛躍 ~エンジニアリング基幹システムの目指す方向性~」というテーマに対し、3つのサブテーマの下に議論いただきました。
先ずは最初のサブテーマでもあるPLMの成果と課題ということで、これまでの各社の取り組みを含めご紹介いただきました。PLMによる開発期間の短縮、効率化という大きな成果は当然挙げられますが、一方で、デジタル化が進むにつれて設計者が考える機会が減少してきたという課題提起もありました。これについては、試作の復活、MBD等による“考える開発”への回帰、さらには設計者が考えるための設計情報共有化の取り組みを進められているというご意見がある一方で、考える機会の減少ではなく、環境の変化と共に設計者に求められる能力が変化してきている、これまで設計者が見えな かったところを可視化できるといったデジタル化の利点を考える必要がある、といった異なる視点でのご意見もありました。
また、設計情報の共有化という課題に対しては、CADデータ情報だけでなく失敗も含めた成果物をどう管理し、設計者にどのようにつなげ、生かしていくのか、また、MBDやサプライヤ連携含めたソフトウェア管理をPLMに取り込んでいくことの必要性など、次に向けた新たな課題も見えてきました。
最後に、部品にすべての最新情報を共有することで部品レベルでトレースできるという次世代のPLM構想についてもご紹介いただきました。
あっという間の1時間20分でした。まだまだお聞きしたい、聞き足りないというお客様も大勢いらしたのではないでしょうか。最後はそういった会場の思いと感謝の拍手でパネルディスカッションが終えられました。
全体を通して
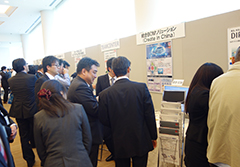
講演の合間の休憩時間には、講演会場外にて弊社及びグループ企業の製品やソリューションのデモ展示を行い、お客様から様々なご質問やご相談をいただきました。
また、セミナー終了後の懇親会も皆様にご参加いただき、盛況のうちに終えることができました。
アンケートでは、大変役に立ったとの声を多くいただきました。お客様の業務に関するお困りごとや様々なお悩みについては、弊社営業やSEが別途、詳細をお聞きして、より良いご提案をさせていただきたいと考えております。お客様のお役に立てる情報を発信しながら、お客様の悩みを解決できる企業をめざし、社員一同、さらに精進してまいりますので、今後とも弊社をご愛顧いただきますようお願い申し上げます。
PICK UP












