DIPROニュース
環境活動と明日のものづくり
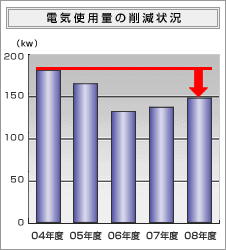

弊社は環境活動の理念として、「私たちの子孫とすべての生き物に蒼い空と碧い海、そしてみどりの大地を残すため、ITとものづくりの融合をめざすあらゆる企業活動を通じて、4つのR(Refuse, Reduce, Reuse, Recycle)に取り組みます」と謳っています。その行動指針として、お客様向けの製品販売・サービスを通じての「ものづくりのデジタル化」の推進や、環境負荷軽減の諸活動の推進、エコ商品の活用、地域の美化活動への協力などを挙げています。
弊社内における活動では省電力・省資源や資源再利用といった平凡ではありますが、着実な活動を進めております。これらの活動をスタートした頃(2004年)と比較してみますと、規範に沿った行動が随分と板に付いてきた感もあり、電源OFFの励行や文房具の再利用など抵抗なく行われていることが、社員の日々の行動からも窺えるようになりました。
しかし「これらの環境活動の結果が、どれだけ地球環境や将来の社会、次の世代に貢献できているだろうか?」と顧みてみると、自らに対して厳しい評価を下さざるを得ません。日々の電気の節約は、お金にすれば数千円ですし、山のように蓄えて回収したペットボトルのキャップもプリペイドカードも「自然の樹木を何本救ったのだろうか?それは何平米くらいの森になるのだろうか?」と考えてみると、大きな効果を出したとは言えないことに気付きます。実際の業務における、お客様への大量なマニュアルの出荷などが続けられていることを考えると、「毎日の活動が環境を良くしているのか、悪くしているのか」の答えは明白に思います。元より資源を消費する営みを続けられている製造業の各社様にとって、これらの葛藤は大きな悩みであるに違いないと拝察します。オフィスにおける環境活動は、そこに居る者の意識を高める目的が趣意と考えるべきであって、実質的な環境改善効果は微々たるものです。これら活動を地道に続けることは大変重要ですが、より大きな舵取りをしなければ、次の世代である「環境を受け取る者たち」に対して、顔向けできないように思います。より大きな舵取りとは言うまでもなく、本業においての環境配慮です。
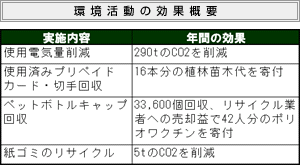
幸いなこと、といっては語弊があるでしょうが、昨年末からの世界経済のバランス喪失によって、私たちは物事の理(ことわり)や自分たちの在り方について、考え直さざるを得ない状況に追いやられました。そんな中で得られたものは、「人間の満足感や幸福感とは、金銭や資産によって満たされるものではない」という気付きや「もはや大量消費型の社会とは、決別することを考えなくてはならない」という自覚です。これら根源的に意識の転換を日常生活の中で現実化していくことや、一人ひとりが新たな価値観に従った行動を選び取っていくことでしか、傷付き、損なわれた地球の自然環境を回復させる方法は無いように思えます。
では、ものづくりをどのように変えれば、環境へ貢献できる事業活動ができるのでしょうか。
この答えについては関係会社を含め、議論をしたこともあります。解決への策は、まだまだ机上の論ではありますが「バーチャルな(デジタルな)ものづくりを徹底活用する」、(お客様には)「製品の品質を高め、エンドユーザー様に長く使っていただける、堅牢で保守性の高い製品を、必要とされる数だけ造っていただく」、さらに「お客様にお納めした製品については、永きにわたって保守・サポートする」といったようなことです。

言い換えると、企業が右肩上がりの拡大成長を前提とした時代、つまり消費型社会と決別し、オンデマンド型によりお客様の要求に沿った良質な製品を必要なだけ作り、大切に長く使っていただく、という経済構造に変えていくことが、限られた資源を最大限に活かす環境配慮型のものづくりであるということになります。これこそが、これからの製造業のあるべき姿ではないかと考えています。
ただし、これらは理屈としては簡単に言うことができますが、考えてみると事業構造の変革のみならず産業全体の就労人口の比率にも影響を与えかねないような大掛かりな話です。経営的な視点から実現の具体策を考えてみても、そう容易ではないことは確かです。当然ながら、こういった挑戦について自ら(自社)のことを棚に上げて、それを他(他社)へ要求するというのも不誠実な話でもあります。やはり、個々人が自らを変革する意志と覚悟をたずさえ、ひとつ一つの言行を変えていくことが要求されている時なのだと思います。
世界経済の方向性が混沌としている今の時代、経営レベルの課題は枚挙にいとまがありませんが、私たち全員が乗っている大きな船(地球)が、沈まないための試みを、皆で力を合わせて最優先で解決していく必要があると感じます。日常の小さな環境配慮の活動を行いながらも、皆様と共に、新しい時代のものづくり産業の在り方を模索していきたいと考えておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
(業務部 部長 吉野 琢也)
PICK UP












